公認野球規則
1.00 試合の目的
1.01 野球は、囲いのある競技場で、監督が指揮する9人のプレーヤーから成る二つのチームの間で、1人ないし数人の審判員の権限のもとに、本規則に従って行われる競技である。
1.02 攻撃側は、まず打者が走者となり、走者となれば進塁して得点することに努める。
1.03 守備側は、相手の打者が走者となることを防ぎ、走者となった場合は、その進塁を最小限にとどめるように努める。
1.04 打者が走者となり、正規にすべての塁に触れたときは、そのチームに1点が記録される。
1.05 各チームは、相手チームより多くの得点を記録して、勝つことを目的とする。
1.06 正式試合が終わったとき、本規則によって記録した得点の多い方が、その試合の勝者となる。
2.00 競技場
2.01 競技場の設定
競技場は、次にしるす要領により、巻頭1、2、3図のように設定する。
まず、本塁の位置を決め、その地点から二塁を設けたい方向に、鋼鉄製巻尺で、127㌳3⅜㌅(38.795㍍)の距離を測って二塁の位置を定める。次に本塁と二塁を起点としてそれぞれ90㌳(27.431㍍)を測り、本塁から向かって右側の交点を一塁とし、本塁から向かって左側の交点を三塁とする。したがって、一塁から三塁までの距離は127㌳3⅜㌅となる。
本塁からの距離は、一塁線と三塁線との交点を基点として測る。
本塁から投手板を経て二塁に向かう線は、東北東に向かっていることを理想とする。
90㌳平方の内野を作るには、まず各ベースライン(塁線)およびホームプレート(本塁)を同一水平面上に設け、続いて内野の中央付近に投手板をホームプレートより10㌅(25.4㌢)高い場所に設け、投手板の前方6㌅(15.2㌢)の地点から、本塁に向かって6㌳(182.9㌢)の地点まで、1㌳(30.5㌢)につき1㌅(2.5㌢)の傾斜をつけ、その傾斜は各競技場とも同一でなければならない。
本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は、60㌳(18.288㍍)以上を推奨する。(1図参照)
外野は、1図に示すように、一塁線および三塁線を延長したファウルラインの間の地域である。本塁よりフェアグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は250㌳(76.199㍍)以上を必要とするが、両翼は320㌳(97.534㍍)以上、中堅は400㌳(121.918㍍)以上あることが優先して望まれる。
境界線(ファウルラインおよびその延長として設けられたファウルポール)を含む内野および外野は、フェアグラウンドであり、その他の地域はファウルグラウンドである。
キャッチャースボックス、バッタースボックス、コーチスボックス、スリーフット・ファーストベースラインおよびネクスト・バッタースボックスは巻頭1、2図のように描く。
図表中のファウルラインおよび太線で示されている諸線は、塗料、または無害かつ不燃性のチョーク、その他の白い材料で描く。
巻頭1図のグラスライン(芝生の線)および芝生の広さは、多くの競技場が用いている規格を示したものであるが、その規格は必ずしも強制されるものではなく、各クラブは任意に芝生および芝生のない地面の広さや形を定めることができる。
ただし、以下の場合を除く。
(a)内野の境目となるグラスラインは、投手板の中心から半径95 ㌳(28.955 ㍍)の距離とし、前後各1㌳については許容される。しかし、投手板の中心から94 ㌳(28.651㍍)未満や96 ㌳(29.26 ㍍)を超える箇所があってはならない。
(b)本塁一塁間のベースラインに沿ったフェアテリトリの内野のグラスライン(芝生の線)はベースラインから18 ㌅(45.7 ㌢)以上、24 ㌅(61.0 ㌢)以下でなければならない。
【注】我が国では、本項(a)および(b)については、適用しない。
【軟式注】学童部では、投手板と本塁間および各塁間の距離を次のとおりとする。塁間の距離は23㍍。投手板と本塁との距離は16㍍。
2.02 本塁
本塁は五角形の白色のゴム板で表示する。この五角形を作るには、まず1辺が17㌅(43.2㌢)の正方形を描き、17㌅の1辺を決めてこれに隣り合った両側の辺を8½㌅(21.6㌢)とする。それぞれの点から各12㌅(30.5㌢)の2辺を作る。12㌅の2辺が交わった個所を本塁一塁線、本塁三塁線の交点に置き、17㌅の辺が投手板に面し、二つの12㌅の辺が一塁線および三塁線に一致し、その表面が地面と水平になるように固定する。(巻頭2図参照)
2.03 塁
一塁、二塁、三塁は、白色のキャンバスまたはゴムで被覆されたバッグで表示し、巻頭2図に示すように地面に正しく固定する。
一塁と三塁のバッグは、完全に内野の内に入るように設置し、二塁のバッグは、図表の二塁の地点にその中心が来るように設置する。
キャンバスバッグはその中に柔らかい材料を詰めて作り、その大きさは18㌅(45.7㌢)
平方、厚さは3㌅(7.6㌢)ないし5㌅(12.7㌢)である。
【注】我が国では、一塁、二塁、三塁のキャンバスバックの大きさは15㌅(38.1㌢)平方とする。
2.04 投手板
投手板は横24㌅(61.0㌢)縦6㌅(15.2㌢)の長方形の白色ゴムの平板で作る。投手板は巻頭1、2、3図に示す個所の地面に固定し、その前縁の中央から本塁(五角形の先端)までの距離は60㌳6㌅(18.44㍍)とする。
2.05 ベンチ
ホームクラブは、ホームチーム用およびビジティングチーム用として、各1個のプレーヤースベンチを設け、これには左右後方の三方に囲いをめぐらし、屋根を設けることが必要である。
3.00 用具・ユニフォーム
3.01 ボール
3.02 バット
3.03 ユニフォーム
3.04 捕手のミット
3.05 一塁手のグラブ
3.06 野手のグラブ
3.07 投手のグラブ
(a)投手のグラブは、縁取りを除き白色、灰色以外のものでなければならない。審判員の判断によるが、どんな方法であっても幻惑させるものであってはならない。
守備位置に関係なく、野手はPANTONEの色基準14番よりうすい色のグラブを使用することはできない。
【注】アマチュア野球では、投手のグラブについては、縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体(捕球面、背面、網)は1色でなければならない。
(b)投手は、そのグラブの色と異なった色のものを、グラブにつけることはできない。
(c)球審は、自らの判断または他の審判員の助言があれば、あるいは相手チームの監督からの異議に球審が同意すれば、本来(a)または(b)項に違反しているグラブを取り替えさせる。
3.08 ヘルメット
プロフェッショナルリーグでは、ヘルメットの使用について、次のような規則を採用しなければならない。
(a)プレーヤーは、打撃時間中および走者として塁に出ているときは、必ず野球用ヘルメットをかぶらなければならない。
(b)マイナーリーグのプレーヤーは、打撃に際して両耳フラップヘルメットを着用しなければならない。
(c)メジャーリーグのプレーヤーは、片耳フラップヘルメット(プレーヤーが両耳フラップヘルメットを選んでもよい)を着用しなければならない。
【注】アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。
【3.08原注】審判員は各項に対する規則違反を認めた場合には、これを是正するように命じる。審判員の判断で、適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反者を試合から除くことができる。
(d)捕手が守備についているときは、捕手の防護用のヘルメットを着用しなければならない。
(e)ベースコーチは、コーチスボックスにいるときには、防護用のヘルメットを着用しなければならない。
(f)バットボーイ、ボールボーイまたはバットガール、ボールガールは、その仕事にたずさわっているときは、防護用の両耳フラップヘルメットを着用しなければならない。
3.09 商業的宣伝
3.10 競技場内の用具
4.00 試合の準備
4.01 審判員の任務
審判員は、試合開始前に、次のことをしなければならない。
(a)競技に使用される用具、およびプレーヤーの装具が、すべて規則にかなっているかどうかを厳重に監視する。
(b)塗料、チョーク、その他の白色材料で引かれた競技場の諸線(図表1、2の太線)が、地面または芝生からはっきりと見分けがつくようにできあがっているかどうかを確かめる。
(c)正規のボール(リーグ会長がホームクラブに対して、その個数および製品について証明済みのもの)を、ホームクラブから受け取る。審判員はボールを検査し、ボールの光沢を消すため特殊な砂を用いて適度にこねられていることを確認する。審判員は、その単独判断でボールの適否を決定する。
【注】アマチュア野球では、ボールはホームチームまたは主催者が供給する。
(d)正規のボールを少なくとも1ダース、必要に応じてただちに使用できるように、ホームクラブが準備しているかどうかを確かめる。
(e)少なくとも2個のボールを予備に持ち、試合中、必要に応じてその都度、予備のボールの補充を要求する。これらのボールを、次の場合に使用する。
(1)ボールがプレイングフィールドの外へ出た場合。
(2)ボールが汚れた場合、あるいはボールがなんらかの理由で使えなくなった場合。
(3)投手がボールの交換を求めた場合。
【原注】球審は、ボールデッドとなりすべてのプレイが終わるまでに投手にボールを手渡してはならない。フェアの打球または野手の送球がプレイングフィールドの外へ出た場合は、走者および打者が与えられた塁に達するまで、予備のボールを渡してプレイを再開してはならない。また、打者がプレイングフィールドの外へ本塁打を打ったときは、その打者が本塁を踏み終わるまで球審は、新しいボールを投手または、捕手に手渡してはならない。
(g)球審は、暗くなったので、それ以降のプレイに支障をきたすと認めたときは、いつでも競技場のライトを点灯するように命じることができる。
(f)試合開始前に公認ロジンバッグが投手板の後方に置かれていることを確認する。
4.02 監督
(a)クラブは試合開始予定時刻30分前までに、リーグ会長、または当該試合の球審に対して監督を指定しなければならない。
(b)監督は、プレーヤーまたはコーチにリーグの規約に基づく特別な任務を任せたことを、球審に通告することができる。
この通告があれば本野球規則は、この指名された代表者を公式のものとして認める。
監督は自チームの行動、野球規則の遵守、審判員への服従に関しては、全責任を持つ。
(c)監督が競技場を離れるときは、プレーヤー、またはコーチを自己の代表者として指定しなければならない。このような監督の代理者は監督としての義務、権利、責任を持つ。もし、監督が競技場を離れるまでに、自己の代理者を指定しなかったり、これを拒否した場合には、球審がチームの一員を監督の代理者として指定する。
4.03 打順表の交換
ホームクラブが試合の延期または試合開始の遅延をあらかじめ申し出た場合を除いて、1人ないし、数人の審判員は、試合開始予定時刻の5分前に競技場内に入り、ただちに本塁に進み、両チームの監督に迎えられる。
(a)まず、ホームチームの監督、または監督が指名した者が、球審に2通の打順表を手渡す。
(b)次に、ビジティングチームの監督、または監督が指名した者が、球審に2通の打順表を手渡す。
(c)球審に手渡される打順表には、各プレーヤーの守備位置も記載されなければならない。指名打者を使用する場合は、どの打者が指名打者であるのかを打順表に明記しなければならない。
(d)球審は、受領した打順表の正本が副本と同一であるかどうかを照合した後、相手チームの監督にそれぞれ打順表の副本を手交する。球審の手元にあるものが正式の打順表となる。球審による打順表の手交は、それぞれの打順表の確定を意味する。したがって、それ以後、監督がプレーヤーを交代させるには規則に基づいて行わなければならない。
(e)ホームチームの打順表が球審に手渡されると同時に、競技場の全責任は、各審判員に託される。そして、その時を期して、球審は天候、競技場の状態などに応じて、試合打ち切りの宣告、試合の一時停止あるいは試合再開などに関する唯一の決定者となる。
球審はプレイを中断した後、少なくとも30分を経過するまでは、打ち切りを命じてはならない。また球審はプレイ再開の可能性があると確信すれば、一時停止の状態を延長してもさしつかえない。
【4.03原注】球審は、試合開始の〝プレイ〟を宣告する前に、打順表における明らかな誤記を見つけた場合、まず誤記をしたチームの監督またはキャプテンに注意し、それを訂正させることができる。たとえば、監督が不注意にも打順表に8人しか記載しなかったり、同性の2人を区別する頭文字をつけないで記載した場合、球審がこれらの誤記を試合開始前に見つけたら、訂正されなければならない。明らかな不注意や試合開始前に訂正できる誤りのために、試合が始まってからチームが束縛されるべきではない。
球審は、いかなる場合でも、試合を完了するように努力しなければならない。試合完了の確信があれば、球審は、その権限において、30分にわたる〝一時停止〟を何度くり返しても、あくまで試合を続行するように努め、試合の打ち切りを命じるのは、その試合を完了させる可能性がないと思われる場合だけである。
【注】アマチュア野球では、次の試合に出場するプレーヤーがスタンドで観戦することを許す場合もある。
4.04 競技場使用の適否の決定権
(a)ホームチームだけが、天候、競技場の状態が試合を開始するのに適しているかどうかを決定する権限を持っている。ただし、ダブルヘッダーの第2試合の場合を除く。
【例外】全日程が消化できず、そのリーグの最終順位が、実際の勝敗の結果によらずに決まることがないようにするために、最終の数週間、そのリーグに限って、本条の適用を中止する権限を、そのリーグの会長に全面的に付与することができる。たとえば、選手権試合の終期の節において、いずれか2チーム間の試合を延期したり、または挙行しなかったことが、リーグの最終順位に影響を及ぼすおそれのある場合には、そのリーグ所属チームの要請によって、本条によるホームチームに付与されている権限を、リーグ会長が持つことができる。
【注】アマチュア野球では、本項を適用しない。
(b)ダブルヘッダーの第1試合の球審だけが、天候、競技場の状態がダブルヘッダーの第2試合を開始するのに適しているかを決定する権限を持っている。
4.05 特別グラウンドルール
観衆が競技場内にあふれ出ている場合、ホームチームの監督は、打球、送球が観衆内に入ったときはもちろん、不測の事態が生じた場合など、あらゆる点を考慮して、広範囲に及ぶグラウンドルールを作って、球審ならびに相手チームの監督に指示して承諾を求める。相手チームの監督がこれを承諾すれば、そのグラウンドルールは正規のものとなるが、万一承諾しないときは、球審はプレイに関する規則に抵触しない範囲内で、競技場の状態から推測して必要と思われる特別グラウンドルールを作成して、これを実行させる。
4.06 ユニフォーム着用者の禁止事項
ユニフォーム着用者は、次のことが禁じられる。
(1)プレーヤーが、試合前、試合中、または試合終了後を問わず、観衆に話しかけたり、席を同じくしたり、スタンドに座ること。
(2)監督、コーチまたはプレーヤーが、試合前、試合中を問わず、いかなるときでも観衆に話しかけたり、または相手チームのプレーヤーと親睦的態度をとること。
【注】アマチュア野球では、次の試合に出場するプレーヤーがスタンドで観戦することを特に許す場合もある。
4.07 安全対策
(a)試合中は、ユニフォームを着たプレーヤーおよびコーチ、監督、ホームチームによって公認されている報道写真班、審判員、制服を着た警官、ならびにホームチームの警備員、その他の従業員のほかは、競技場内に入ってはならない。
(b)ホームチームは、秩序を維持するのに十分な警察の保護を要請する備えをしておく義務がある。1人もしくは2人以上の人が試合中に競技場内に入り、どんな方法ででもプレイを妨害した場合には、ビジティングチームは、競技場からそれらの人々が退去させられるまで、プレイを行なうことを拒否することができる。
ペナルティ ビジティングチームがプレイを行なうことを拒否してから、15分を経過した後、なお適宜な時間をかけても競技場からそれらの人々が退去させられなかった場合には、球審はフォーフィッテッドゲームを宣告してビジティングチームの勝ちとすることができる。
【注1】ここにいう〝適宜な時間〟とは、球審の判断に基づく適宜な時間を意味する。
フォーフィッテッドゲームは、同僚との協議の末、球審がとる最後の手段であって、すべての手段が尽き果てた後に、初めてこれを宣告するもので、料金を払って試合を見にきているファンを失望させることは極力避けなければならない。
【注2】アマチュア野球では、ホームチームに代わって大会主催者、連盟などがその責にあたる。
4.08 ダブルヘッダー
(a)(1)選手権試合は、1日2試合まで行なうことができる。サスペンデッドゲームを完了させるために、ダブルヘッダーとともに行なっても、本条項に抵触することにはならない。
(2)もし、同じ日に、一つの入場料で2試合が組まれている場合には、第1試合をその当日における正規の試合としなければならない。
(b)ダブルヘッダーの第2試合は、第1試合の完了後でなければ開始してはならない。
(c)ダブルヘッダーの第2試合は、第1試合の終了30分後に開始する。ただし、この2試合の間にこれ以上の時間(45分を超えないこと)を必要とするときは、第1試合終了時に、球審はその旨を宣告して相手チームの監督に通告しなければならない。
【例外】ホームクラブが特別な行事のために、2試合の間を規定以上に延長したいと申し出て、リーグ会長がこれを承認した場合には、球審はこの旨を宣告して、相手チームの監督に通告しなければならない。どの場合でも、第1試合の球審は、第2試合が開始されるまでの時間を監視する任にあたる。
【注】両チーム監督の同意を得れば、ダブルヘッダーの第2試合を、第1試合の終了後30分以内に開始してもさしつかえない。
(d)審判員は、ダブルヘッダーの第2試合をできる限り開始し、そして競技は、グラウンドコンディション、地方時間制限、天候状態などの許す限り、続行しなければならない。
(e)正式に日程に組まれたダブルヘッダーが、降雨その他の理由で、開始が遅延した場合には、開始時間には関係なく開始されたその試合がダブルヘッダーの第1試合となる。
(f)日程の変更により、ある試合をダブルヘッダーの一つに組み入れた場合は、その試合は第2試合となり、正式にその日の日程に組まれている試合が、第1試合となる。
(g)ダブルヘッダーの第1試合と第2試合の間、または試合が競技場使用不適のため停止されている場合、競技場をプレイに適するようにするため、球審は球場管理人およびその助手を指図することができる。
ペナルティ 球場管理人およびその助手が球審の指図に従わなかった場合には、球審は、フォーフィッテッドゲームを宣告して、ビジティングチームに勝ちを与えることが許される。(7.03c)
5.00 試合の進行
5.01 試合の開始
(a)ホームチームの各プレーヤーが、それぞれの守備位置につき、ビジティングチームの第1打者が、バッタースボックス内に位置したとき、球審はプレイを宣告し、試合が開始される。
(b)球審が〝プレイ〟を宣告すればボールインプレイとなり、規定によってボールデッドとなるか、または審判員が〝タイム〟を宣告して試合を停止しない限り、ボールインプレイの状態は続く。
(c)まず、投手は打者に投球する。その投球を打つか打たないかは打者が選択する。
5.02 守備位置
試合開始のとき、または試合中ボールインプレイとなるときは、捕手を除くすべての野手はフェア地域にいなければならない。
(a)捕手は、ホームプレートの直後に位置しなければならない。
故意の四球が企図された場合は、ボールが投手の手を離れるまで、捕手はその両足をキャッチャースボックス内に置いていなければならないが、その他の場合は、捕球またはプレイのためならいつでもその位置をはなれてもよい。
ペナルティ ボークとなる。(6.02a12参照)
(b)投手は、打者に投球するにあたって、正規の投球姿勢をとらなければならない。
(c)投手と捕手を除く各野手は、フェア地域ならば、どこに位置してもさしつかえない。
【注1】投手が打者に投球する前に、捕手以外の野手がファウル地域に位置を占めることは、本条で禁止されているが、これに違反した場合のペナルティはない。
審判員がこのような事態を発見した場合には、速やかに警告してフェア地域に戻らせた上、競技を続行しなければならないが、もし、警告の余裕がなく、そのままプレイが行なわれた場合でも、この反則行為があったからといってすべての行為を無効としないで、その反則行為によって守備側が利益を得たと認められたときだけ、そのプレイは無効とする。
内野手の守備位置については、次のとおり規定する。
(ⅰ)投手が投手板に触れて、打者への投球動作および投球に関連する動作を開始するとき、4人の内野手は、内野の境目より前に、両足を完全に置いていなければならない。
(ⅱ)投手が打者に対して投球するとき、4人の内野手のうち、2人ずつは二塁ベースの両側に分かれて、両足を位置した側に置いていなければならない。
(ⅲ)二塁ベースの両側に分かれた2人の内野手は、投手がそのイニングの先頭打者に初球を投じるときから、そのイニングが完了するまで、他方の側の位置に入れ替わったり、移動したりできない。
ただし、守備側のプレーヤーが交代したとき(投手のみの交代は除く)は、いずれの内野手も他方の側の位置に入れ替わったり、移動してもかまわない。
イニングの途中で内野手として正規に出場したプレーヤーは、その交代後に投手が打者に投じるときから、そのイニングが完了するまで、他方の側の位置に入れ替わったり、移動したりできない。(そのイニングで、その後再び別の交代があった場合は除く)。
【原注】審判員は、内野手の守備位置に関する本項の目的として、投手が投球する前に打者がどこへ打つのかを予測して、二塁ベースのどちらかの側に3人以上の内野手が位置するのを防ぐことであることに留意しなければならない。いすれかの野手が本項を出し抜こうとしたと審判員が判断した場合、次のペナルティが適用される。
ペナルティ 守備側チームが本項に違反した場合、投手の投球にはボールが宣告され、ボールデッドとなる。
ただし、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に達し、しかも他の全走者が少なくとも1個の塁を進んだときには、規則違反とは関係なく、プレイが続けられる。もし、本項に違反した後に、他のプレイ(たとえば、犠牲フライ、犠牲バントなど)があった場合は、攻撃側の監督は、そのプレイが終わってからただちに、違反行為に対するペナルティの代わりに、そのプレイを生かす旨を球審に通告することができる。
【注2】我が国では、本項後段の内野手の守備位置については、適用しない。
5.03 ベースコーチ
(a)攻撃側チームは、攻撃期間中、2人のベースコーチ──1人は一塁近く、他は三塁近く──を所定の位置につかせなければならない。
(b)ベースコーチは、各チーム特に指定された2人に限られ、そのチームのユニフォームを着なければならない。
(c)ベースコーチは、本規則に従いコーチスボックス内にとどまらなければならない。ただし、コーチが、プレーヤーに「滑れ」「進め」「戻れ」とシグナルを送るために、コーチスボックスを離れて、自分の受け持ちのベースで指示することは、プレイを妨げない限り許される。ベースコーチは、用具の交換を除き、特にサイン交換がなされている場合などには、走者の身体に触れてはならない。
ペナルティ コーチは、打球が自分を通過するまで、コーチスボックスを出て、本塁寄りおよびフェア地域寄りに立っていてはならない。相手チーム監督の異議申し出があったら、審判員は、規則を厳しく適用しなければならない。審判員は、そのコーチに警告を発し、コーチスボックスに戻るように指示しなければならない。警告にもかかわらず、コーチスボックスに戻らなければ、そのコーチは試合から除かれる。加えて、リーグ会長が制裁を科す対象となる。
【注1】監督が指定されたコーチに代わって、ベースコーチとなることはさしつかえない。
【注2】アマチュア野球では、ベースコーチを必ずしも特定の2人に限る必要はない。
【注3】コーチがプレイの妨げにならない範囲で、コーチスボックスを離れて指図することは許されるが、たとえば、三塁コーチが本塁付近にまできて、得点しようとする走者に対して、「滑れ」とシグナルを送るようなことは許されない。
5.04 打者
(a)打撃の順序
(1)攻撃側の各プレーヤーはそのチームの打順表に記載されている順序に従って打たなければならない。
(2)試合中、打撃順の変更は認められない。しかし、打順表に記載されているプレーヤーが控えのプレーヤーと代わることは許される。ただし、その控えのプレーヤーは退いたプレーヤーの打撃順を受け継がなければならない。
(3)第2回以後の各回の第1打者は、前回正規に打撃(タイムアットバット)を完了した打者の次の打順のものである。
(b)打者の義務
(1)打者は自分の打順がきたら、速やかにバッタースボックスに入って、打撃姿勢をとらなければならない。
(2)打者は、投手がセットポジションをとるか、またはワインドアップを始めた場合には、バッタースボックスの外に出たり、打撃姿勢をやめることは許されない。
ペナルティ 打者が本項に違反した際、投手が投球すれば、球審はその投球によってボールまたはストライクを宣告する。
【原注】打者は、思うままにバッタースボックスを出入りする自由は与えられていないから、打者が〝タイム〟を要求しないで、バッタースボックスをはずしたときに、ストライクゾーンに投球されれば、ストライクを宣告されてもやむを得ない。
打者が打撃姿勢をとった後、ロジンバッグやパインタールバッグを使用するために、打者席から外に出ることは許されない。ただし、試合の進行が遅滞しているとか、天候上やむを得ないと球審がみとめたときは除く。
審判員は、投手がワインドアップを始めるか、セットポジションをとったならば、打者または攻撃側チームのメンバーのいかなる要求があっても〝タイム〟を宣告してはならない。たとえ、打者が〝目にごみが入った〟〝眼鏡がくもった〟〝サインが見えなかった〟など、その他どんな理由があっても、同様である。球審は、打者が打者席に入ってからでも〝タイム〟を要求することを許してもよいが、理由なくして打者席から離れることを許してはならない。球審が寛大にしなければしないほど、打者は打者席の中にいるのであり、投球されるまでそこにとどまっていなければならないということがわかるだろう。(5.04b4参照)
打者が打者席に入ったのに、投手が正当な理由もなくぐずぐずしていると球審が判断したときには、打者がほんの僅かの間、打者席を離れることを許してもよい。走者が塁にいるとき、投手がワインドアップを始めたり、セットポジションをとった後、打者が打者席から出たり、打撃姿勢をやめたのにつられて投球をはたさなかった場合、審判員はボークを宣告してはならない。投手と打者との両者が規則違反をしているので、審判員はタイムを宣告して、投手も打者もあらためて〝出発点〟からやり直させる。
以下はマイナーリーグだけに適用される〔原注〕の追加事項である。走者が塁にいるとき、投手がワインドアップを始めたり、セットポジションをとった後、打者が打者席から出たり、打撃姿勢をやめたのにつられて投球を果たさなかった場合、審判員はボークを宣告してはならない。打者のこのような行為は、バッターボックスルールの違反として扱い、5.04(b)(4)(A)に定められたペナルティを適用する。
(3)打者が、バッタースボックス内で打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審はストライクを宣告する。この場合はボールデッドとなり、いずれの走者も進塁できない。
このペナルティの後、打者が正しい打撃姿勢をとれば、その後の投球は、その投球によってボールまたはストライクがカウントされる。打者が、このようなストライクを3回宣告されるまでに、打撃姿勢をとらなかったときは、アウトが宣告される。
【原注】球審は、本項により打者にストライクを宣告した後、再びストライクを宣告するまでに、 打者が正しい打撃姿勢をとるための適宜な時間を認める。
(4)バッタースボックスルール
(A)打者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を除き、少なくとも一方の足をバッタースボックス内に置いていなければならない。この場合は、打者はバッタースボックスを離れてもよいが、〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出てはならない。
(ⅰ)打者が投球に対してバットを振った場合。
(ⅱ)チェックスイングが塁審にリクエストされた場合。
(ⅲ)打者が投球を避けてバランスを崩すか、バッタースボックスの外に出ざるを得なかった場合。
(ⅳ)いずれかのチームのメンバーが〝タイム〟を要求し認められた場合。
(ⅴ)守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者に対するプレイを企てた場合。
(ⅵ)打者がバントをするふりをした場合。
(ⅶ)暴投または捕逸が発生した場合。
(ⅷ)投手がボールを受け取った後マウンドの土の部分を離れた場合。
(ⅸ)捕手が守備のためのシグナルを送るためキャッチャースボックスを離れた場合。
打者が意図的にバッタースボックスを離れてプレイを遅らせ、かつ前記(ⅰ)~(ⅸ)の例外規定に該当しない場合、当該試合におけるその打者の最初の違反に対しては球審が警告を与え、その後違反が繰り返されたときにはリーグ会長が然るべき制裁を科す。マイナーリーグでは、当該試合におけるその打者の2度目以降の違反に対して、投手が投球をしなくても球審はストライクを宣告する。この際、ボールデッドで、走者は進塁できない。
【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。
(B)打者は、次の目的で〝タイム〟が宣告されたときは、バッタースボックスおよび〝ホームプレートを囲む土の部分〟を離れることができる。
(ⅰ)負傷または負傷の可能性がある場合。
(ⅱ)プレーヤーの交代
(ⅲ)いずれかのチームの協議
【原注】審判員は、前の打者が塁に出るかまたはアウトになれば、速やかにバッタースボックスに入るよう次打者に促さねばならない。
(5)打者は、正規の打撃姿勢をとるためには、バッタースボックスの内にその両足を置くことが必要である。
【規則説明】 バッタースボックスのラインは、バッタースボックスの一部である。
(c)打撃の完了
打者は、アウトになるか、走者となったときに、打撃を完了したことになる。
5.05 打者が走者となる場合
(a)次の場合、打者は走者となる。
(1)フェアボールを打った場合。
【原注】投球が地面に触れた後、打者がこれを打ってバットに当たった場合には、インフライトの投球を打ったときと同様に扱う。
(2)(A)走者が一塁にいないとき、(B)走者が一塁にいても2アウトのとき、捕手が第3ストライクと宣告された投球を捕らえなかった場合。
【原注】第3ストライクと宣告されただけで、まだアウトになっていない打者が、気が付かずに、一塁に 向かおうとしなかった場合、その打者は〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出たらただちにアウトが宣告される。
(3)投球が地面に触れた後、ストライクゾーンを通過しても、ボールであり、このバウンドした投球が打者に触れた場合は、球審の裁定で打者に一塁を与える。ただし、2ストライク後打者が打ったがバットに当たらなかったときは、捕手がそのままつかんでも〝捕球〟したものとはみなされない。(5.05b2、5.09a3)
(4)野手(投手を除く)を通過したか、または野手(投手を含む)に触れたフェアボールが、フェア地域で審判員または走者に触れた場合。(走者については、6.01a11参照)
(5)フェア飛球が、本塁からの距離が250㌳(76.199㍍)以上あるフェンスを越えるか、スタンドに入った場合、打者がすべての塁を正規に触れれば、本塁打が与えられる。
フェア飛球が、本塁からの距離が250㌳(76.199㍍)未満のフェンスを越えるか、スタンドに入った場合は、二塁打が与えられる。
(6)フェアボールが、地面に触れた後、バウンドしてスタンドに入った場合、またはフェンス、スコアボード、灌木およびフェンス上のつる草を抜けるか、その下をくぐるか、挟まって止まった場合には、打者、走者ともに2個の進塁権が与えられる。
【注】〝地面に触れた〟とあるのは、インフライトでない状態を指す。
(7)フェアボール(地面に触れたものでも、地面に触れないものでも)が、フェンス、スコアボード、灌木およびフェンス上のつる草を抜けるか、その下をくぐった場合、フェンスまたはスコアボードの隙間を抜けた場合、あるいはフェンス、スコアボード、灌木およびフェンスのつる草に挟まって止まった場合には、打者、走者ともに2個の進塁権が与えられる。
(8)バウンドしたフェアボールが、野手に触れて進路が変わり、フェア地域またはファウル地域のスタンドに入った場合か、フェンスを越えるか、くぐるかした場合、打者、走者、ともに2個の進塁権が与えられる。
(9)フェア飛球が野手に触れて進路が変わり、
(A)ファウル地域のスタンドに入るか、またはファウル地域のフェンスを越えた場合──打者に二塁が与えられる。
(B)フェア地域のスタンドに入るか、またはフェア地域のフェンスを越えた場合──打者に本塁が与えられる。
ただし(B)の場合、そのスタンドまたはフェンスが、本塁から250㌳(76.199㍍)未満の距離にあるときは、打者に二塁が与えられるだけである。
【注】(a)項各規定で、打者、走者ともに2個の進塁権が与えられる場合は、投手の投球当時に占有していた塁を基準とする。
(b)打者は、次の場合走者となり、アウトにされるおそれなく、安全に一塁が与えられる。(ただし、打者が一塁に進んで、これに触れることを条件とする)
(1)審判員が〝四球〟を宣告した場合。
【原注】監督からのシグナルを得て審判員より一塁を与えられた打者を含む、ボール4個を得て一塁への安全進塁権を得た打者は、一塁へ進んでかつこれに触れなければならない義務を負う。これによって、塁上の走者は次塁への進塁を余儀なくされる。この考え方は、満塁のときおよび代走者を出場させるときにも適用される。
打者への〝四球〟の宣告により、進塁を余儀なくされた走者が何らかのプレイがあると思い込んで塁に触れずにまたは触れてからでも、その塁を滑り越してしまえば、野手に触球されるとアウトになる。また、与えられた塁に触れそこなってその塁よりも余分に進もうとした場合には、身体またはその塁に触球されればアウトになる。
(2)打者が打とうとしなかった投球に触れた場合。
ただし、(1) バウンドしない投球が、ストライクゾーンで打者に触れたとき、(2) 打者が投球を避けないでこれに触れたときは除かれる。
バウンドしない投球がストライクゾーンで打者に触れた場合には、打者がこれを避けようとしたかどうかを問わず、すべてストライクが宣告される。
しかし、投球がストライクゾーンの外で打者に触れ、しかも、打者がこれを避けようとしなかった場合には、ボールが宣告される。
【規則説明】打者が投球に触れたが一塁を許されなかった場合も、ボールデッドとなり、各走者は進塁できない。
【原注】投球が打者の身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具にだけ触れた場合には、その打者が投球に触れたものとはみなさない。
【注1】〝投球がストライクゾーンで打者に触れた〟ということは、ホームプレートの上方空間に限らず、これを前後に延長した空間で打者に触れた場合も含む。
【注2】投球が、ストライクゾーンの外で打者に触れた場合でも、その投球が、ストライクゾーンを通っていたときには、打者がこれを避けたかどうかを問わず、ストライクが宣告される。
【注3】打者が投球を避けようとしたかどうかは、一に球審の判断によって決定されるものであって、投球の性質上避けることができなかったと球審が判断した場合には、避けようとした場合と同様に扱われる。
【注4】投球がいったん地面に触れた後、これを避けようと試みた打者に触れた場合も、打者には一塁が許される。ただし、ストライクゾーンを通ってからバウンドした投球に触れた場合を除く。
(3)捕手またはその他の野手が、打者を妨害(インターフェア)した場合。しかし、妨害にもかかわらずプレイが続けられたときには、攻撃側チームの監督は、そのプレイが終わってからただちに、妨害行為に対するペナルティの代わりに、そのプレイを生かす旨を通告することができる。
ただし、妨害にもかかわらず、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に達し、しかも他の全走者が少なくとも1個の塁を進んだときは、妨害とは関係なく、プレイは続けられる。
【原注】捕手の妨害が宣告されてもプレイが続けられたときは、そのプレイが終わってからこれを生かしたいと監督が申し出るかもしれないから、球審はそのプレイを継続させる。
打者走者が一塁を空過したり、走者が次塁を空過しても、〔5.06b3付記〕に規定されているように、塁に到達したものとみなされる。
監督がプレイを選ぶ場合の例。
①1アウト走者三塁、打者が捕手に妨げられながらも外野に飛球を打ち、捕球後三塁走者が得点した。監督は、打者アウトで得点を記録するのと、走者三塁、一塁(打者が打撃妨害により出塁)とのいずれを選んでもよい。
②0アウト走者二塁、打者は捕手に妨げられながらもバントして走者を三塁に進め、自らは一塁でアウトになった。監督は、0アウト走者二塁、一塁とするよりも、走者三塁で1アウトとなる方を選んでもよい。
三塁走者が盗塁またはスクイズプレイにより得点しようとした場合のペナルティは、6.01(G)に規定されている。
投手が投球する前に、捕手が打者を妨害した場合、打者に対する妨害とは考えられるべきではない。このような場合には、審判員は〝タイム〟を宣告して〝出発点〟からやり直させる。
【注1】監督がプレイを生かす旨を球審に通告するにあたっては、プレイが終わったら、ただちに行なわれなければならない。なお、いったん通告したら、これを取り消すことはできない。
【注2】監督がペナルティの適用を望んだ場合、次のとおり解釈できる。
捕手(または他の野手)が打者を妨害した場合、打者には一塁が与えられる。三塁走者が盗塁またはスクイズプレイによって得点しようとしたときに、この妨害があった場合にはボールデッドとし、三塁走者の得点を認め、打者には一塁が与えられる。
三塁走者が盗塁またはスクイズプレイで得点しようとしていなかったときに、捕手が妨害した場合にはボールデッドとし、打者に一塁が与えられ、そのために塁を明け渡すことになった走者は進塁する。盗塁を企てていなかった走者と塁を明け渡さなくてもよい走者とは、妨害発生の瞬間に占有していた塁にとめおかれる。
(4)野手(投手を含む)に触れていないフェアボールが、フェア地域で審判員または走者に触れた場合。
ただし、内野手(投手を除く)をいったん通過するか、または野手(投手を含む)に触れたフェアボールが審判員に触れた場合にはボールインプレイである。
5.06 走者
(a)塁の占有
(1)走者がアウトになる前に他の走者の触れていない塁に触れれば、その塁を占有する権利を獲得する。
その走者は、アウトになるか、または、その塁に対する正規の占有権を持っている他の走者のためにその塁を明け渡す義務が生じるまで、その権利が与えられる。
【5.06a・c原注】走者が塁を正規に占有する権利を得て、しかも投手が投球姿勢に入った場合は、元の占有塁に戻ることは許されない。
(2)2人の走者が同時に一つの塁を占有することは許されない。ボールインプレイの際、2人の走者が同一の塁に触れているときは、その塁を占有する権利は前位の走者に与えられているから、後位の走者はその塁に触れていても触球されればアウトとなる。ただし本条(b)(2)項適用の場合を除く。
(b)進塁
(1)走者は進塁するにあたり、一塁、二塁、三塁、本塁の順序に従って、各塁に触れなければならない。逆走しなければならないときも、5.06(c)の各項規定のボールデッドとなっていない限り、すべての塁を逆の順序で、再度触れて行かなければならない。前記のボールデッドの際は、途中の塁を踏まないで、直接元の塁へ帰ることはさしつかえない。
【注1】ボールインプレイ中に起きた行為(たとえば悪送球、ホームランまたは柵外に出たフェアヒットなど)の結果、安全進塁権が認められたときでも、走者が、進塁または逆走するにあたっては、各塁に正規に触れなければならない。
【注2】〝逆走しなければならないとき〟というのは、
①フライが飛んでいるうちに次塁に進んだ走者が、捕球されたのを見て帰塁しようとする場合(5.09b5参照)
②塁を空過した走者が、その塁を踏み直す場合(5.09c2参照)
③自分よりも前位の走者に先んじるおそれがある場合(5.09b9参照)
を指すものであって、このようなときでも、逆の順序で各塁に触れなければならない
(2)打者が走者となったために進塁の義務が生じ、2人の走者が後位の走者が進むべき塁に触れている場合には、その塁を占有する権利は後位の走者に与えられているので、前位の走者は触球されるか、野手がボールを保持してその走者が進むべき塁に触れればアウトになる。(5.09b6参照)
(3)次の場合、打者を除く各走者は、アウトにされるおそれなく1個の塁が与えられる。
(A)ボークが宣告された場合。
(B)打者が次の理由で走者となって一塁に進むために、その走者が塁を明け渡さなければならなくなった場合。
①打者がアウトにされるおそれなく、一塁に進むことが許された場合。
②打者の打ったフェアボールが、野手(投手を含む)に触れる前か、または野手(投手を除く)を通過する前に、フェア地域で審判員もしくは他の走者に触れた場合。
【原注】安全進塁権を得た走者が、与えられた塁に触れた後さらに進塁することはさしつかえないが、その行為の責任はその走者自身が負うだけで、たとえ与えられた塁に触れた後にアウトになった場合でも、他の走者の安全進塁権に影響を及ぼすことはない。
したがって、2アウト後その走者が与えられた塁に触れた後にアウトになり、第3アウトが成立しても安全進塁権がある前位の走者は、そのアウトの後で本塁を踏んでも得点として認められる。
例──2アウト満塁、打者四球、二塁走者が勢いこんで、三塁を回って本塁の方へ向かってきたが、捕手からの送球で触球アウトとなった。たとえ2アウト後であっても、四球と同時に三塁走者が本塁に押し出されたので、すべての走者に次塁へ進んで触れる必要が生まれたという理論に基づいて得点が記録される。
【注】本項〔原注〕は、打者が四球を得たために、塁上の各走者に次塁への安全進塁権が与えられた場合だけに適用される。
(C)野手が飛球を捕らえた後、《ボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合。》
【原注】野手が正規の捕球をした後、《ボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合、》ボールデッドとなり、各走者は野手が《ボールデッドの個所に入ったとき》の占有塁から1個の進塁が許される。
(D)走者が盗塁を企てたとき、打者が捕手またはその他の野手に妨害(インターフェア)された場合。
【注】本項は、盗塁を企てた塁に走者がいない場合とか、進もうとした塁に走者がいても、その走者もともに盗塁を企てていたために次塁への進塁が許される場合だけに適用される。しかし、進もうとした塁に走者があり、しかもその走者が盗塁を企てていない場合には、たとえ盗塁行為があってもその走者の進塁は許されない。また単に塁を離れていた程度では本項は適用されない。
(E)野手が帽子、マスク、その他着衣の一部を本来つけている個所から離して、投球に故意に触れさせた場合。
この際はボールインプレイで、ボールに触れたときの走者の位置を基準に塁が与えられる。
【5.06b3付記】ボールインプレイのもとで1個の塁に対する安全進塁権を得た走者が、その塁を踏まないで次塁に進もうとした場合、および2個以上の塁に対する安全進塁権を得た走者が、与えられた最終塁に達した後はボールインプレイになる規則のもとで、その塁を踏まないで次塁へ進もうとした場合は、いずれもその走者は安全進塁権を失ってアウトにされるおそれがある状態におかれる。したがって、その進むことが許された塁を踏み損ねた走者は、その空過した塁に帰る前に、野手によってその身体またはその塁に触球されれば、アウトとなる。
【注】たとえば、打者が右中間を抜こうとするような安打を打ったとき、右翼手が止めようとしてこれにグラブを投げつけて当てたが、ボールは外野のフェンスまで転じ去った。打者は三塁を空過して本塁へ進もうとしたが、途中で気がついて三塁へ踏み直しに帰ろうとした。この際、打者はもはや三塁へ安全に帰ることは許されないから、その打者が三塁に帰る前に、野手が打者または三塁に触球してアピールすれば、打者はアウトになる。(5.06b4C参照)
(4)次の場合、各走者(打者走者を含む)は、アウトにされるおそれなく進塁することができる。
(A)本塁が与えられる得点が記録される場合──フェアボールがインフライトの状態でプレイングフィールドの外へ出て、しかも、各走者が正規に各塁を触れた場合。また、フェアボールがインフライトの状態で、明らかにプレイングフィールドの外へ出ただろうと審判員が判断したとき、野手がグラブ、帽子、その他着衣の一部を投げつけて、その進路を変えた場合。
【注1】フェアの打球がインフライトの状態で、明らかにプレイングフィールドの外へ出ただろうと審判員が判断したとき、観衆や鳥などに触れた場合には、本塁が与えられる。
送球またはインフライトの打球が、鳥に触れた場合は、ボールインプレイでありインフライトの状態は続く。しかし、プレイングフィールド上(地上)の鳥または動物に触れた場合は、ボールインプレイであるが、インフライトの状態でなくなる。また、投球が鳥に触れた場合は、ボールデッドとしてカウントしない。犬などがフェアの打球、送球または投球をくわえたりした場合には、ボールデッドとして審判員の判断によって処置する。
【注2】〝その進路を変えた場合〟とあるが、インフライトの状態で、明らかにプレイングフィールドの外へ出ただろうと審判員が判断したフェアの打球が、野手の投げつけたグラブなどに触れて、グラウンド内に落ちたときでも、本項が適用される。
(B)3個の塁が与えられる場合──野手が、帽子、マスクその他着衣の一部を、本来つけている個所から離して、フェアボールに故意に触れさせた場合。
この際はボールインプレイであるから、打者はアウトを賭して本塁に進んでもよい。
(C)3個の塁が与えられる場合──野手が、グラブを故意に投げて、フェアボールに触れさせた場合。
この際はボールインプレイであるから、打者はアウトを賭して本塁に進んでもよい。
【注】ここにいうフェアボールとは、野手がすでに触れていたかどうかを問わない。
(D)2個の塁が与えられる場合──野手が、帽子、マスクその他着衣の一部を、本来つけている個所から離して、送球に故意に触れさせた場合。
この際はボールインプレイである。
(E)2個の塁が与えられる場合──野手が、グラブを故意に投げて、送球に触れさせた場合。
この際はボールインプレイである。
【BCDE原注】投げたグラブ、本来の位置から離した帽子、マスクその他がボールに触れなければ、このペナルティは適用されない。
【CE原注】このペナルティは、打球または送球の勢いにおされて、野手の手からグラブが脱げたとき、あるいは正しく捕らえようと明らかに努力したにもかかわらず、野手の手からグラブが脱げた場合などには、適用されない。
【BCDE注】野手より、本項の行為がなされた場合の走者の進塁の起点は、野手が投げたグラブ、本来の位置から離した帽子、マスクその他が打球または送球に触れた瞬間とする。
(F)2個の塁が与えられる場合──フェアの打球が、
①バウンドしてスタンドに入るか、または野手に触れて進路が変わって、一塁または三塁のファウル線外にあるスタンドに入った場合。
②競技場のフェンス、スコアボード、灌木、またはフェンスのつる草を抜けるか、その下をくぐるか、挟まって止まった場合。
(G)2個の塁が与えられる場合──送球が、
①競技場内に観衆があふれ出ていないときに、スタンドまたはベンチに入った場合。(ベンチの場合は、リバウンドして競技場に戻ったかどうかを問わない。)
②競技場のフェンスを超えるか、くぐるか、抜けた場合。
③バックストップの上部のつぎ目から、上方に斜めに張ってある金網に上がった場合。
④観衆を保護している金網の目に挟まって止まった場合。
この際は、ボールデッドとなる。
審判員は2個の進塁を許すにあたって、次の定めに従う。すなわち、打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づく悪送球であった場合には、投手の投球当時の各走者の位置、その他の場合は、悪送球が野手の手を離れたときの各走者の位置を基準として定める。
【規則説明】悪送球が打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づくものであっても、打者を含む各走者が少なくとも1個の塁を進んでいた場合には、その悪送球が内野手の手を離れたときの各走者の位置を基準として定める。
【原注】ときによっては、走者に2個の塁が与えられないこともある。
たとえば、走者一塁のとき、打者が浅い右翼飛球を打った。走者は一塁二塁間で立ち止まっており、打者は一塁を過ぎて走者の後ろまできた。打球は捕らえられず、外野手は一塁に送球したが送球はスタンドに入った。すべてボールデッドとなったときは、走者は進む権利を与えられた塁以上には進塁できないから、一塁走者は三塁へ、打者走者は二塁まで進む。
規則説明 〝悪送球がなされたとき〟という術語が、その送球が実際に野手の手を離れたときのことであって、地面にバウンドした送球がこれを捕ろうとした野手を通過したときとか、スタンドの中へ飛び込んでプレイからはずれたときのことではない。
内野手による最初の送球がスタンドまたはダッグアウトに入ったが、打者が走者となっていない(三塁走者が捕逸または暴投を利して得点しようとしたときに、アウトにしようとした捕手の送球がスタンドに入った場合など)ような場合は、その悪送球がなされたときの走者の位置を基準として2個の進塁が許される。(5.06b4Gの適用に際しては、捕手は内野手とみなされる)
例──走者一塁、打者が遊ゴロを打った。遊撃手は、二塁でフォースアウトしようとして送球したが間に合わなかった。二塁手は打者が一塁を通り過ぎてから一塁手に悪送球した。──二塁に達してした走者は得点となる。(このようなプレイで、送球がなされたとき、打者走者が一塁に達していなかったときは、打者走者は二塁が許される)
(H) 1個の塁が与えられる場合──打者に対する投手の投球、または投手板上から走者をアウトにしようと試みた送球が、スタンドまたはベンチに入った場合、競技場のフェンスまたはバックストップを超えるか、抜けた場合。
この際はボールデッドとなる。
【規則説明】投手の投球が捕手を通過した後(捕手が触れたかどうかを問わない)、ダッグアウト、スタンドなどボールデッドの個所に入った場合、および投手板に触れている投手が走者をアウトにしようと試みた送球が直接前記の個所に入った場合、1個の塁が与えられる。
しかしながら、投球または送球が、捕手または他の野手を通過した後、プレイングフィールド内にあるボールを捕手または野手が蹴ったり、捕手または野手にさらに触れたりして、前記の個所に入った場合は、投球当時または送球当時の走者の位置を基準として2個の塁が与えられる。
(I)四球目、三振目の投球が、捕手のマスクまたは用具、あるいは球審の身体やマスクまたは用具に挟まって止まった場合、1個の塁が与えられる。
ただし、打者の四球目、三振目の投球が(h)および(i)項規定の状態になっても、打者には一塁が与えられるにすぎない。
【原注1】走者がアウトにされることなく1個またはそれ以上の塁が与えられたときでも、与えられた塁またはその塁に至るまでの途中の塁に触れる義務を負うものである。
例──打者が内野にゴロを打ち、内野手の悪送球がスタンドに飛び込んだ。打者走者は一塁を踏まないで二塁に進んだ。打者走者は二塁を許されたわけだが、ボールインプレイになった後、一塁でアピールされればアウトになる。
【原注2】飛球が捕らえられたので元の塁に帰らなければならない走者は、グラウンドルールやその他の規則によって、余分の塁が与えられたときでも投手の投球当時の占有塁のリタッチを果たさなければならない。この際、ボールデッド中にリタッチを果たしてもよい。また、与えられる塁はリタッチを果たさなければならない塁が基準となる。
【注】打者の四球目または三振目の投手の投球が、(H)項〔規則説明〕後段の状態になったときは、打者にも二塁が与えられる。
(c)ボールデッド
次の場合にはボールデッドとなり、走者は1個の進塁が許されるか、または帰塁する。その間に走者はアウトにされることはない。
(1)投球が、正規に位置している打者の身体、または着衣に触れた場合──次塁に進むことが許された走者は進む。
(2)球審が、盗塁を阻止しようとしたり、塁上の走者をアウトにしようとする捕手の送球動作を妨害(インターフェア)した場合──各走者は戻る。
【付記】捕手の送球が走者をアウトにした場合には、妨害はなかったものとする。
【原注】捕手の送球動作に対する球審の妨害には、投手への返球も含む。
【注】捕手の送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はただちに〝タイム〟を宣告して、走者を元の塁に戻す。
ボールデッドとなった際は、各プレーヤーはアウトになったり、進塁したり、帰塁したり、得点することはできない。
ただし、ボールインプレイ中に起きた行為(たとえば、ボーク、悪送球、インターフェア、ホームランまたはプレイングフィールドの外に出たフェアヒット)などの結果、1個またはそれ以上の進塁が認められた場合を除く。
(3)ボークの場合──各走者は進む。(6.02aペナルティ参照)
(4)反則打球の場合──各走者は戻る。
(5)ファウルボールが捕球されなかった場合──各走者は戻る。
球審は塁上の走者が、元の塁にリタッチするまで、ボールインプレイの状態にしてはならない。
(6)内野手(投手を含む)に触れていないフェアボールが、フェア地域で走者または審判員に触れた場合、あるいは内野手(投手を除く)を通過していないフェアボールが、審判員に触れた場合──打者が走者となったために、塁を明け渡す義務が生じた各走者は進む。
走者がフェアボールに触れても、次の場合には、審判員はアウトを宣告してはならない。なお、この際は、ボールインプレイである。
(A)いったん内野手に触れたフェアボールに触れた場合。
(B)1人の内野手に触れないでその股間または側方を通過した打球にすぐその後方で触れても、このボールに対して他のいずれの内野手も守備する機会がなかったと審判員が判断した場合。
【原注】打球が投手を通過してから、内野内に位置していた審判員に触れた場合は、ボールデッドとなる。フェア地域で野手によってそらされた打球が、まだインフライトの状態のまま、走者または審判員に触れ地上に落ちるまでに、内野手によって捕球されても、捕球とはならず、ボールインプレイの状態は続く。
【注】フェアボールがファウル地域で審判員に触れた場合、ボールインプレイである。
(7)投球が、捕手のマスクまたは用具、あるいは球審の身体やマスクまたは用具に挟まって止まった場合──各走者は進む。
【原注】チップした打球が、球審に当たってはね返ったのを、野手が捕らえても、ボールデッドとなって、打者はアウトにはならない。チップした打球が、球審のマスクに挟まって止まっても、同様である。
第3ストライクと宣告された投球が、捕手を通過して球審に当たったときは、ボールインプレイである。球審に当たってはね返ったボールが、地上に落ちる前に捕球されても、打者はただちにアウトにはならない。ボールインプレイであり、打者は一塁に触れる前に、身体または一塁に触球されて、初めてアウトになる。
第3ストライクと宣告された投球または四球目の投球が、球審か捕手のマスクまたは用具に挟まって止まった場合、打者には一塁が与えられ、塁上の走者には1個の進塁が許される。
(8)正規の投球が、得点しようとしている走者に触れた場合──各走者は進む。
5.07 投手
(a)正規の投球姿勢
投球姿勢にはワインドアップポジションと、セットポジションとの二つの正規のものがあり、どちらでも随時用いることができる。
投手は、投手板に触れて捕手からのサインを受けなければならない。
【原注】 投手がサインを見終わってから、投手板を外すことはさしつかえないが、外した後はすばやく投手板に踏み出して投球することは許されない。このような投球は、審判員によってクイックピッチと判断される。投手は、投手板を外したら、必ず両手を身体の両側に下ろさなければならない。
投手が、サインを見終わるたびに投手板を外すことは許されない。
投手は投球に際して、どちらの足も本塁の方向に2度目のステップを踏むことは許されない。塁に走者がいるときには、6.02(b)により反則投球となる。
(1)ワインドアップポジション
投手は、打者に面して立ち、その軸足は投手板に触れて置き、他の足の置き場には制限がない。
この姿勢から、投手は、
①打者への投球動作を起こしたならば、中断したり、変更したりしないで、その投球を完了しなければならない。
②実際に投球するときを除いて、どちらの足も地面から上げてはならない。ただし、実際に投球するときには、自由な足(軸足でない足)を1歩後方に引き、さらに1歩前方に踏み出すこともできる。
投手が軸足を投手板に触れて置き(他の足はフリー)、ボールを両手で身体の前方に保持すれば、ワインドアップポジションをとったものとみなされる。
【原注1】ワインドアップポジションにおいては、投手は軸足でない足(自由な足)を投手板の上か、前方か、後方かまたは側方に置くことが許される。
【原注2】 (1)項の姿勢から、投手は、
①打者に投球してもよい。
②走者をアウトにしようとして塁に踏み出して送球してもよい。
③投手板を外してもよい(ボールを両手で保持した投手は、投手板から外したら必ず両手を身体の両側に下ろさなければならない)。投手板を外すときには、最初に軸足から外さなければならない。
また、前記の姿勢から、セットポジションに移ったり、ストレッチをすることは許されない。──違反すればボークとなる。
【注】投手が投球に関連する動作をして、身体の前方で両手を合わせたら、打者に投球すること以外は許されない。したがって、走者をアウトにしようとして塁に踏み出して送球することも、投手板を外すこともできない。違反すればボークとなる。
(2)セットポジション
投手は、打者に面して立ち、軸足を投手板に触れ、他の足を投手板の前方に置き、ボールを両手で身体の前方に保持して、完全に動作を静止したとき、セットポジションをとったとみなされる。
この姿勢から、投手は、
①打者に投球しても、塁に送球しても、軸足を投手板の後方(後方に限る)に外してもよい。
②打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更したりしないで、その投球を完了しなければならない。
セットポジションをとるに際して〝ストレッチ〟として知られている準備動作(ストレッチとは、腕を頭上または身体の前方に伸ばす行為をいう)を行なうことができる。しかし、ひとたびストレッチを行なったならば、打者に投球する前に、必ずセットポジションをとらなければならない。
投手は、セットポジションをとるに先立って、片方の手を下に下ろして身体の横につけていなければならない。この姿勢から、中断することなく、一連の動作でセットポジションをとらなければならない。
投手は、ストレッチに続いて投球する前には(a)ボールを両手で身体の前方に保持し、(b)完全に静止しなければならない。審判員は、これを厳重に監視しなければならない。投手は、しばしば走者を塁に釘づけにしようと規則破りを企てる。投手が〝完全な静止〟を怠った場合には、審判員は、ただちにボークを宣告しなければならない。
【原注】走者が塁にいない場合、セットポジションをとった投手は、必ずしも完全静止をする必要はない。
しかしながら、投手が打者のすきをついて意図的に投球したと審判員が判断すれば、クイックピッチとみなされ、ボールが宣告される。6.02(a)(5)〔原注〕参照。
塁に走者がいるときに、投手が投手板に軸足を並行に触れ、なおかつ自由な足を投手板の前方に置いた場合には、この投手はセットポジションで投球するものとみなされる。
【注1】(1)(2)項でいう〝中断〟とは、投手が投球動作を起こしてから途中でやめてしまったり、投球動作中に一時停止したりすることであり、〝変更〟とは、ワインドアップポジションからセットポジション(または、その逆)に移行したり、投球動作から塁への送球(けん制)動作に変更することである。
【注2】投手がセットポジションをとるにあたっては、投手板を踏んだ後投球するまでに、必ずボールを両手で保持したことを明らかにしなければならない。その保持に際しては、身体の前面ならどこで保持してもよいが、いったん両手でボールを保持して止めたならば、その保持した個所を移動させてはならず、完全に身体の動作を停止して、首以外はどこも動かしてはならない。
【注3】セットポジションからの投球に際して、自由な足は、
①投手板の真横に踏み出さない限り、前方ならどの方向に踏み出しても自由である。
②ワインドアップポジションの場合のように、1歩後方に引き、そして更に1歩踏み出すことは許されない。
【注4】投手は走者が塁にいるとき、セットポジションをとってからでも、プレイの目的のためなら、自由に投手板を外すことができる。この場合、軸足は必ず投手板の後方に外さなければならず、側方または前方に外すことは許されない。投手が投手板を外せば、打者への投球はできないが、走者のいる塁には、ステップをせずに、スナップだけで送球することも、また送球のまねをすることも許される。
【注5】ワインドアップポジションとセットポジションとの区別なく、軸足を投手板に触れてボールを両手で保持した投手が、投手板から軸足を外すにあたっては、必ずボールを両手で保持したまま外さなければならない。また、軸足を投手板から外した後には、必ず両手を離して身体の両側に下ろし、あらためて軸足を投手板に触れなければならない。
【問】投手がストレッチを行なってから、セットポジションをとるまでに、両手を顔の前で接触させ、そのまま下ろし、胸の前でボールを保持した。ボークになるか。
【答】たとえ顔の前で両手を接触させても、そのままの連続したモーションで、胸の前に下ろして静止すれば、ボークにはならない。しかし、いったん顔の前で停止すれば、そこでボールを保持したことになるから、その姿勢から両手を下に下ろせばボークとなる。
(b)準備投球
投手は各回のはじめに登板する際、あるいは他の投手を救援する際には、捕手を相手に8球を超えない準備投球をすることは許される。この間プレイは停止される。
各リーグは、その独自の判断で、準備投球の数を8球以下に制限してもさしつかえない。このような準備投球は、いずれの場合も1分間を超えてはならない。
突然の事故のために、ウォームアップをする機会を得ないで登板した投手には、球審は必要と思われる数の投球を許してもよい。
(c)投手の遅延行為
塁に走者がいないとき、投手はボールを受けた後12秒以内に打者に投球しなければならない。投手がこの規則に違反して試合を長引かせた場合には、球審はボールを宣告する。
12秒の計測は、投手がボールを所持し、打者がバッタースボックスに入り、投手に面したときから始まり、ボールが投手の手から離れたときに終わる。
この規則は、無用な試合引き延ばし行為をやめさせ、試合をスピードアップするために定められたものである。したがって、審判員は次のことを強調し、それにもかかわらず、投手の明らかな引き延ばし行為があったときには、遅滞なく球審はボールを宣告する。
(1)投球を受けた捕手は、速やかに投手に返球すること。
(2)また、これを受けた投手は、ただちに投手板を踏んで、投球位置につくこと。
(d) 塁に送球
投手が、準備動作を起こしてからでも、打者への投球動作を起こすまでなら、いつでも塁に送球することができるが、それに先立って、送球しようとする塁の方向へ、直接踏み出すことが必要である。
【原注】投手は送球の前には、必ず足を踏み出さなければならない。スナップスロー(手首だけで送球すること)の後で、塁に向かって踏み出すようなことをすればボークとなる。
【注】投手が投手板を外さずに一塁へ送球する場合、投手板上で軸足が踏みかわっても、その動作が一挙動であればさしつかえない。しかし、送球前に軸足を投手板の上でいったん踏みかえた後で送球すれば、軸足の投手板上の移行としてボークとなる。
(e)軸足を外したとき
投手がその軸足を投手板の後方に外したときは、内野手とみなされる。したがって、その後、塁に送球したボールが悪送球となった場合には、他の内野手による悪送球と同様に取り扱われる。
【原注】投手は、投手板を離れているときならば、意のままに走者のいる塁ならどの塁に送球してもよいが、もしその送球が悪送球となれば、その送球は内野手の送球とみなされ、その後の処置は、野手の送球に関する規則が適用される。(5.06b4G)
(f)両手投げ投手
投手は、球審、打者および走者に、投手板に触れる際に、どちらかの手にグラブをはめることで、投球する手を明らかにしなければならない。
投手は、打者がアウトになるか走者になるか、攻守交代になるか、打者に代打者が出るか、あるいは投手が負傷するまでは、投球する手を変えることはできない。投手が負傷したために、同一打者の打撃中に投球する手を変えれば、その投手は以降再び投球する手を変えることはできない。投手が投球する手を変えたときには、準備投球は認められない。
投球する手の変更は、球審にはっきりと示さなければならない。
5.08 得点の記録
(a)3人アウトになってそのイニングが終了する前に、走者が正規に一塁、二塁、三塁、本塁に進み、かつこれに触れた場合には、その都度、1点が記録される。
【例外】第3アウトが次のような場合には、そのアウトにいたるプレイ中に、走者(1、2にあたる場合は全走者、3にあたる場合は後位の走者)が本塁に進んでも、得点は記録されない。
(1)打者走者が一塁に触れる前にアウトにされたとき。(5.09a、6.03a参照)
(2)走者がフォースアウトされたとき。(5.09b6参照)
(3)前位の走者が塁に触れ損ねてアウトにされたとき。(5.09c1・2、同d参照)
【原注】たとえば、三塁走者が、飛球が捕らえられてから、離塁して本塁を踏んだ後、離塁が早かったと誤信して、三塁に帰ろうとした場合のように、走者が正規の走塁を行なって本塁に触れたならば、その走者のそれ以後の行為によって、その得点は無効とはならない。
【注1】第3アウトがフォースアウト以外のアウトで、そのプレイ中に他の走者が本塁に達した場合、審判員は、その走者にアピールプレイが残っているか否かに関係なく、本塁到達の方が第3アウトより早かったか否かを明示しなければならない。
【注2】本項は打者および塁上の走者に安全進塁権が与えられたときも適用される。たとえば、2アウト後ある走者が他の走者に先んじたためにアウトになったときは、そのアウトになった走者よりも後位の打者または走者の得点が認められないことはもちろんであるが、たとえアウトになった走者より前位の走者でも第3アウトが成立するまでに本塁を踏まなければ得点は認められない。
ただし、2アウト満塁で、打者が四球を得たとき、他のいずれかの走者がいったん次塁を踏んだ後にアウトになったときだけ、その第3アウトが成立した後に三塁走者が本塁を踏んでも、得点と認められる。(5.06b3b〔原注〕参照)
(b)正式試合の最終回の裏、または延長回の裏、満塁で、打者が四球、死球、その他のプレイで一塁を与えられたために走者となったので、打者とすべての走者が次の塁に進まねばならなくなり三塁走者が得点すれば勝利を決する1点となる場合には、球審は三塁走者が本塁に触れるとともに、打者が一塁に触れるまで、試合の終了を宣告してはならない。
【原注】例外として観衆が競技場になだれこんで、走者が本塁に触れようとするのを、または打者が一塁に触れようとするのを肉体的に妨げた場合には、審判員は観衆のオブストラクションとして走者の得点または進塁を認める。
ペナルティ 前記の場合、三塁走者が、適宜な時間がたっても、あえて本塁に進もうとせず、かつこれに触れようとしなかった場合には、球審は、その得点を認めず、規則に違反したプレーヤーにアウトを宣告して、試合の続行を命じなければならない。
また、2アウト後、打者走者があえて一塁に進もうとせず、かつこれに触れようとしなかった場合には、その得点を認めず、規則に違反したプレーヤーにアウトを宣告して、試合続行を命じなければならない。
0アウトまたは1アウトのとき、打者走者があえて一塁に進もうとせず、かつこれに触れようとしなかった場合には、その得点は記録されるが、打者走者はアウトを宣告される。
【注】たとえば、最終回の裏、満塁で、打者が四球を得たので決勝点が記録されるような場合、次塁に進んで触れる義務を負うのは、三塁走者と打者走者だけである。三塁走者または打者走者が適宜な時間がたっても、その義務を果たそうとしなかった場合に限って、審判員は、守備側のアピールを待つことなくアウトの宣告を下す。
打者走者または三塁走者が進塁に際して塁に触れ損ねた場合も、適宜な時間がたっても触れようとしなかった場合に限って、審判員は、守備側のアピールを待つことなく、アウトの宣告を下す。
【5.08原注】 規則説明 打者走者のアウトが一塁に触れる前のアウトの形をとり、それが第3アウトにあたったときは、たとえ他の走者がアウトの成立前か、あるいはそのアウトが成立するまでのプレイ中に本塁に触れていても得点は記録されない。
〔例〕 1アウト走者一・二塁のとき打者が安打したので、二塁走者は本塁に達したが、一塁走者は本塁への送球でアウトにされて2アウトとなった。この間、打者走者は二進していたが、途中一塁を踏んでいなかったので一塁でアピールされて打者はアウトになり、3アウトとなった。──二塁走者は〝打者走者が一塁に触れる前のアウトで、しかも第3アウトにあたる場合〟のプレイ中に本塁に触れたのであるから、その得点は記録されない。
規則説明 2アウト以前であれば、前位の走者の行為によって後位の走者が影響を受けることはない。
〔例〕 1アウト走者一・二塁のとき、打者は場内本塁打を打った。二塁走者は本塁へ達する間に三塁を空過した。一塁走者と打者は正しく塁を踏んで本塁に達した。守備側は三塁に送球してアピールしたので、審判員は二塁走者に対してアウトを宣告して、2アウトとなった。── 一塁走者と打者の得点は認められる。
規則説明 2アウト走者一・二塁のとき、打者が場内本塁打を打ち、3人とも本塁を踏んだが、二塁走者は三塁を空過したので、アピールによってアウトにされ、3アウトとなった。──一塁走者と打者は正しく本塁を踏んではいるが、得点は数えられない。
規則説明 1アウト走者二・三塁のとき、打者が中堅飛球を打ってアウトになり、2アウトとなった。三塁走者はそのフライアウトを利して本塁に触れ、二塁走者も本塁への悪送球によって得点した。このとき三塁走者に対してアピールがあり、捕球前に三塁を離れたものと判定されて、3アウトとなった。──無得点である。
規則説明 2アウト満塁のとき、打者はフェンス越えの本塁打を打って4人とも本塁を踏んだが、打者は一塁を踏まなかったのでアピールされて3アウトになった。──この場合、打者のアウトは一塁に触れる前の第3アウトの形をとるから、無得点である。
一般的にアピールと得点の関係は以下のとおりとなる。
塁を踏み損ねた走者または飛球がとらえられたときにリタッチを果たさなかった走者に対して、守備側がアピールした場合、審判員がそれを認めたときにその走者はアウトになる。
2アウトのとき、後位の走者がアピールによって第3アウトとなった場合、前位の走者はそのアウトよりも先に正しい走塁を行なって本塁に触れていれば得点となる。
また、フォースの状態での塁の空過や打者走者の一塁空過がアピールによって第3アウトになった場合、すべての走者は正しい走塁を行なっていても得点とはならない。
規則説明 1アウト走者一・三塁のとき、打者の右翼飛球で2アウトとなった。三塁走者は捕球後三塁にリタッチして本塁を踏んだが、一塁走者は二塁へ向かっていたので一塁に帰塁しようと試みたが、右翼手の送球でアウトになった。三塁走者はそのアウトより早く本塁を踏んでいた。── 一塁走者のアウトはフォースアウトでないから、その第3アウトより早く本塁を踏んだ三塁走者の得点は記録される。
5.09 アウト
(a) 打者アウト
打者は、次の場合、アウトとなる。
(1)フェア飛球またはファウル飛球(ファウルチップを除く)が、野手に正規に捕らえられた場合。
【原注1】野手は捕球するためにダッグアウトの中に手を差し伸べることはできるが、足を踏み込むことはできない。野手がボールを確捕すれば、それは正規の捕球となる。ダッグアウトまたはボールデッドの個所(たとえばスタンド)に近づいてファウル飛球を捕らえるためには、野手はグラウンド(ダッグアウトの縁を含む)上または上方に片足または両足を置いておかなければならず、またいずれの足もダッグアウトの中またはボールデッドの個所の中に置いてはならない。正規の捕球の後、野手がダッグアウトまたはボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合、ボールデッドとなる。走者については5.06(b)(3)(c)〔原注〕参照。
捕球とは、野手が、インフライトの打球、投球または送球を、手またはグラブでしっかりと受け止め、かつそれを確実につかむ行為であって、帽子、プロテクター、あるいはユニフォームのポケットまたは他の部分で受け止めた場合は、捕球とはならない。
また、ボールに触れると同時に、あるいはその直後に、他のプレーヤーや壁と衝突したり、倒れた結果、落球した場合は〝捕球〟ではない。
野手が飛球に触れ、そのボールが攻撃側チームのメンバーまたは審判員に当たった後に、いずれの野手がこれを捕らえても〝捕球〟とはならない。
野手がボールを受け止めた後、これに続く送球動作に移ってからボールを落とした場合は〝捕球〟と判断される。
要するに、野手がボールを手にした後、ボールを確実につかみ、かつ意識してボールを手放したことが明らかであれば、これを落とした場合でも〝捕球〟と判定される。
【原注2】野手がボールを地面に触れる前に捕らえれば、正規の捕球となる。その間、ジャッグルしたり、あるいは他の野手に触れることがあってもさしつかえない。
走者は、最初の野手が飛球に触れた瞬間から、塁を離れてさしつかえない。
野手はフェンス、手すり、ロープなど、グラウンドと観客席との境界線を越えた上空へ、身体を伸ばして飛球を捕らえることは許される。また野手は、手すりの頂上やファウルグラウンドに置いてあるキャンバスの上に飛び乗って飛球を捕らえることも許される。しかし、野手が、フェンス、手すり、ロープなどを超えた上空やスタンドへ、身体を伸ばして飛球を捕らえようとすることは、危険を承知で行うプレイだから、たとえ観客にその捕球を妨げられても、観客の妨害行為に対してはなんら規則上の効力は発生しない。
ダッグアウトの縁で飛球を捕らえようとする野手が、中へ落ち込まないように、中にいるプレーヤー(いずれのチームかを問わない)によって身体を支えられながら捕球した場合、正規の捕球となる。
【注】捕手が、身につけているマスク、プロテクターなどに触れてからはね返ったフライボールを地面に取り落とさずに捕らえれば、正規の〝捕球〟となる(ファウルチップについては定義34参照)。ただし、手またはミット以外のもの、たとえばプロテクターあるいはマスクを用いて捕らえたものは、正規の捕球とはならない。
(2)第3ストライクと宣告された投球を、捕手が正規に捕球した場合。
【原注】〝正規の捕球〟ということは、まだ地面に触れていないボールが、捕手のミットの中に入っているという意味である。ボールが、捕手の着衣または用具に止まった場合は、正規の捕球ではない。また、球審に触れてはね返ったボールを捕らえた場合も同様である。
チップしたボールが、最初に捕手の身体または用具に触れて、はね返ったのを捕手が地上に落ちる前に捕球した場合、ストライクであり、第3ストライクにあたるときには、打者はアウトである。
(3)0アウトまたは1アウトで一塁に走者がいるとき、第3ストライクが宣告された場合。
【注】0アウトまたは1アウトで一塁(一・二塁、一・三塁、一・二・三塁のときも同様)に走者がいた場合には、第3ストライクと宣告された投球を捕手が後逸したり、またはその投球が球審か捕手のマスクなどに入り込んだ場合でも、本項が適用されて打者はアウトになる。
(4)2ストライク後の投球をバントしてファウルボールになった場合。
(5)インフィールドフライが宣告された場合。(2.40参照)
(6)2ストライク後、打者が打った(バントの場合も含む)が、投球がバットに触れないで、打者の身体に触れた場合。
(7)野手(投手を含む)に触れていないフェアボールが、打者走者に触れた場合。
ただし、打者がバッターボックス内にいて、打球の進路を妨害しようとする意図がなかったと審判員が判断すれば、打者に当たった打球はファウルボールとなる。
(8)打者が打つか、バントしたフェアの打球に、フェア地域内でバットが再び当たった場合。
ボールデッドとなって、走者の進塁は認められない。
これに反して、フェアの打球が転がってきて、打者が落としたバットにフェア地域内で触れた場合は、ボールインプレイである。ただし、打者が打球の進路を妨害するためにバットを置いたのではないと審判員が判断したときに限られる。
打者がバッターボックス内にいて、打球の進路を妨害しようとする意図がなかったと審判員が判断すれば、打者の所持するバットに再び当たった打球はファウルボールとなる。
【原注】バットの折れた部分がフェア地域に飛び、これに打球が当たったとき、またはバットの折れた部分が走者または野手に当たったときは、プレイはそのまま続けられ、妨害は宣告されない。打球がバットの折れた部分にファウル地域で当たったときは、ファウルボールである。
バット全体がフェア地域またはファウル地域に飛んで、プレイを企てている野手(打球を処理しようとしている野手だけでなく、送球を受けようとしている野手も含む)を妨害したときには、故意であったか否かの区別なく、妨害が宣告される。
打撃用ヘルメットに、偶然、打球がフェア地域で当たるか、または送球が当たったときは、ボールインプレイの状態が続く。
打球が、ファウル地域で打撃用ヘルメット、地面以外の異物に触れたときは、ファウルボールとなり、ボールデッドとなる。
走者がヘルメットを落としたり、ボールに投げつけて打球または送球を妨害しようとする意図があったと審判員が判断したときには、その走者はアウトとなり、ボールデッドとなって、他の走者は、打球に対してのときは投手の投球当時占有していた塁、送球に対してのときは妨害発生の瞬間に占有していた塁に帰らなければならない。
【注】本項前段を適用するにあたっては、打者がバットを所持していたかどうかを問わない。
(9)打者が、打つか、バントした後、一塁に走るにあたって、まだファウルと決まらないままファウル地域を動いている打球の進路を、どんな方法であろうとも故意に狂わせた場合。
ボールデッドとなって、走者の進塁は認められない。
(10)打者が第3ストライクの宣告を受けた後、またはフェアボールを打った後、一塁に触れる前に、その身体または一塁に触球された場合。
【注】触球するに際しては、まずボールを保持して触れることが必要なことはもちろん、触球後においても確実にボールを保持していなければならない。
また、野手がボールを手にしていても、そのボールをグラブの中でジャッグルしたり、両腕と胸とでボールを抱き止めたりしている間は、確実に捕らえたとはいえないから、たとえ打者が一塁に触れる前に野手が塁に触れながらボールを手にしていても、確捕したのが打者が一塁に触れた後であればその打者はアウトにならない。
(11)一塁に対する守備が行なわれているとき、本塁一塁間の後半を走るに際して、打者がスリーフットラインの外側(向かって右側)またはファウルラインの内側(向かって左側)を走って、一塁への送球を捕らえようとする野手の動作を妨げたと審判員が認めた場合。この際は、ボールデッドとなる。
ただし、打球を処理する野手を避けるために、スリーフットラインの外側(向かって右側)またはファウルラインの内側(向かって左側)を走ることはさしつかえない。
【原注】スリーフットレーンを示すラインはそのレーンの一部であり、打者走者は両足をスリーフットレーンの中もしくはスリーフットレーンのライン上に置かなければならない。
(12)0アウトまたは1アウトで、走者一塁、一・二塁、一・三塁または一・二・三塁のとき、内野手がフェアの飛球またはライナーを故意に落とした場合。
ボールデッドとなって、走者の進塁は認められない。
【規則説明】内野手が打球に触れないでこれを地上に落としたときには、打者はアウトにならない。ただし、インフィールドフライの規則が適用された場合は、この限りではない。
【注1】本項は、容易に捕球できるはずの飛球またはライナーを、内野手が地面に触れる前に片手または両手で現実にボールに触れて、故意に落とした場合に適用される。
【注2】投手、捕手および外野手が、内野で守備した場合は、本項の内野手と同様に扱う。また、あらかじめ外野に位置していた内野手は除く。
(13)野手が、あるプレイをなし遂げるために、送球を捕らえようとしているか、または送球しようとしているのを前位の走者が故意に妨害したと審判員が認めた場合。
【原注】この規則は攻撃側プレーヤーによる許しがたい非スポーツマン的な行為に対するペナルティとして定められたものであって、走者が塁を得ようとしないで、併殺プレイのピボットマン(併殺の際、ボールを継送するプレーヤー。すなわち遊撃手─二塁手─一塁手とわたる併殺ならば二塁手、二塁手─遊撃手─一塁手の併殺ならば遊撃手がピボットマンである)を妨害する目的で、明らかにベースラインからはずれて走るような場合に適用されるものである。
【注】まだアウトにならない前位の走者の妨害行為に対する処置は、本項では定めていないように見えるが、5.09(b)(3)に規定してあるとおり、このような妨害行為に対しては、その走者はもちろん打者もともにアウトにする規則であって、このような粗暴な行為を禁止するために規定された条項である。すでにアウトになった走者または得点したばかりの走者の妨害行為に対しては、6.01(a)(5)に規定されている。
(14)2アウト、2ストライク後本盗を企てた三塁走者が、打者への正規の投球にストライクゾーンで触れた場合。
この際、打者は〝第3ストライク〟の宣告を受けてアウトとなり、その走者の得点は認められない。しかし0アウトまたは1アウトであれば、打者は〝第3ストライク〟の宣告を受けてアウトとなり、ボールデッドになるが、その得点は認められる。
【注】0アウトまたは1アウトの場合には、他の塁の走者にも、次塁への走塁行為があったかどうかに関係なく、1個の進塁が許される。(5.06c8参照)
(15)走者を除く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理しようとしている野手の守備を妨害した場合。(6.01b参照。走者による妨害については5.09b3参照)
(b)走者アウト
5.10 プレーヤーの交代
5.11 指名打者
5.12 〝タイム〟の宣告
6.00 反則行為
6.01 妨害・オブストラクション・本塁での衝突プレイ
(a)打者または走者の妨害
次の場合は、打者または走者によるインターフェアとなる。
(1)捕手に捕球されていない第3ストライクの後、打者走者が投球を処理しようとしている捕手を明らかに妨げた場合。
打者走者はアウトになり、ボールデッドとなって、他の走者は投手の投球当時占有していた塁に戻る。
もし、捕球されずに本塁周辺にとどまっている投球が、打者または審判員によって不注意にそらされた場合、ボールデッドとなって、塁上の走者は投手の投球当時占有していた塁に戻る。この投球が第3ストライクのときは、打者はアウトになる。
【原注】投球が、捕手または審判員に触れて進路が変わり、その後に打者走者に触れた場合は、打者走者が投球を処理しようとしている捕手を明らかに妨げたと審判員が判断しない限り、妨害とはみなされない。
【注】①第3ストライクの宣告を受けただけでまだアウトになっていないか、または四球の宣告を受けて1塁へ進むべき打者走者が、三塁からの走者に対する捕手の守備動作を明らかに妨害した場合は、その打者走者をアウトとし、三塁からの走者は、投手の投球当時占有していた三塁へ帰らせる。その他の各走者も、同様に帰塁させる。
②第3ストライクの宣告を受けて5.09(a)(2)または同(3)でアウトになった打者が、三塁走者に対する捕手の守備動作を明らかに妨害したときは、6.01(a)(5)によって三塁から走ってきた走者もアウトにする。
③②の場合で、重盗を防ごうとする捕手の守備動作を明らかに妨害したときは、その対象となった走者をアウトとして、他の走者は妨害発生の瞬間にすでに占有していた塁へ帰らせる。もしも、捕手の守備動作がどの走者に 対してなされたかが明らかでない場合には、本塁に近い走者をアウトにする。(6.01a5〔注〕参照)
(2)打者または走者が、まだファウルと決まらないままファウル地域を動いている打球の進路を、どんな方法であろうとも故意に狂わせた場合。(5.09a9参照)
(3)0アウトまたは1アウトで、走者三塁のとき、打者が本塁における野手のプレイを妨げた場合。
この場合、走者がアウトになるが、2アウト後の場合は打者がアウトになる。(5.09b8、6.03a3・4参照)
【注】本項は、5.09(b)(8)と異なる文字を用いているにすぎないから、ただ離塁しているにすぎない三塁走者をアウトにしようとする捕手のプレイを打者が妨げた場合などには、適用されない。
(4)1人または2人以上の攻撃側メンバーが、走者が達しようとする塁に接近して立つか、あるいは、その塁の付近に集合して守備側を妨げるか、惑乱させるか、ことさらに守備を困難にした場合、その走者は味方のメンバーが相手の守備を妨害(インターフェア)したものとしてアウトを宣告される。
(5)アウトになったばかりの打者または走者、あるいは得点したばかりの走者が、味方の走者に対する野手の次の行動を阻止するか、あるいは妨げた場合は、その走者は、味方のプレーヤーが相手の守備を妨害(インターフェア)したものとして、アウトを宣告される。(5.09a13参照)
【原注】打者または走者が、アウトになった後、進塁を続けたり、帰塁したり、正規の占有していた塁に戻ろうと試みたりしても、その行為だけでは、野手を惑乱したり、邪魔したり、または遮ったものとはみなされない。
【注】本項を適用するにあたって、2人または3人の走者がいる場合、妨げられた守備動作が直接1人の走者に対して行なわれようとしていたことが判明しているときは、その走者をアウトにし、どの走者に対して守備が行なわれようとしていたか判定しにくいときは、本塁に最も近い走者をアウトにする。
前項によって、1人の走者に対してアウトを宣告したときは、ボールデッドとなり、他の走者は守備妨害の行なわれた瞬間すでに占有していた塁に帰らせる。
ただし、打球を直接処理した野手が打者走者に対して守備を行なわず、他の走者に対して行なおうとした守備が妨害された場合には、その走者をアウトにし、その他の走者は、投手の投球当時占有していた塁へ戻らせる。しかし打者走者だけは、再びバッタースボックスに帰せないから、1塁の占有を許す。
なお、打者が走者となって一塁へ進んだために、走者に一塁を明け渡す義務が生じたときは、その走者を2塁へ進ませる。たとえば、0アウト満塁のとき、打者が遊ゴロして、三塁からの走者がフォースアウトにされ、その際、その走者が、捕手がさらに三塁にボールを送ってダブルプレイを企てようとするのを、突きとばして妨害したような場合、その走者と三塁に向かった走者とはアウトになるが、打者に一塁が与えられるので、一塁の走者は二塁に進むことが許されるような場合がそれである。
(6)走者が明らかに併殺を行なわせまいとして故意に打球を妨げるか、または打球を処理している野手を妨害したと審判員が判断したとき、審判員はその妨害をした走者にアウトを宣告するとともに、味方のプレーヤーが相手の守備を妨害したものとして打者走者に対してもアウトを宣告する。この場合、ボールデッドとなって他の走者は進塁することも得点することもできない。
(7)打者走者が、明らかに併殺を行なわせまいとして故意に打球を妨げるか、または打球を処理している野手を妨害したと審判員が判断したとき、審判員は打者走者に妨害によるアウトを宣告するとともに、どこかで併殺が行なわれようとしていたかには関係なく、本塁に最も近い走者に対してもアウトを宣告する。この場合、ボールデッドとなって他の走者は進塁することはできない。
(8)三塁または一塁のベースコーチが、走者に触れるか、または支えるかして、走者の三塁または一塁への帰塁、あるいはそれらの離塁を、肉体的に援助したと審判員が認めた場合。
(9)走者三塁のとき、ベースコーチが自己のボックスを離れて、なんらかの動作で野手の送球を誘致した場合。
(10)走者が打球を処理しようとしている野手を避けなかったか、あるいは送球を故意に妨げた場合。
ただし、2人以上の野手が接近して、打球を処理しようとしており、走者がそのうち1人か2人以上の野手に接触したときには、審判員はそれらの野手のうちから、本項の適用を受けるのに最もふさわしい位置にあった野手を1人決定して、その野手に触れた場合に限ってアウトを宣告する。(5.09b3参照)
走者がファウルボールに対する守備を妨害したとして、アウトを宣告され、これが第3アウトにあたる場合、打者走者は打撃を完了したものとみなされ、次のイニングの第1打者は次打者となる。(0アウトまたは1アウトのときは、打者はそのまま打撃を続ける。)
【原注】捕手が打球を処理しようとしているときに、捕手と一塁へ向かう打者走者とが接触した場合は、守備妨害も走塁妨害もなかったとみなされて、何も宣告されない。打球を処理しようとしている野手による走塁妨害は、非常に悪質で乱暴な場合にだけ宣告するべきである。たとえば打球を処理しようとしているからといって、走者を故意につまずかせるようなことをすれば、オブストラクションが宣告される。
捕手が打球を処理しようとしているのに、《他の野手(投手を含む。)》が、一塁へ向かう打者走者を妨害したらオブストラクションが宣告されるべきで、打者走者には一塁が与えられる。
(11)野手(投手を含む)に触れていないフェアボールが、フェア地域で走者に触れた場合。
ただし、走者がフェアボールに触れても、
(A) いったん内野手(投手を含む)に触れたフェアボールに触れた場合
(B)1人の内野手(投手を除く)に触れないでその股間または側方を通過したフェアボールに、すぐその後方で触れても、この打球に対して、他のいずれの内野手も守備する機会がない場合
には、審判員は走者が打球に触れたという理由でアウトを宣告してはならない。
しかし、内野手が守備する機会を失った打球(内野手に触れたかどうかを問わない)でも、走者が故意にその打球を蹴ったと審判員が認めれば、その走者は、妨害(インターフェア)をしたという理由でアウトの宣告を受けなければならない。(5.06c6、5.09b7参照)
インターフェアに対するペナルティ 走者はアウトになりボールデッドとなる。
審判員が、打者、打者走者または走者に妨害によるアウトを宣告した場合には、他のすべての走者は、妨害発生の瞬間にすでに占有していたと審判員が判断する塁まで戻らなければならない。ただし、本規則で別に規定した場合を除く。
打者走者が一塁に到達しないうちに妨害が発生したときは、すべての走者は投手の投球当時占有していた塁に戻らなければならない。
ただし、0アウトまたは1アウトのとき、本塁でのプレイで走者が得点した後、打者走者がスリーフットレーンの外を走って守備妨害でアウトが宣告されても、その走者はそのままセーフが認められて、得点は記録される。
【注】前記の〝打者走者が一塁に到達しないうち〟以下の段は、プレイが介在した後に妨害が発生した場合には適用しない。
【原注1】打球(フェアボールとファウルボールとの区別なく)を処理しようとしている野手の妨げになったと審判員によって認められた走者は、それが故意であったか故意でなかったかの区別なくアウトになる。
しかし、正規に占有を許された塁についていた走者が、フェア地域とファウル地域との区別なく守備の妨げになった場合、審判員がその妨害を故意と判断したときを除いて、その走者はアウトにはならない。審判員が、その妨害を故意と宣告した場合には次のペナルティを科す。
0アウトまたは1アウトのときは、その走者と打者とにアウトを、2アウト後のときは、打者にアウトを宣告する。
【問】1アウト走者三塁のとき、三塁に触れている走者が、三塁横に上がったファウルフライを捕らえようとする三塁手の守備の妨げになったので、三塁手は捕球できなかった。いかに処置すべきか。
【答】その走者が故意に守備を妨げたと審判員が認めれば、その走者と打者にアウトを宣告する。
【原注2】三塁本塁間で狭撃された走者が妨害によってアウトを宣告された場合には、後位の走者はその妨害行為発生以前に、たとえ三塁を占めることがあってもその占有は許されず、二塁に帰らなければならない。また二塁三塁間で挟撃された走者が妨害によってアウトになった場合も同様、後位の走者は一塁に帰らなければならない。妨害が発生した場合には、いずれの走者も進塁できないこと、および走者は正規に次塁に進塁するまでは元の塁を占有しているものとみなされることがその理由である。
【注】走者一・三塁のとき三塁走者が三塁本塁間で挟撃され、妨害によってアウトを宣告された場合、一塁走者がその妨害行為発生以前に二塁を占めておれば、一塁走者には二塁の占有が許される。
(b) 守備側の権利優先
攻撃側チームのプレーヤー、ベースコーチまたはその他のメンバーは、打球あるいは送球を処理しようとしている野手の守備を妨げないように、必要に応じて自己の占めている場所(ダッグアウト内またはブルペンを含む)を譲らなければならない。
走者を除く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理しようとしている野手の守備を妨害した場合は、ボールデッドとなって、打者はアウトになり、すべての走者は投球当時に占有していた塁に戻る。
走者を除く攻撃側チームのメンバーが、送球を処理しようとしている野手の守備を妨害した場合は、ボールデッドとなって、そのプレイの対象であった走者はアウトとなり、他のすべての走者は妨害発生の瞬間に占有していた塁に戻る。
【原注】守備側の妨害とは、投球を打とうとする打者を妨げたり、邪魔をする野手の行為をいう。
【注】たとえば、プレーヤーが2本のバットを持って次打者席に入っていたとき、打者がファウル飛球を打ち、これを捕手が追ってきたので、そのプレーヤーは1本のバットを持って場所を譲ったが、捕手は取り残されたバットにつまずいたために、容易に捕らえることができたはずのファウル飛球を捕らえることができなかったような場合、プレーヤーの取り残したバットが、明らかに捕手の捕球を妨げたと審判員が判断すれば、打者はアウトになる。
(c) 捕手の妨害
捕手またはその他の野手が、打者を妨害(インターフェア)した場合、打者は走者となり、アウトにされるおそれなく、安全に一塁が与えられる。(ただし、打者が一塁に進んで、これに触れることを条件とする)
しかし、妨害にもかかわらずプレイが続けられたときには、攻撃側チームの監督は、そのプレイが終わってからただちに、妨害行為に対するペナルティの代わりに、そのプレイを生かす旨を球審に通告することができる。
ただし、妨害にもかかわらず、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に達し、しかも他の全走者が少なくとも1個の塁を進んだときは、妨害とは関係なく、プレイは続けられる。
【原注】捕手の妨害が宣告されてもプレイが続けられたときは、そのプレイが終わってからこれを生かしたいと監督が申し出るかもしれないから、球審はそのプレイを継続させる。
打者走者が一塁を空過したり、走者が次塁を空過しても、〔5.06b3付記〕に規定されているように、塁に到達したものとみなされる。
監督がプレイを選ぶ場合の例。
①1アウト走者三塁、打者が捕手に妨げられながらも外野に飛球を打ち、捕球後三塁走者が得点した。監督は、打者アウトで得点を記録するのと、走者三塁、一塁(打者が打撃妨害により出塁)とのいずれを選んでもよい。
②0アウト走者二塁、打者は捕手に妨げられながらもバントして走者を三塁に進め、自らは一塁でアウトになった。監督は0アウト走者二塁、一塁とするよりも走者三塁で1アウトとなる方を選んでもよい。
三塁走者が盗塁またはスクイズプレイにより得点しようとした場合のペナルティは、6.01(g)に規定されている。
投手が投球する前に、捕手が打者を妨害した場合、打者に対する妨害とは考えられるべきではない。このような場合には、審判員は〝タイム〟を宣告して〝出発点〟からやり直させる。
【注1】監督がプレイを生かす旨を球審に通告するにあたっては、プレイが終わったら、ただちに行なわなければならない。なお、いったん通告したら、これを取り消すことはできない。
【注2】監督がペナルティの適用を望んだ場合、次のとおり解釈できる。
捕手(または他の野手)が打者を妨害した場合、打者には一塁が与えられる。三塁走者が盗塁またはスクイズによって得点しようとしたときに、この妨害があった場合にはボールデッドとし、三塁走者の得点を認め、打者には一塁が与えられる。
三塁走者が盗塁またはスクイズプレイで得点しようとしていなかったときに、捕手が打者を妨害した場合にはボールデッドとし、打者に一塁が与えられ、そのために塁を明け渡すことになった走者は進塁する。盗塁を企てていなかった走者と塁を明け渡さなくてもよい走者とは、妨害発生の瞬間に占有していた塁にとめおかれる。
(d) 競技場内に入ることを公認された人の妨害
競技場内に入ることを公認された人(試合に参加している攻撃側メンバーまたはベースコーチ、そのいずれかが打球または送球を守備しようとしている野手を妨害した場合、あるいは審判員を除く。)が競技を妨害したとき、その妨害が故意でないときは、ボールインプレイである。
しかし故意の妨害のときには、妨害と同時にボールデッドとなり、審判員は、もし妨害がなかったら競技はどのような状態になったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。(4.07a参照)
【原注】本項で除かれている攻撃側メンバーまたはベースコーチが、打球または送球を守備しようとしている野手を妨害した場合については、6.01(b)参照。審判員による妨害については5.06(c)(2)、同(6)および5.05(b)(4)、走者による妨害については5.09(b)(3)参照。
妨害が故意であったか否かは、その行為に基づいて決定しなければならない。
たとえば、バットボーイ、ボールボーイ、警察官などが、打球または送球に触れないように避けようとしたが避けきれずに触れた場合は、故意の妨害とはみなされない。しかしボールを拾い上げたり、捕ったり、意図的に触れたりすることや、押し戻したり、蹴ったりすれば、この行為は故意の妨害とみなされる。
例──打者が遊撃手にゴロを打ち、それを捕った遊撃手が一塁に悪送球した。一塁ベースコーチは送球に当たるのを避けようとしてグラウンドに倒れ、悪送球を捕りに行こうとした一塁手と衝突した。打者走者は三塁まで到達した。妨害を宣告するかどうかは審判員の判断による。コーチが妨害を避けようとしたが避けきれなかったと判断すれば、妨害を宣告してはならない。
(e) 観衆の妨害
打球または送球に対して観衆の妨害があったときは、妨害と同時にボールデッドとなり、審判員は、もし妨害がなかったら競技はどのような状態になったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。
【規則説明】観衆が飛球を捕らえようとする野手を明らかに妨害した場合には、審判員は打者に対してアウトを宣告する。
【原注】打球または送球がスタンドに入って観衆に触れたら、たとえ競技場内にはね返ってきてもボールデッドとなる場合と、観衆が競技場内に入ったり、境界線から乗り出すか、その下またはあいだをくぐり抜けてインプレイのボールに触れるか、あるいはプレーヤーに触れたり、その他の方法で妨げた場合とは事情が異なる。後者の場合は故意の妨害として取り扱われる。打者と走者は、その妨害がなかったら競技はどのような状態になったかと審判員が判断した場所におかれる。
野手がフェンス、手すり、ロープから乗り出したり、スタンドの中へ手を差し伸べて捕球するのを妨げられても妨害とは認められない。野手は危険を承知でプレイしている。しかし、観衆が競技場に入ったり、身体を競技場の方へ乗り出して野手の捕球を明らかに妨害した場合は、打者は観衆の妨害によってアウトが宣告される。
例──1アウト走者三塁、打者が外野深く飛球(フェアかファウルかを問わない)を打った。観衆がそれを捕球しようとする外野手を明らかに妨害した。審判員は観衆の妨害によるアウトを宣告した。その宣告と同時にボールデッドとなり、審判員は打球が深かったので、妨害されずに野手が捕球しても捕球後三塁走者は得点できたと判断して、三塁走者の得点を認める。本塁からの距離が近いほんの浅いフライに対しては、妨害があっても、このような処置をとるべきではない。
(f) コーチ及び審判員の妨害
送球が偶然ベースコーチに触れたり、投球または送球が審判員に触れたときも、ボールインプレイである。しかし、ベースコーチが故意に送球を妨害した場合には、走者はアウトとなる。
【原注】審判員の妨害は、(1)盗塁を阻止しようとしたり、塁上の走者をアウトにしようとする捕手の送球動作を、球審が邪魔したり、はばんだり、妨げた場合、(2)打球が、野手(投手を除く)を通過する前に、フェア地域で審判員に触れた場合に起こる。
捕手の送球動作には、投手の返球も含む。
(g) スクイズプレイまたは本塁の妨害
3塁走者が、スクイズプレイまたは盗塁によって得点しようと試みた場合、捕手またはその他の野手がボールを持たないで、本塁の上またはその前方に出るか、あるいは打者または打者のバットに触れたときには、投手にボークを課して、打者はインターフェアによって一塁が与えられる。この際はボールデッドとなる。
【注1】捕手がボールを持たないで本塁の上またはその前方に出るか、あるいは打者または打者のバットに触れた場合は、すべて捕手のインターフェアとなる。
特に、捕手がボールを持たないで本塁の上またはその前方に出た場合には、打者がバッタースボックス内にいたかどうか、あるいは打とうとしたかどうかには関係なく、捕手のインターフェアとなる。また、その他の野手の妨害というのは、たとえば、一塁手などが著しく前進して、投手の投球を本塁通過前にカットしてスクイズプレイを妨げる行為などを指す。
【注2】すべての走者は、盗塁行為の有無に関係なく、ボークによって1個の塁が与えられる。
【注3】本項は、投手の投球が正規、不正規にかかわらず適用される。
【注4】投手が投手板を正規に外して走者を刺そうと送球したときには、捕手が本塁上またはその前方に出ることは、正規なプレイであって、打者がこの送球を打てば、かえって打者は守備妨害として処置される。
(h) オブストラクション
オブストラクションが生じたときには、審判員は〝オブストラクション〟を宣告するか、またはそのシグナルをしなければならない。
(1)走塁を妨げられた走者に対しプレイが行われている場合、または打者走者が一塁に触れる前にその走塁を妨げられた場合には、ボールデッドとし、塁上の各走者はオブストラクションがなければ達しただろうと審判員が推定する塁まで、アウトのおそれなく進塁することが許される。
走塁を妨げられた走者は、オブストラクション発生当時すでに占有していた塁よりも少なくとも1個先の進塁が許される。
走塁を妨げられた走者が進塁を許されたために、塁を明け渡さなければならなくなった前位の走者(走塁を妨げられた走者より)は、アウトにされるおそれなく次塁へ進むことが許される。
【付記】捕手はボールを持たないで、得点しようとしている走者の進路をふさぐ権利はない。塁線(ベースライン)は走者の走路であるから、捕手は、まさに送球を捕ろうとしているか、送球が直接捕手に向かってきており、しかも十分近くにきていて、捕手がこれを受け止めるにふさわしい位置を占めなければならなくなったときか、すでにボールを持っているときだけしか、塁線上に位置することができない。
【原注】走塁を妨げられた走者に対してプレイが行なわれている場合には、審判員は〝タイム〟を宣告するときと同じ方法で、両手を頭上にあげてオブストラクションのシグナルをしなければならない。オブストラクションのシグナルが行なわれたときは、ただちにボールデッドとなる。しかし、審判員のオブストラクションの宣告がなされる前に、野手の手を離れていたボールが悪送球となったときには、オブストラクションが発生しなければ、その悪送球によって当然許されるはずの塁がその走者に与えられるべきである。走者が二塁三塁間で挟撃され、すでに遊撃手からの送球がインフライトの状態のときに、三塁へ進もうとした走者が三塁手に走塁を妨げられたとき、その送球がダッグアウトに入った場合、その走者には本塁が与えられる。この際、他の走者に関しては、オブストラクションが宣告される以前に占有していた塁を基準として2個の塁が与えられる。
【注1】内野手におけるランダウンプレイ中に走者が走塁を妨げられたと審判員が判断した場合はもちろん、野手が、走者(一塁に触れた後の打者走者を含む)をアウトにしようとして、その走者が進塁を企てている塁へ直接送球していたときに、その走者が走塁を妨げられたと審判員が判断した場合も同様、本項が適用される。
【注2】たとえば、走者二・三塁のとき、三塁走者が投手に追い出されて三塁本塁間で挟撃され、この間を利して二塁走者は三塁に達していたところ、挟撃されていた走者が三塁へ帰ってきたので二塁走者は元の塁へ戻ろうとし、二塁三塁間で挟撃された。しかし、このランダウンプレイ中に二塁走者はボールを持たない二塁手と衝突したような場合、審判員が二塁手の走塁妨害を認めれば〝オブストラクション〟を宣告し、ボールデッドとして、二塁走者を三塁へ、三塁走者を本塁へ進める処置をとる。
【注3】たとえば、走者一塁、打者が左翼線に安打したとき、左翼手は一塁走者の三塁への進塁をはばもうとして三塁へ送球したが、一塁走者は二塁を越えたところでボールを持たない遊撃手と衝突したような場合、審判員が遊撃手の走塁妨害を認めれば、オブストラクションを宣告して、ボールデッドにし、一塁走者に三塁の占有を許す。打者については、審判員がオブストラクション発生時の状況を判断して、二塁へ達したであろうとみれば二塁の占有を許すが、二塁へ進めなかったとみれば一塁に留める。
【注4】たとえば、走者一塁、打者が一ゴロしたとき、ゴロをとった一塁手は一塁走者をフォースアウトにしようと二塁へ送球したが、一塁へ向かっている打者と一塁へ入ろうとした投手とが一塁の手前で衝突したような場合、審判員が投手の走塁妨害を認めれば、オブストラクションを宣告して、ボールデッドにする。この際、審判員がオブストラクションよりも二塁でのフォースアウトが後に成立したと判断したときには、打者走者を一塁に、一塁走者を二塁に進める。これに反して、オブストラクションより二塁でのフォースアウトが先に成立していたと判断したときには、打者走者の一塁占有を認めるだけで、一塁走者の二塁でのフォースアウトは取り消さない。
(2)走塁を妨げられた走者に対してプレイが行なわれていなかった場合には、すべてのプレイが終了するまで試合は続けられる。審判員はプレイが終了したのを見届けた後に、初めて〝タイム〟を宣告し、必要とあれば、その判断で走塁妨害によってうけた走者の不利益を取り除くように適宜な処置をとる。
【原注】本項規定のようにオブストラクションによってボールデッドとならない場合、走塁を妨げられた走者が、オブストラクションによって与えようと審判員が判断した塁よりも余分に進んだ場合は、オブストラクションによる安全進塁権はなくなり、アウトを賭して進塁したこととなり、触球されればアウトになる。このアウトは、審判員の判断に基づく裁定である。
【注1】たとえば、走者二塁のとき打者が左前安打した。左翼手は本塁をうかがった二塁走者をアウトにしようと本塁へ送球した。打者走者は一塁を越えたところで一塁手にぶつかったので、審判員は〝オブストラクション〟のシグナルをした。左翼手の本塁への送球は捕手の頭上を越す悪送球となったので、二塁走者はやすやすと得点することができた。オブストラクションを受けた打者走者はボールが転じているの見て二塁を越え、三塁をうかがったところ、ボールを拾った投手からの送球を受け三塁手に三塁到達前に触球されたような場合、審判員が、打者走者にはオブストラクションによって二塁しか与えることができないと判断したときには、三塁でのアウトは認められる。
これに反して、打者走者が三塁手の触球をかいくぐって三塁に生きたような場合、その三塁の占有は認められる。いずれの場合も、二塁走者の得点は認められる。
【注2】たとえば、打者が三塁打と思われるような長打を放ち、一塁を空過した後、二塁を経て三塁に進もうとしたとき、遊撃手に妨げられて、三塁へ進むことができなかったような場合、審判員は、この反則の走塁を考慮することなく、妨害がなければ達したと思われる三塁へ進めるべきである。もし野手が打者の一空過を知ってアピールすれば、その打者はアウトになる。走塁の失敗はオブストラクションとはなんら関係がないからである。
(i) 本塁での衝突プレイ
(1)得点しようとしている走者は、最初から捕手に接触しようとして、または避けられたにもかかわらず最初から接触をもくろんで走路から外れることはできない。もし得点しようとした走者が最初から捕手または野手に接触しようとしたと審判員が判断すれば、捕手がボールを保持していたかどうかに関係なく、審判員はその走者にアウトを宣告する。その場合、ボールデッドとなって、すべての他の走者は接触が起きたときに占有していた塁(最後に触れていた塁)に戻らなければならない。走者が正しく本塁に滑り込んでいた場合には、本項に違反したとはみなされない。
【原注】走者が触塁の努力を怠って、肩を下げたり、手、肘または腕を使って押したりする行為は、本項に違反して最初から捕手と接触するために、または避けられたにもかかわらず最初から接触をもくろんで走路を外れたとみなされる。走者が塁に滑り込んだ場合、足からのスライディングであれば、走者の尻および脚が捕手または野手と接触する前に地面に落ちたとき、またヘッドスライディングであれば、捕手または野手が接触する前に走者の身体が先に地面に落ちたときは、正しいスライディングとみなされる。捕手または野手が走者の走路をブロックした場合は、本項に違反して走者が避けられたにもかかわらず接触をもくろんだということを考える必要はない。
(2)捕手がボールを持たずに得点しようとしている走者の走路をブロックすることはできない。もし捕手がボールを持たずに走者の走路をブロックしたと審判員が判断した場合、審判員はその走者にセーフを宣告する。前記にかかわらず、捕手が送球を実際に守備しようとして走者の走路をふさぐ結果になった場合(たとえば、送球の方向、軌道、バウンドに反応して動いたような場合)には、本項に違反したとはみなされない。また、走者がスライディングすることで捕手との接触を避けられたならば、ボールを持たない捕手が本項に違反したとはみなされない。
本塁でのフォースプレイには、本項を適用しない。
【原注】捕手が、ボールを持たずに本塁をブロックするか(または実際に送球を守備しようとしていないとき)、および得点しようとしている走者の走塁を邪魔するか、阻害した場合を除いて、捕手は本項に違反したとはみなされない。審判員が、捕手が本塁をブロックしたかどうかに関係なく、走者はアウトを宣告されていただろうと判断すれば、捕手が走者の走塁を邪魔または阻害したとはみなされない。また、捕手は、滑り込んでくる走者に触球するときには不必要かつ激しい接触を避けるために最大限の努力をしなければならない。滑り込んでくる走者と日常的に不必要なかつ激しい接触(たとえば膝、レガース、肘または前腕を使って接触をもくろむ)をする捕手はリーグ会長の制裁の対象となる。
【6.01i原注】本項の〝捕手〟については、本塁のカバーに来た投手を含む野手にも適用される。
【注】我が国では、本項の(1)(2)ともに、所属する団体の規定に従う。
(j)併殺を試みる塁へのスライディング
走者が併殺を成立させないために、〝正しいスライディング〟をせずに、野手に接触したり、接触しようとすれば、本条によりインターフェアとなる。
本条における〝正しいスライディング〟とは、次のとおりである。走者が、
(1) ベースに到達する前からスライディングを始め(先に地面に触れる)、
(2) 手や足でベースに到達しようとし、
(3) スライディング終了時は(本塁を除き)ベース上にとどまろうとし、
(4) 野手に接触しようとして走路を変更することなく、ベースに達するように滑り込む。
〝正しいスライディング〟をした走者は、そのスライディングで野手に接触したとしても、本条によりインターフェアとはならない。また、走者の正規の走路に野手が入ってきたために、走者が野手に接触したとしてもインターフェアにはならない。
前記にかかわらず、走者がロールブロックをしたり、意図的に野手の膝や送球する腕、上半身より高く足を上げて野手に接触したり、接触しようとすれば、〝正しいスライディング〟とはならない。
走者が本項に違反したと審判員が判断した場合、走者と打者走者にアウトを宣告する。その走者がすでにアウトになっている場合については、守備側がプレイを試みようとしている走者にアウトが宣告される。
【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。
6.02 投手の反則行為
(a)ボーク
塁に走者がいるときは、次の場合ボークとなる。
(1)投手板に触れている投手が、5.07(a)(1)および(2)項に定める投球動作に違反した場合。
【原注】左投げ、右投げ、いずれの投手でも自由な足を振って投手板の後縁を越えたら、打者へ投球しなければならない。ただし、二塁走者のピックオフプレイのために二塁へ送球することは許される。
(2)投手板に触れている投手が、一塁または三塁に送球するまねだけして、実際に送球しなかった場合。
【注】投手が投手板に触れているとき、走者のいる二塁へは、その塁の方向に直接ステップすれば偽投してもよいが、一塁または三塁と打者への偽投は許されない。投手が軸足を投手板の後方へ外せば、走者のいるどの塁へもステップしないで偽投してもよいが、打者にだけは許されない。
(3)投手板に触れている投手が、塁に送球する前に、足を直接その塁の方向に踏み出さなかった場合。
【原注】投手板に触れている投手は、塁に送球する前には直接その塁の方向に自由な足を踏み出すことが要求されている。投手が実際に踏み出さないで、自由な足の向きを変えたり、ちょっと上にあげて回したり、または踏み出す前に身体の向きを変えて送球した場合、ボークである。投手は、塁に送球する前に塁の方向へ直接踏み出さなければならず、踏み出したら送球しなければならない。(二塁については例外)
ランナー一・三塁のとき、投手が走者を三塁に戻すために三塁へ踏み出したが実際に送球しなかったら(軸足は投手板に触れたまま)、ボークとなる。
(4)投手板に触れている投手が、走者のいない塁へ送球したり、送球するまねをした場合。
ただし、プレイの必要があればさしつかえない。
【原注】投手が走者のいない塁へ送球したり、送球するまねをした場合、審判員は、それが必要なプレイかどうかを、走者がその塁に進もうとしたか、あるいはその意図が見られたかで判断する。
【問】走者一塁のとき、走者のいない二塁に送球したり、または送球するまねをしたらボークか。
【答】ボークである。しかし一塁走者が二塁に盗塁しようとしたのを防ぐ目的で、第1動作で二塁の方向に正しく自由な足を踏み出せば、ボークにならない。なお投手が投手板を正規に外せば、ステップをしないで送球してもかまわない。
(5)投手が反則投球をした場合。
【原注】クイックピッチは反則投球である。打者が打者席内でまだ十分な構えをしていないときに投球された場合には、審判員は、その投球をクイックピッチと判定する。塁に走者がいればボークとなり、いなければボールである。クイックピッチは危険なので許してはならない。
(6)投手が打者に正対しないうちに投球した場合。
(7)投手が投手板に触れないで、投球に関連する動作をした場合。
【問】走者一塁のとき、投手が投手板をまたいだままストレッチを始めたがボールを落とした。ボークとなるか。
【答】投手が投手板に触れないで、投球に関連する動作を起こしているからボークとなる。
(8)投手が不必要に試合を遅延させた場合。
【原注】本項は、6.02(c)(8)により警告を発せられたときは、適用されない。投手が遅延行為を繰り返して6.02(c)(8)により試合から除かれた場合には、あわせて本項のボークも課せられる。5.07(c)は、塁に走者がいないときだけ適用される。
(9)投手がボールを持たないで、投手板に立つか、これをまたいで立つか、あるいは投手板を離れていて投球するまねをした場合。
(10)投手が正規の投球姿勢をとった後、実際に投球するか、塁に送球する場合を除いて、ボールから一方の手を離した場合。
(11)投手板に触れている投手が、故意であろうと偶然であろうと、ボールを落とした場合。
(12)故意四球が企図されたときに、投手がキャッチャースボックスの外にいる捕手に投球した場合。
【注】〝キャッチャースボックスの外にいる捕手〟とは、捕手がキャッチャースボックス内に両足を入れていないことをいう。したがって故意四球が企図されたときに限って、ボールが投手の手を離れないうちに捕手が片足でもボックスの外に出しておれば、本項が適用される。
(13)投手がセットポジションから投球するに際して、完全に静止しないで投球した場合。
ペナルティ (a)項各規定によってボークが宣告されたときは、ボールデッドとなり、各走者は、アウトにされるおそれなく、1個の塁が与えられる。
ただし、ボークにもかかわらず、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に達し、かつ、他のずべての走者が少なくとも1個の塁を進んだときには、このペナルティの前段を適用しないで、プレイはボークと関係なく続けられる。
【規則説明1】投手がボークをして、しかも塁または本塁に悪送球(投球を含む)した場合、塁上の走者はボークによって与えられる塁よりもさらに余分の塁へアウトを賭して進塁してもよい。
【規則説明2】(a)項ペナルティを適用するに際して、走者が進塁しようとする最初の塁を空過し、アピールによってアウトを宣告されても、1個の塁を進んだものと解する。
【注】前掲〔規則説明1〕の〝悪送球〟には、投手の悪送球だけではなく、投手からの送球を止め損じた野手のミスプレイも含まれる。走者が、投手の悪送球または野手のミスプレイによって余塁が奪えそうな状態となり、ボークによって与えられる塁を越えて余分に進もうとしたときには、ボークと関係なくプレイは続けられる。
【6.02a原注】ボークルールの目的は、投手が走者を意図的に騙そうとするのを防ぐためであることを、審判員は心に銘記しなくてはならない。もし、審判員の判断で投手の〝意図〟に疑いを抱いたら、審判員は厳重に規則を適用すべきである。
(b)反則投球
塁に走者がいないときに、投手が反則投球をした場合には、その投球には、ボールが宣告される。ただし、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に達した場合は除く。
【原注】投球動作中に、投手の手からとび出したボールがファウルラインを超えたときだけボールと宣告されるが、その他の場合は、投球とみなされない。塁に走者がいれば、ボールが投手の手から落ちたときただちにボークとなる。
【注】球審は、反則投球に対してボールを宣告したならば、それが反則投球によるものであることを投手に指摘する。
なお、6.02(c)(6)に違反した場合には、6.02(d)を適用する。
(c)投手の禁止事項
投手は次のことを禁じられる。
(1)投手が投手板を囲む18㌳の円い場所の中で、投球する手を口または唇につけた後にボールに触れるか、投手板に触れているときに投球する手を口または唇につけること。
投手は、ボールまたは投手板に触れる前に、投球する手の指をきれいに拭かなければならない。
【例外】天候が寒い日の試合開始前に、両チーム監督の同意があれば、審判員は、投手が手に息を吹きかけることを認めることができる。
ペナルティ 投手が本項に違反した場合には、球審はただちにボールを交換させ、投手に警告を発する。投手がさらに違反した場合には、ボールを宣告する。その宣告にもかかわらず、投手が投球して、打者が安打、失策、死球、その他で一塁に達し、かつ走者が次塁に達するか、または元の塁にとどまっていた(次塁に達するまでにアウトにならなかった)ときには、本項の違反とは関係なくプレイは続けられる。なお、違反を繰り返した投手は、リーグ会長から罰金が科せられる。
(2)ボール、投球する手またはグラブに唾液をつけること。
(3)ボールをグラブ、身体、着衣で摩擦すること。
(4)ボールに異物をつけること。
(5)どんな方法であっても、ボールに傷をつけること。
(6)(2)~(5)項で規定されている方法で傷つけたボール、いわゆるシャインボール、スピットボール、マッドボール、あるいはエメリーボールを投球すること。
ただし、投手は素手でボールを摩擦することは許される。
【注】シャインボール──ボールを摩擦してすべすべにしたもの。
スピットボール──ボールに唾液を塗ったもの。
マッドボール──ボールに泥をなすりつけたもの。
エメリーボール──ボールをサンドペーパーでザラザラにしたもの。
なお、ボールに息を吹きかけることも禁じられれている。
(7)投手がいかなる異物でも、身体につけたり、所持すること。
【原注】投手は、いずれの手、指または手首に何もつけてはならない(たとえば救急ばんそうこう、テープ、瞬間接着剤、ブレスレットなど)。審判員が異物と判断するかしないか、いずれの場合も、手、指または手首に何かをつけて投球することを許してはならない。
【注】我が国では、本項〔原注〕については、所属する団体の規定に従う。
(8)打者がバッタースボックスにいるときに、捕手以外の野手に送球して、故意に試合を遅延させること。ただし、走者をアウトにしようと企てる場合は除く。
ペナルティ 審判員は1度警告を発し、しかもなお、このような遅延行為が繰り返されたときには、その投手を試合から除く。
【注1】投手が捕手のサインを投手板から離れて受けるので、しばしば試合を遅延させている。これは悪い習慣であるから、監督及びコーチはこれを是正するように努めなければならない。
【注2】アマチュア野球では、本項ペナルティの後段を適用せず、このような遅延行為が繰り返されたときは、ボールを宣告する。
(9)打者を狙って投球すること。このような反則行為が起きたと審判員が判断したときは、審判員は次のうちのいずれかを選ぶことができる。
(A)その投手またはその投手とそのチームの監督とを試合から除く。
(B)その投手と両チームの監督に、再びこのような投球が行われたら、その投手(またはその投手の後に出場した投手)と監督を退場させる旨の警告を発する。
審判員は、反則行為が起きそうな状況であると判断したときには、試合開始前、あるいは試合中を問わず、いつでも両チームに警告を発することができる。
リーグ会長は、8.04に規定された権限によって、制裁を加えることができる。
【原注】チームのメンバーは、本項によって発せられた警告に対し抗議したり、不満を述べたりするためにグラウンドに出てくることはできない。もし監督、コーチまたはプレーヤーが抗議のためにダッグアウトまたは自分の場所を離れれば、警告発せられる。警告にもかかわらず本塁に近づけば、試合から除かれる。
打者を狙って投球することは、非スポーツマン的である。特に頭を狙って投球することは、非常に危険であり、この行為は許されるべきではない。審判員はちゅうちょなく、本項を厳格に適用しなければならない。
(d)ペナルティ 投手が(c)項(2)~(7)に違反した場合、球審は次のような処置をしなければならない。
投手は次のことを禁じられる。
(1)投手はただちに試合から除かれ、自動的に出場停止となる。マイナーリーグでは、自動的に10試合の出場停止となる。
(2)球審が違反をしたにもかかわらずプレイが続けられたときには、攻撃側の監督は、そのプレイが終わってからただちにそのプレイを生かす旨、球審に通告することができる。ただし、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に達し、しかも他の全走者が次塁に達するか、元の塁にとどまっていた(次塁に達するまでにアウトにならなかった)ときには、反則とは関係なくプレイは続けられる。
(3)(2)項の場合でも、投手の反則行為は消滅せず、(1)項のペナルティは適用される。
(4)攻撃側の監督がそのプレイを生かすことを選択しなかった場合は、球審は走者がいなければボールを宣告し、走者がいればボークとなる。
(5)投手が各項に違反したかどうかについては、審判員が唯一の決定者である。
【6.02d原注1】投手が(c)項(2)または(3)に違反しても、その投球を変化させる意図はなかったと球審が判断した場合は、本項のペナルティを適用せずに警告を発することができる。しかし、投手が違反を繰り返せば、球審はその投手にペナルティを科さなければならない。
【6.02d原注2】ロジンバッグにボールが触れたときは、どんなときでも、ボールインプレイである。
雨天の場合または競技場が湿っている場合には、審判員は投手にロジンバッグを腰のポケットに入れるよう指示する。(1個のロジンバッグを交互に使用させる)
投手はこのロジンバッグを用いて、素手にロジンをつけることを許されるが、投手、野手を問わず、プレーヤーは、ロジンバッグで、ボールまたはグラブにロジンをふりかけたり、またはユニフォームのどの部分にも、これをふりかけることは許されない。
6.03 打者の反則行為
(a)打者の反則行為によるアウト
次の場合、打者は反則行為でアウトになる。
(1)打者が片足または両足を完全にバッタースボックスの外に置いて打った場合。
【原注】本項は、打者が打者席の外に出てバットにボールを当てた(フェアかファウルかを問わない)とき、アウトを宣告されることを述べている。球審は、故意四球が企てられているとき、投球を打とうとするバッターの足の位置に特に注意を払わなければならない。打者は打者席から跳び出したり、踏み出して投球を打つことは許されない。
(2)投手が投球姿勢にはいったとき、打者が一方のバッタースボックスから他方のバッタースボックスに移った場合。
【注】投手が投手板に触れて捕手からのサインを見ているとき、打者が一方から他方のバッタースボックスに移った場合、本項を適用して打者をアウトとする。
(3)打者がバッタースボックスの外に出るか、あるいはなんらかの動作によって、本塁での捕手のプレイおよび捕手の守備または送球を妨害した場合。
しかし例外として、進塁しようとしていた走者がアウトになった場合、および得点しようとした走者が打者の妨害によってアウトの宣告を受けた場合は、打者はアウトにはならない。
【原注】打者が捕手を妨害したとき、球審は妨害を宣告しなければならない。打者はアウトになり、ボールデッドとなる。妨害があったとき、走者は進塁できず、妨害発生の瞬間に占有していたと審判員が判断した塁に帰らなければならない。しかし、妨害されながらも捕手がプレイをして、アウトにしようとした走者がアウトになった場合には、現実には妨害がなかったものと考えられるべきで、その走者がアウトとなり、打者はアウトにはならない。その際、他の走者は、走者がアウトにされたら妨害はなかったものとするという規則によって、進塁も可能である。このような場合、規則違反が宣告されなかったようにプレイは続けられる。
打者が空振りし、スイングの余勢で、その所持するバットが、捕手または投球に当たり、審判員が故意ではないと判断した場合は、打者の妨害とはしないが、ボールデッドとして走者の進塁を許さない。打者については、第1ストライク、第2ストライクにあたるときは、ただストライクを宣告し、第3ストライクにあたるときに打者をアウトにする。(2ストライク後の〝ファウルチップ〟も含む)
【注1】打者が空振りしなかったとき、投手の投球を捕手がそらし、そのボールがバッタースボックス内にいる打者の所持するバットに触れた際はボールインプレイである。
【注2】本項は、捕手以外の野手の本塁でのプレイを打者が妨害した場合も含む。
打者に妨害行為があっても、走者を現実にアウトにすることができたときには、打者をそのままとして、その走者のアウトを認め、妨害と関係なくプレイは続けられる。しかしアウトの機会はあっても、野手の失策で走者を生かした場合には、現実にアウトが成立していないから、本項の前段を適用して打者をアウトにする。
なお、捕手からの送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はただちに〝タイム〟を宣告して打者を妨害によるアウトにし、走者を元の塁に戻す。
(4)走者がいるとき、または投球が第3ストライクのとき、打者がフェア地域またはファウル地域にバットを投げて、投球を受けようとしていた捕手(またはミット)に当たった場合。
【6.03a3・4例外】進塁しようとしていた走者がアウトになった場合、および得点しようとした走者が打者の妨害によってアウトの宣告を受けた場合には、打者はアウトにはならない。
(5)打者が、いかなる方法であろうとも、ボールの飛距離を伸ばしたり、異常な反発力を生じさせるように改造、加工したと審判員が判断するバットを使用したり、使用しようとした場合。
このようなバットには、詰めものをしたり、表面を平らにしたり、釘を打ちつけたり、中をうつろにしたり、溝をつけたり、パラフィン、ワックスなどでおおって、ボールの飛距離を伸ばしたり、異常な反発力を生じさせるようにしたものが含まれる。
打者がこのようなバットを使用したために起きた進塁は認められない《(バットの使用に起因しない進塁、たとえば盗塁、ボーク、暴投、捕逸を除く)》が、アウトは認められる。
打者はアウトを宣告され、試合から除かれ、後日リーグ会長によってペナルティが科せされる。
【原注】打者ががこのようなバットを持ってバッタースボックスに入れば、打者は規則違反のバットを使用した、あるいは使用しようとしたとみなされる。
【注】アマチュア野球では、このようなバットを使用した場合、打者にはアウトを宣告するにとどめる。
(b)打順の誤り
(1)打順表に記載されている打者が、その番のときに打たないで、番でない打者(不正位打者)が打撃を完了した(走者となるか、アウトとなった)後、相手方がこの誤りを発見してアピールすれば、正位打者はアウトを宣告される。
(2)不正位打者の打撃完了前ならば、正位打者は、不正位打者の得たストライクおよびボールのカウントを受け継いで、これに代わって打撃につくことはさしつかえない。
(3)不正位打者が打撃を完了したときに、守備側チームが〝投手の投球〟前に球審にアピールすれば、球審は、
(A)正位打者にアウトを宣告する。
(B)不正位打者の打球によるものか、または不正位打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に進んだことに起因した、すべての進塁および得点を無効とする。
【注1】(3)(5)(7)項でいう、〝投手の投球〟とは、投手が次に面した打者(いずれのチームの打者かを問わない)へ1球を投じた場合はもちろん、たとえ投球しなくてもその前にプレイをしたりプレイを企てた場合も含まれる。
ただし、アピールのための送球などは、ここでいう〝プレイ〟に含まれない。
【注2】不正位打者の打球によるものか、不正位打者が一塁に進んだことに起因した、すべての進塁および得点を無効とするとあるが、進塁だけに限らず、不正位打者の打撃行為によるすべてのプレイを無効とする。すなわち、不正位打者の二ゴロで一塁走者が二塁でフォースアウトにされた後、アピールによって正位打者がアウトの宣告を受ければ、一塁走者のフォースアウトは取り消される。
(4)走者が、不正位打者の打撃中に盗塁、ボーク、暴投、捕逸などで進塁することは、正規の進塁とみなされる。
(5)不正位打者が打撃を完了した後、〝投手の投球〟前にアピールがなかった場合には、不正位打者は正位打者として認められ、試合はそのまま続けられる。
(6)正位打者が、打撃順の誤りを発見されてアウトの宣告を受けた場合には、その正位打者の次の打順の打者が正規の次打者となる。
(7)不正位打者が〝投手の投球〟前にアピールがなかったために、正位打者と認められた場合には、この正位化された不正位打者の次に位する打者が正規の次打者となる。不正位打者の打撃行為が正当化されれば、ただちに、打順はその正位化された不正位打者の次の打者に回ってくる。
【6.03b原注】審判員は、不正位打者がバッタースボックスに立っても、何人にも注意を喚起してはならない。各チームの監督、プレーヤーの不断の注意があって、初めて本項の適用が可能となる。
【規則説明】 打順を次のように仮定して、打順の誤りによって生じる種々の状態を例証する。
打順……1 2 3 4 5 6 7 8 9
打者……A B C D E F G H Ⅰ
【例題1】Aの打順にBがバッタースボックスに入って、投球カウントが2-1となったとき、
(a)攻撃側が打順の誤りに気がついた。
(b)守備側はアピールした。
【解答】どちらの場合も、Aはカウント2-1を受け継いでBと代わる。この際アウトはない。
【例題2】Aの打順にBが打ち、二塁打を放った。この場合、
(a)守備側はただちにアピールした。
(b)守備側はCに1球が投じられた後、アピールした。
【解答】(a)正位打者Aはアウトの宣告を受け、Bが正規の次打者となる。
(b)Bはそのまま二塁にとどまり、Cが正規の次打者となる。
【例題3】A、Bともに四球、Cはゴロを打ってBをフォースアウトとして、Aを三塁へ進めた後、Dの打順にEがバッタースボックスに入った。その打撃中に暴投があって、Aは得点し、Cは二塁へ進んだ。Eがゴロを打ってアウトとなり、Cを三塁に進めた。この場合、
(a)守備側はただちにアピールした。
(b)守備側は、次にバッタースボックスに入ったDへの1球が投じられた後、アピールした。
【解答】(a)正位打者Dがアウトの宣告を受け、Eの打撃行為のために三塁に進んだCは二塁に戻されるが、暴投によるAの得点およびCの二塁への進塁は、Eの打撃行為とは関係なく行なわれた進塁だから有効となる。Eは次打者となって再び打たなければならない。
(b)Aの得点は認められ、Cは三塁にとどまる。正位化したEの次のFが正規の次打者となる。
【例題4】2アウト満塁で、Fの打順にHが出て三塁打し、全走者を得点させた。この場合、
(a)守備側はただちにアピールした。
(b)守備側はGに1球が投じられた後、アピールした。
【解答】(a)正位のFはアウトの宣告を受け、得点は全部認められない。Gが次回の第1打者となる。
(b)Hは三塁にとどまり、3点が記録される。Ⅰが正規の次打者となる。
【例題5】2アウト満塁で、Fの打順にHが出て三塁打し、全走者を得点させ3点を記録し、続いてバッタースボックスに入ったGへの1球が投じられた後、
(a)Hは三塁で投手の送球によりアウトになり、攻守交代となった。
(b)Gが飛球を打ってアウトとなり攻守交代したが、アピールがなく、相手チームが攻撃に移った。
この二つの場合では誰が次回の第1打者となるか。
【解答】(a)Ⅰである。Gへの1球が投じられたのでHの三塁打は正当化され、Ⅰが正規の次打者となる。
(b)Hである。相手チームの第1打者への1球が投じられるまでにアピールがなかったので、Gの打撃行為は正当化されるから、Hが正規の次打者となる。
【例題6】Aの打順にDが出て四球を得た後、Aがバッタースボックスについて、1球が投じられた。その際、Aへの投球前にアピールがあれば、正位打者のAがアウトの宣告を受けて、Dの四球は取り消され、Bが正規の次打者となるが、すでにAに1球が投じられたために、Dの四球は正当化され、Eが正規の次打者となる。ところが、不正位のAはそのまま打撃を続けてフライアウトとなり、Bがバッタースボックスについてしまった。この際も、Bに1球が投じられるまでにアピールがあれば、正位打者のEがアウトの宣告を受けて、Fが正規の次打者となるはずだが、またしてもアピールがなく、Bに1球が投じられたので、こんどはAの打撃行為が正当化されて、Bが正規の次打者となった。そのBが四球を得てDを二塁へ進め、次打者のCは飛球を打ってアウトとなった。Dが正規の次打者であるはずだが、二塁走者となっている。この際、だれが正規の次打者となるか。
【解答】Dは打順を誤っているが、すでに正当化され、しかも塁上にいるから、Dを抜かして、Eを正規の次打者とする。
6.04 競技中のプレーヤーの禁止事項
(a)監督、プレーヤー、控えのプレーヤー、コーチ、トレーナーおよびバットボーイは、どんなときでも、ベンチ、コーチスボックス、その他競技場のどの場所からも、次のことをしてはならない。
(1)言葉、サインを用いて、観衆を騒ぎたたせるようにあおったり、あおろうとすること。
(2)どんな方法であろうとも、相手チームのプレーヤー、審判員または観衆に対して、悪口をいったりまたは暴言を吐くこと。
(3)ボールインプレイのときに〝タイム〟と叫ぶか、他の言葉または動作で明らかに投手にボークを行なわせようと企てること。
(4)どんな形であろうとも、審判員に故意に接触すること。(審判員の身体に触れることはもちろん、審判員に話しかけたり、なれなれしい態度をとること)
(b)ユニフォームを着用者は、次のことが禁じられる。
(1)プレーヤーが、試合前、試合中、または試合終了後を問わず、観衆に話しかけたり、席を同じくしたり、スタンドに座ること。
(2)監督、コーチまたはプレーヤーが、試合前、試合中を問わず、いかなるときでも観衆に話しかけたり、または相手チームのプレーヤーと親睦的態度をとること。
【注】アマチュア野球では、次の試合に出場するプレーヤーがスタンドで観戦することを特に許す場合もある。
(c)野手は、打者の目のつくところに位置して、スポーツ精神に反する意図で故意に打者を惑わしてはならない。
ペナルティ 審判員は反則者を試合から除き、競技場から退かせる。なお投手がボークをしても無効とする。
(d)監督、プレーヤー、コーチまたはトレーナーは、試合から除かれた場合、ただちに競技場を去り、以後その試合にたずさわってはならない。
試合から除かれた者はクラブハウス内にとどまっているか、ユニフォームを脱いで野球場構内から去るか、あるいはスタンドに座る場合には、自チームのベンチまたはブルペンから離れたところに席をとらなければならない。
【原注】出場停止処分中の監督、コーチ、プレーヤーは、ユニフォームを着てクラブの試合前の練習に参加することはかまわないが、試合中は、ユニフォームを着ることはできず、プレーヤーが試合にたずさわる場所から離れていなければならない。また、出場停止中の者は試合中、新聞記者席や放送室の中に入ることはできないが、スタンドから試合を見ることは許される。
(e)ベンチにいる者が、審判員の判定に対して激しい不満の態度を示した場合は、審判員は、まず警告を発し、この警告にもかかわらず、このような行為が継続された場合には、次のペナルティを適用する。
ペナルティ 審判員は、反則者にベンチを退いてクラブハウスに行くことを命じる。もし、審判員が反則者を指摘することができなければ、控えのプレーヤーを全部ベンチから去らせる。しかし、この場合そのチームの監督には、試合に出場しているプレーヤーと代えるために必要な者だけを競技場に呼び戻す特典が与えられる。
7.00 試合の終了
7.01 正式試合
(a)正式試合は、通常9イニングから成るが、次の例外がある。
すなわち同点のために試合が延長された場合、あるいは試合が次の理由によって短縮された場合──
(1)ホームチームが9回裏の攻撃の全部、または一部を必要としない場合。
(2)球審もしくはリーグ事務局がコールドゲームを宣告した場合。
【例外】マイナーリーグは、ダブルヘッダーのうちの1試合またはその2試合を7回に短縮する規定を採用することが許される。
この際、本規則で9回とあるのを7回と置きかえるほかは、すべて本規則に従うべきである。
(b)延長回
(1)両チームが9回の攻撃を完了してなお得点が等しいときは、さらに回数を重ねていき、
(A)延長回の表裏を終わって、ビジティングチームの得点がホームチームの得点より多い場合
(B)ホームチームが延長回の裏の攻撃中に決勝点を記録した場合
に試合は終了する。
(2)9回が完了した後、10回以降は、走者二塁から、次のとおり始めることとする。
(A)10回以降の延長回の先頭打者(またはその打者の代打者)は、前の回からの継続打順とする。
(B)延長回における二塁走者は、その回の先頭打者の前の打順のプレーヤー(またはそのプレーヤーの代走者)とする。
たとえば、10回の先頭打者が5番打者であれば、4番打者(またはその代走者)が二塁走者となる。ただし、先頭打者の前の打順のプレーヤーが投手であれば、その投手の前の打順のプレーヤーが代わりに二塁走者を務めることができる。
交代して退いた打者および走者は、規則5.10により、再び試合に出場することはできない。
(C)投手の自責点を規則9.16により決定するために、延長回を開始するときの二塁走者は守備の失策により二塁に到達したようにみなされるが、チームおよびプレーヤーに失策は記録されない。公式記録員は、延長回における打者および二塁走者についても、規則9.02により記録をする。
(D)延長回が始まるたびに、球審は二塁走者が適正であるかを確かめるため、攻撃側チームの打順表を確認する。もし、その走者が適正でなければ、球審はただちに攻撃側チームの監督に知らせて、適正な二塁走者にさせる必要がある。また、プレイが開始された後に、審判員またはいずれかの監督が、走者が適正でないことに気付けば、その走者は適正な走者と入れ替わらなければならず、打順の誤りに起因したことにより、プレイを無効としない限りは、すべてのプレイは正規なものとなる。得点する前後に関係なく、適正でない走者に対するペナルティはない。
【注】 我が国では、所属する団体の規定に従う。
(c)球審もしくはリーグ事務局は、天候、フィールドまたは球場のコンディション、設備(開閉式屋根、防水シートなど)の故障または意図しない操作ミス、大気の質、外出禁止令、電気または照明の喪失、地域や国家の緊急事態、災害や政府の規制、暗闇、ファンおよ
び選手を含むチーム関係者と球場職員の健康と安全、または試合の安全な実施と継続を妨げる異常事態のために、試合を延期または中止することができる。
【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。
(d)コールドゲームが次に該当する場合、正式試合となる。
(1)5回の表裏を完了した後に、打ち切りを命じられた試合。(両チームの得点の数には関係がない)
(2)5回表を終わった際、または5回裏の途中で打ち切りを命じられた試合で、ホームチームの得点がビジティングチームの得点より多いとき。
(3)5回裏の攻撃中にホームチームが得点して、ビジティングチームの得点と等しくなっているときに打ち切りを命じられた試合。
コールドゲームとなった正式試合の得点はゲームが宣告された時点での得点となる。
上記にかかわらず、両チームの得点が等しいままコールドゲームが宣告された場合、またはイニングの途中で、そのイニングが終了する前にコールドゲームが宣告された場合であって、ビジティングチームが同点またはリードするために1点またはそれ以上の得点をして、ホームチームがリードを奪い返していない場合、通常であれば正式試合となるコールドゲームは、以下の7.02に適用されるサスペンデッドゲームとして扱われる。
リーグ事務局はまた、試合を打ち切らなければならない状況が非常に特殊または異常であれば、公正を期すためにその試合をサスペンデッドゲームとして扱うか、別の方法で扱う必要があるかを判断することができる。
【注1】我が国では、正式試合となる前に、球審もしくはリーグ事務局が試合の打ち切りを命じた場合には、〝ノーゲーム〟を宣告することができる。(2025年改正:追記)
【注2】我が国では、所属する団体の規定に従う。
(e)正式試合においては、試合終了時の両チームの総得点をもって、その試合の勝敗を決する。
(1)ビジティングチームが9回表の攻撃を終わったとき、ホームチームの得点が相手より多いときには、ホームチームの勝ちとなる。
(2)両チームが9回の攻守が終わったとき、ビジティングチームの得点が相手より多いときにはビジティングチームの勝ちとなる。
(3)ホームチームの9回裏または延長回の裏の攻撃中に、勝ち越し点にあたる走者が得点すれば、そのときに試合は終了して、ホームチームの勝ちとなる。
【例外】試合の最終回の裏、打者がプレイングフィールドの外へ本塁打を打った場合、打者および塁上の各走者は、正規に各塁に触れれば得点として認められ、打者が本塁に触れたときに試合は終了し、打者および走者のあげた得点を加えて、ホームチームの勝ちとなる。
【規則説明】9回裏または延長回の裏に、プレイングフィールドの外へ本塁打を打った打者が、前位の走者に先んじたためアウトになった場合は、塁上の全走者が得点するまで待たないで、勝ち越し点にあたる走者が得点したときに試合は終了する。ただし、2アウトの場合で、走者が前位の走者に先んじたときに勝ち越し点にあたる走者が本塁に達していなければ、試合は終了せず、追い越すまでの得点だけが認められる。
【注】9回裏または延長回の裏、0アウトまたは1アウトで、打者がプレイングフィールドの外へ本塁打を打ったときに、ある走者が前位の走者に先んじたためにアウトになった場合は、打者に本塁打が認められ、試合は打者が本塁に触れたときに終了する。
(4)コールドゲームが宣告された正式試合の得点は、試合終了時の両チームの総得点をもって、その試合の勝敗を決する。
【注】 我が国では、正式試合となった後のある回の途中で球審もしくはリーグ事務局がコールドゲームを宣告したとき、次に該当する場合は、両チームが完了した最終均等回の総得点でその試合の勝敗を決することとする。
①ビジティングチームがその回の表で得点してホームチームの得点と等しくなったが、表の攻撃が終わらないうち、または裏の攻撃が始まらないうち、あるいは裏の攻撃が始まってもホームチームが得点しないうちにコールドゲームが宣告された場合。
②ビジティングチームがその回の表でリードを奪う得点を記録したが、表の攻撃が終わらないうち、または裏の攻撃が始まらないうち、あるいは裏の攻撃が始まってもホームチームが同点またはリードを奪い返す得点を記録しないうちにコールドゲームが宣告された場合。
7.02 サスペンデッドゲーム(一時停止試合)
(a)ポストポンドゲーム(開始前に中止、延期された試合)やサスペンデッドゲーム(以下の状況で打ち切られた試合)は、開始または再開して完了できるよう、直ちに予定されなければならない。
(1)正式試合となる前。
(2)両チームの得点が等しい。
(3)イニングの途中で、そのイニングが終了する前に、ビジティングチームが1点またはそれ以上の得点をして、同点またはリードを奪ったが、ホームチームがリードを奪い返していない。
(b)ポストポンドゲームおよびサスペンデッドゲームは、両クラブ間で予定されているシーズン中(すなわち、両クラブ間で次に予定されている試合の前)に、できれば同じ球場で、両クラブの試合のない日に開始または再開して完了できるよう、直ちに予定されなければならない。
(c)ポストポンドゲームおよびサスペンデッドゲームが、シーズン中に完了する予定が立たない場合、またはシーズン中に実施可能な選択肢が片方もしくは両方のチームに過度の負担を及ぼす場合、リーグ事務局は、関連するすべての要素を考慮して、シーズンの完了後を含めて、試合を行なうか決定する。
(d)サスペンデッドゲームが、シーズン中に再開されなかった場合、その試合がコールドゲームを宣告された時点ですでに正式試合となる回数が行なわれていたときは、次のようになる。
(1)コールドゲームが宣告された時点でリードしているチームの勝ちとなる。
(2)コールドゲームが宣告された時点で得点が同点であった場合、その試合はタイゲームとなる。
ただし、(1)および(2)にかかわらず、イニングの途中で、そのイニングが終了する前にコールドゲームが宣告され、ビジティングチームが1点もしくはそれ以上の得点でリードを奪うかまたは同点に追いつき、ホームチームがリードを奪い返すか再び同点に追いつくことができなかった場合、両チームが完了した最終均等回の総得点で勝敗を決する。
(e) ポストポンドゲームがシーズン中に再び予定されなかった場合、またはサスペンデッドゲームがシーズン中に再開されなかった場合であって、その試合がコールドゲームを宣告された時点で正式試合となる回数が行なわれていなかったとき、その試合は〝ノーゲーム〟となり、いかなる目的においても試合としてカウントされない。
(f)継続試合は、元の試合の停止された個所から再開しなければならない。すなわち、停止試合を完了させるということは、一時停止された試合を継続して行なうことを意味するものであるから、両チームの出場者と打撃順は、停止されたときと同一にしなければならないが、規則によって認められる交代は、もちろん可能である。したがって、停止試合に出場しなかったプレーヤーならば、継続試合に代わって出場することができるが、停止試合にいったん出場して他のプレーヤーと代わって退いたプレーヤーは、継続試合には出場することはできない。停止された試合のメンバーとして登録されていなかったプレーヤーでも、継続試合のメンバーとして登録されれば、その試合には出場できる。さらに、継続試合の出場資格を失ったプレーヤー(停止状態に出場し、他のプレーヤーと代わって退いたため)の登録が抹消されて、その代わりとして登録された者でも、継続試合には出場できる。
【原注】交代して出場すると発表された投手が、そのときの打者(代打者を除く)がアウトになるか一塁に達するか、あるいは攻守交代となるまで投球しないうちに、サスペンデッドゲームとなった場合、その投手は継続試合の先発投手として出場してもよいし、出場しなくてもよい。しかし、継続試合に出場しなかった場合には、他のプレーヤーと交代したものとみなされて、以後その試合に出場することはできない。
【7.02注】我が国では、所属する団体の規定に従う。
7.03 フォーフィッテッドゲーム(没収試合)
(a)一方のチームが次のことを行なった場合には、フォーフィッテッドゲームとして相手チームに勝ちが与えられる。
(1)球審が試合開始時刻にプレイを宣告してから、5分を経過してもなお競技場に出ないか、あるいは競技場に出ても試合を行なうことを拒否した場合。
ただし、遅延が不可避であると球審が認めた場合は、この限りではない。
(2)試合を長引かせ、または短くするために、明らかに策を用いた場合。
(3)球審が一時停止または試合の打ち切りを宣告しないにもかかわらず、試合の続行を拒否した場合。
(4)一時停止された試合を再開するために、球審がプレイを宣告してから、1分以内に競技を再開しなかった場合。
(5)審判員が警告を発したにもかかわらず、故意に、また執拗に反則行為を繰り返した場合。
(6)審判員の命令で試合から除かれたプレーヤーを、適宜な時間内に、退場させなかった場合。
(7)ダブルヘッダーの第2試合の際、第1試合終了後30分以内に、競技場に現われなかった場合。
ただし、第1試合の球審が第2試合開始までの時間を延長した場合は、この限りではない。
(b)一方のチームが競技場に9人のプレーヤーを位置させることができなくなるか、またはこれを拒否した場合、その試合はフォーフィッテッドゲームとなって相手チームの勝ちとなる。
(c)球審が、試合を一時停止した後、その再開に必要な準備を球場管理人に命じたにもかかわらず、その命令が《意図的に》履行されなかったために、試合再開にに支障をきたした場合は、その試合はフォーフィッテッドゲームとなり、ビジティングチームの勝ちとなる。
【注】アマチュア野球では、本項を適用しない。
(d)球審がフォーフィッテッドゲームを宣告したときは、宣告後24時間以内に、その旨を書面でリーグ会長に報告しなければならない。
ただし、球審がこの報告をしなかったからといって、フォーフィッテッドゲームであることに変わりはない。
7.04 提訴
審判員の判断に基づく裁定についての異議であろうが、審判員の裁定が本規則に違反して決定したことに対する異議かにかかわらず、どのような提訴も許されない。
補則 ボールデッドの際の走者の帰塁に関する処置(再録)
ボールデッドとなって各走者が帰塁する場合、ボールデッドとなった原因によって、帰るべき塁の基準がおのおの異なるので、その基準をここに一括する。
(Ⅰ)投手の投球当時に占有していた塁に帰らせる場合。
(a)ファウルボールが捕球されなかった場合。(5.06c5)
(b)打者が反則打球した場合。(5.06c4、6.03a1)
(c)投球が正規に位置している打者の身体または着衣に触れた場合。(5.06c1、5.09a6)
(d)0アウトまたは1アウトで、走者一塁、一・二塁、一・三塁または一・二・三塁のとき、内野手がフェアの飛球またはライナーを故意に落とした場合。(5.09a12)
(e)打球を守備しようとする野手を妨げた場合。
(1)フェアボールが、内野手(投手を含む)に触れる前に打者走者に触れた場合。(5.09a7)
(2)フェアボールが、内野手(投手を含む)に触れる前に、フェア地域で走者または審判員に触れた場合。またはフェアボールが、内野手(投手を除く)を通過する前に、フェア地域で審判員に触れた場合。(5.05b4、5.06c6、5.09b7、6.01a11)
(3)打者が打つかバントしたフェアの打球に、フェア地域内でバットが再び当たった場合。(5.09a8)
(4)打者または走者が、打球を処理しようとしている野手の守備を妨げた場合。(5.09b3、6.01a6・7・10)
(5)打者または走者が、まだファウルと決まらないままファウル地域を動いている打球の進路を、どんな方法であろうとも、故意に狂わせた場合。(5.09a9、6.01a2)
(6)攻撃側プレーヤーまたはコーチが、必要に応じて自己の占めている場所を譲らないで、打球を処理しようとしている野手を妨げて、守備妨害を宣告された場合。(5.09a15、6.01b)
(f)打者走者が、本塁から一塁へ走る際に、一塁への送球を受けようとしている野手の動作を妨げた場合。(5.09a11、定義44)──特に規定した場合を除く。
(g)第3ストライクの宣告を受けただけでまだアウトになっていない打者走者、または四球の宣告を受けた打者走者が、捕手の守備を明らかに妨げた場合。(6.01a1)
(Ⅱ)妨害発生の瞬間すでに占有していた塁に帰らせる場合。
(a)投手の打者への投球に始まった守備を妨げた場合。
(1)球審が捕手の送球動作を妨げた場合。(5.06c2)
(2)打者が捕手の送球動作を妨げた場合。(6.03a3)
(3)0アウトまたは1アウトで、走者が得点しようとしたとき、打者が本塁における守備側のプレイを妨げた場合。(5.09b8、6.01a3)
(4)打者が空振りした後、スイングの余勢で、その所持するバットが捕手または投球に当たり、審判員が故意ではないと判断した場合。(6.03a3原注)
(b)捕手またはその他の野手が、打者の打撃を妨害した場合。(5.05b3、6.01c)
(c)走者が故意に送球を妨げた場合。(5.09b3)
(d)攻撃側チームのプレーヤーまたはベースコーチが、必要に応じて自己の占めている場所を譲らないで、送球を処理しようとしている野手を妨げたために、守備妨害でアウトを宣告された場合。(5.09a15、6.01b)
(e)内野手が守備する機会を失った打球(内野手に触れたかどうかを問わない)を走者が故意にけったと審判員が認めた場合。(6.01a11B)──ボールをけったときを基準とする。
(f)アウトを宣告されたばかりの打者または走者、あるいは得点したばかりの走者が、野手の次の行為を妨げた場合。(6.01a5)──次の行為に移ろうとしたときを基準とする。
(g)1人または2人以上の攻撃側メンバーが、走者が達しようとする塁に接近して立つか、あるいはその塁の付近に集合して守備を妨害するか、惑乱させるか、ことさらに守備を困難にした場合。(6.01a4)──その守備が起ころうとしたときを基準とする。
(Ⅲ)走者三塁のとき、ベースコーチが自己のボックスを離れてなんらかの動作で野手の送球を誘発した場合、またはベースコーチが意識的に送球を妨げた場合(6.01a9、6.01f)には、その送球がなされたときにすでに占有していた塁に帰らせる。
8.00 審判員
8.01 審判員の資格と権限
(a)リーグ会長は、1名以上の審判員を指名して、各リーグの選手権試合を主宰させる。
審判員は、本公認野球規則に基づいて、試合を主宰するとともに、試合中、競技場における規律と秩序とを維持する責にも任ずる。
(b)各審判員は、リーグ及びプロフェッショナルベースボールの代表者であり、本規則を厳格に適用する権限を持つとともに、その責にも任ずる。審判員は、プレーヤー、コーチ、監督のみならず、クラブ役職員、従業員でも、本規則の施行上、必要があるときには、その所定の任務を行なわせ、支障のあるときはには、その行動を差し控えさせることを命ずる権限と、規則違反があれば、規定のペナルティを科す権限とを持つ。
(c)審判員は、本規則に明確に規定されている事項に関しては、自己の裁量に基づいて、裁定を下す権能が与えられている。
(d)審判員は、プレーヤー、コーチ、監督または控えのプレーヤーが裁定に異議を唱えたり、スポーツマンらしくない言動をとった場合には、その出場資格を奪って、試合から除く権限を持つ。審判員がボールインプレイのときプレーヤーの出場資格を奪った場合には、そのプレイが終了して、初めてその効力が発生する。
(e)審判員は、その判断において、必要とあれば、次の人々を競技場から退場させる権限を持つ。すなわち、
(1)グラウンド整備員、案内人、写真班、新聞記者、放送局員などのように、仕事の性質上、競技場に入ることを許されている人々。
(2)競技場に入ることを許されていない観衆またはその他の人々。
8.02 審判員の裁定
(a)打球がフェアかファウルか、投球がストライクかボールか、あるいは走者がアウトかセーフかという裁定に限らず、審判員の判断に基づく裁定は最終のものであるから、プレーヤー、監督、コーチまたは控えのプレーヤーが、その裁定に対して、異議を唱えることは許されない。
【原注】ボール、ストライクの判定について異議を唱えるためにプレーヤーが守備位置または塁を離れたり、監督またはコーチがベンチまたはコーチスボックスを離れることは許されない。もし、宣告に異議を唱えるために本塁に向かってスタートすれば、警告が発せられる。警告にもかかわらず本塁に近づけば、試合から除かれる。
(b)審判員の裁定が規則の適用を誤って下された疑いがあるときには、監督だけがその裁定を規則に基づく正しい裁定に訂正するように要請することができる。しかし、監督はこのような裁定を下した審判員に対してだけアピールする(規則適用の訂正の申し出る)ことが許される。
【注】審判員が、規則に反した裁定を下したにもかかわらず、アピールもなく、定められた期間が過ぎてしまったあとでは、たとえ審判員が、その誤りに気づいても、その裁定を訂正することはできない。
(c)審判員が、その裁定に対してアピールを受けた場合は、最終の裁定を下すにあたって、他の審判員の意見を求めることはできる。裁定を下した審判員から相談を受けた場合を除いて、審判員は、他の審判員の裁定に対して、批評を加えたり、変更を求めたり、異議を唱えたりすることは許されない。
審判員が協議して先に下した裁定を変更する場合、審判員は、走者をどこまで進めるかを含め、すべての処置をする権限を有する。この審判員の裁定に、プレーヤー、監督またはコーチは異議を唱えることはできない。異議を唱えれば、試
合から除かれる。
投球カウントの誤りの訂正は、投手が次の打者へ1球を投じるまで、または、イニングや試合の最終打者の場合には守備側チームのすべての内野手がフェア地域を離れるまでに行わなければならない。
【原注1】監督は、審判員にプレイおよび裁定を変更した理由について説明を求めることはできる。しかし、いったん審判員の説明を受ければ、審判員に異議を唱えることは許されない。
【原注2】ハーフスイングの際、球審がストライクと宣告しなかったときだけ、監督または捕手は、振ったか否かについて、塁審のアドバイスを受けるよう球審に要請することができる。球審は、このような要請があれば、塁審にその裁定を一任しなければならない。
塁審は、球審からのリクエストがあれば、ただちに裁定を下す。このようにして下された塁審の裁定は最終のものである。
監督または捕手からの要請は、投手が打者へ次の1球を投じるまで、または、たとえ投球しなくてもその前にプレイをしたりプレイを企てるまでに行なわなければならない。イニングの表または裏が終わったときの要請は、守備側チームのすべての内野手がフェア地域を去るまでに行なわなければならない。
ハーフスイングについて、監督または捕手が前記の要請を行なってもボールインプレイであり、塁審がストライクの裁定に変更する場合があるから、打者、走者、野手を問わず、状況の変化に対応できるよう常に注意していなければならない。
監督が、ハーフスイングに異議を唱えるためにダッグアウトから出て一塁または三塁に向かってスタートすれば警告が発せられる。警告にもかかわらず一塁または三塁に近づけば試合から除かれる。監督はハーフスイングに関して異議を唱えるためにダッグアウトを離れたつもりでも、ボール、ストライクの宣告について異議を唱えるためにダッグアウトを離れたことになるからである。
(d)試合中、審判員の変更は認められない。ただし、病気または負傷のため、変更の必要が生じた場合はこの限りではない。
1人の審判員だけで試合を担当する場合には、その義務と権限は、競技場のあらゆる点、本規則のあらゆる条項に及び、その任務の遂行上、競技場内の最適と思われる場所に位置をとらなければならない。(通常は捕手の後方に、走者がいる場合は、ときとして投手の後方に位置をとる)
(e)2人以上の審判員が試合を担当する場合は、1人はアンパイヤーインチーフ(球審)に、他はフィールドアンパイヤ―(塁審)に指定されなければならない。
8.03 球審および塁審の任務
(a)アンパイヤーインチーフ(通常球審と呼ばれている)は、捕手の後方に位置し、その任務は次のとおりである。
(1)試合の適正な運行に関するすべての権限と義務とを持つ。
(2)捕手の後方に位置し、ボールとストライクを宣告し、かつそれをカウントする。
(3)通常塁審によって宣告される場合を除いて、フェアボールとファウルボールを宣告する。
(4)打者に関するすべての裁定を下す。
(5)通常塁審が行うものとされているものを除いたすべての裁定を下す。
(6)フォーフィッテッドゲームの裁定を下す。
(7)特定の時刻に競技を打ち切ることが決められている場合には、試合開始前にその事実と終了時刻を公表する。
(8)公式記録員に打撃順を知らせる。また出場プレーヤーに変更があれば、その変更を知らせる。
(9)球審の判断で特別グラウンドルールを発表する。
(b)フィールドアンパイヤーは、塁におけるとっさの裁定を下すのに最適と思われる位置を占め、その任務は次のとおりである。
(1)特に球審が行なう場合を除く塁におけるすべての裁定を下す。
(2)タイム、ボーク、反則投球またはプレーヤーによるボールの損傷、汚色の宣告について、球審と同等の権限を持つ。
(3)この規則を施行するにあたって、あらゆる方法で球審を援助し、規則の施行と規律の維持については、球審と同等の権限を持つ。ただし、フォーフィッテッドゲームの宣告はできない。
(c)一つのプレイに対して、2人以上の審判員が裁定を下し、しかもその裁定が食い違っていた場合には、球審は審判員を集めて協議し(監督、プレーヤーをまじえず審判員だけで)、その結果、通常球審(または、このような場合には球審に代わって解決にあたるようにリーグ会長から選任された審判員)が、最適の位置から見たのはどの審判員であったか、またどの審判員の裁定が正しかったかなどを参酌して、どの裁定をとるかを決定する。
このようにして、決定された裁定は最終のものであり、初めから一つの裁定が下された場合と同様に、試合は続行されなければならない。
8.04 審判員の報告義務
(a)審判員は、すべての規則違反またはその他の報告しなければならない出来事を、試合終了後にリーグ事務局まで報告する義務がある。ただし、監督またはプレーヤーを退場させた試合には、その理由を付記することを必要とする。
(b)審判員がトレーナー、監督、コーチまたはプレーヤーを次の理由で退場させた場合には、審判員はその詳細をリーグ事務局に報告する義務がある。
すなわち、これらの人々が、審判員、トレーナー、監督、コーチまたはプレーヤーに、野卑不作法な言を用いて黙過できない侮辱を加えたためか、暴力を働いたことが退場理由となった場合がそれである。
(c)リーグ事務局は、審判員から、監督、コーチ、トレーナー、プレーヤーを退場させた旨の報告を受けたならば、ただちに事務局の判断で適当と思われる制裁を科し、その旨を当事者ならびにその所属クラブに通告しなければならない。
制裁金を科せられた当事者が、リーグ事務局にその総額を支払わなかった場合には、支払いが完了するまで、試合に出場することもベンチに座ることも禁止される。
審判員に対する一般指示
審判員は、競技場においては、プレーヤーと私語を交わすことなく、またコーチスボックスの中に入ったり、任務中のコーチに話しかけるようなことをしてはならない。
制服は常に清潔に保ち、しかも正しく着用し、競技場においては、積極的に機敏な動作をとらなければならない。
クラブ役職員に対しては常に礼儀を重んずる必要はあるが、クラブ事務所を訪ねたり、特にあるクラブの役職員と親しくするようなことは避けなければならない。
審判員が競技場に入れば、ただその試合の代表者として試合を審判することだけに専念しなければならない。
試合中に悪い事態が起こった場合、その事態の解決を回避したという非難を受けるようなことがあってはならない。常に規則書を携行し、紛糾した問題を解決するにあたっては、たとえ10分間試合を停止することがあっても、よく規則書を調べ、その解決に万全を期して、その試合で不注意な規則適用の誤りをしないように努めなければならない。
試合を停滞させてはならない。試合は、しばしば審判員の活気ある真剣な運びによって、より以上の効果をもたらすものである。
審判員は、競技場における唯一の代表者であって、強い忍耐と、よりよい判断とを必要とするようなつらい立場におかれることがしばしば起こるが、悪い事態に対処するにあたっては、感情を棄てて自制することが、いちばん大切なことである。
審判員は自己の決定について、誤りを犯しているのではないかと疑うようなことがあってはならないし、また、たとえ誤りを犯したとしても、埋め合わせをしようとしてはならない。すべて見たままに基づいて判定を下し、ホームチームとビジティングチームとに差別をつけるようなことがあってはならない。
試合進行中はボールから目を離してはならない。走者が塁を踏んだかどうかを知ることも大切ではあるが、飛球の落ちた地点を見定めたり、送球の行方を最後まで見きわめることがより重要なことである。プレイの判定を下すにあたっては、早まることなく、正確を期さなければならず、野手がダブルプレイをなしとげるために送球する場合にも、あまり早く向きを変えてはいけない。アウトを宣告した後、一応落球の有無を確かめる必要がある。
走りながら〝セーフ〟〝アウト〟の宣告の動作をすることなく、そのプレイが終わるのを待って、宣告を下さなければならない。
各審判員は簡単な1組のサインを用意しておく必要がある。これによって、自己のエラーを悟れば、その明らかに間違った決定を正すことができる。〝プレイを正しく見た〟という確信があれば、〝他の審判員に聞け〟というプレーヤーの要求に従う必要はない。確信がなければ、同僚の1人に聞くこともよいが、これもあまり度を超すようなことなく、機敏にプレイを十分に把握して審判しなければならない。しかしながら、正しい判定を下すことが第1の要諦であることを忘れてはならない。疑念のあるときは、ちゅうちょせず同僚と協議しなければならない。審判員が威厳を保つことはもちろん大切であるが、〝正確である〟ということがより重要なことである。
審判員にとって最も大切な掟は、〝あらゆるプレイについて最もよい位置をとれ〟ということである。
たとえ判定が完璧であっても、審判員の位置が、そのプレイをはっきりと明確に見ることができる地点でなかったとプレーヤーが感じたときは、しばしば、その判定に異議を唱えるものである。
最後に、審判員は礼儀を重んじ、しかも公平にして厳格でなければならない。そうすれば、すべての人々から尊敬される。
9.00 記録に関する規則
本規則における用語の定義
1 ADJUDGED「アジャッジド」
審判員が、その判断に基づいて下す裁定である。
2 APPEAL「アピール」
守備側チームが、攻撃側チームの規則に反した行為を指摘して、審判員に対してアウトを主張し、その承認を求める行為である。
3 BALK「ボーク」
塁上に走者がいるときの、投手の反則行為である。その場合には、全走者に各1個の進塁を許す。(6.02a)
4 BALL「ボール」
ストライクゾーンを通過しなかった投球、または地面に触れた投球で、いずれも打者が打たなかったものである。
5 BASE「ベース」(塁)
走者が得点するために、触れなければならない四つの地点の一つである。通常その地点を表示するために、キャンバスバッグとゴムの平板が用いられる。
6 BASE COACH「ベースコーチ」
一塁、または、三塁のコーチスボックス内に位置して、打者または走者を指図する、ユニフォームを着用したチームの一員をいう。(5.03)
7 BASE ON BALLS「ベースオンボールズ」(四球)
打者が打撃中にボール4個を得るか、守備側チームの監督が打者を故意四球とする意思を審判員に示し、一塁に進むことが許される裁定である。守備側チームの監督が審判員に故意四球の意思を伝えた場合(この場合はボールデッドである)、打者には、ボール4個を得たときと同じように、一塁が与えられる。(5.05b1)
8 BATTER「バッター」(打者)
バッターボックスに入って攻撃するプレーヤーである。
9 BATTER-RUNNER「バッターランナー」(打者走者)
打撃を終わった打者がアウトになるまでか、または走者となったことに対するプレイが終了するまでの間を指す術語である。
10 BATTER'S BOX「バッタースボックス」
打者が打撃に際して立つべき場所である。
11 BATTERY「バッテリー」
投手と捕手とをあわせて呼ぶときに用いる。
12 BENCH or DUGOUT「ベンチ」または「ダッグアウト」
ユニフォームを着たプレーヤー、控えのプレーヤー、その他チームのメンバーが実際に競技にだずさわっていないときに、入っていなければならない施設である。(2.05、5.10k、6.04e)
13 BUNT「バント」
バットをスイングしないで、内野をゆるく転がるように意識的にミートした打球である。
14 CALLED GAME「コールドゲーム」
どのような理由にせよ、球審が打ち切りを命じた試合である。(7.01)(2025年改正:削除)
どのような理由にせよ、球審もしくはリーグ事務局が、その試合の完了する前に打ち切りを命じた試合である。(7.01)(2025年改正:追記)
15 CATCH「キャッチ」(捕球)
野手が、インフライトの打球、投球または送球を、手またはグラブでしっかりと受け止め、かつそれを確実につかむ行為であって、帽子、プロテクター、あるいはユニフォームのポケットまたは他の部分で受け止めた場合は、捕球とはならない。
また、ボールに触れると同時に、あるいはその直後に、他のプレーヤーや壁と衝突したり、倒れた結果、落球した場合は〝捕球〟ではない。
野手が飛球に触れ、そのボールが攻撃側チームのメンバーまたは審判員に当たった後に、いずれの野手がこれを捕らえても〝捕球〟とはならない。
野手がボールを受け止めた後、これに続く送球動作に移ってからボールを落とした場合は〝捕球〟と判断される。
要するに、野手がボールを手にした後、ボールを確実につかみ、かつ意識してボールを手放したことが明らかであれば、これを落とした場合でも〝捕球〟と判定される。(5.09a1)
【原注】野手がボールを地面に触れる前に捕らえれば、正規の捕球となる。その間、ジャッグルしたり、あるいは他の野手に触れることがあってもさしつかえない。
走者は、最初の野手が飛球に触れた瞬間から、塁を離れてさしつかえない。
野手はフェンス、手すり、ロープなど、グラウンドと観客席との境界線を越えた上空へ、身体を伸ばして飛球を捕らえることは許される。また野手は、手すりの頂上やファウルグラウンドに置いてあるキャンバスの上に飛び乗って飛球を捕らえることも許される。しかし、野手が、フェンス、手すり、ロープなどを超えた上空やスタンドへ、身体を伸ばして飛球を捕らえようとすることは、危険を承知で行うプレイだから、たとえ観客にその捕球を妨げられても、観客の妨害行為に対してはなんら規則上の効力は発生しない。
ダッグアウトの縁で飛球を捕らえようとする野手が、中へ落ち込まないように、中にいるプレーヤー(いずれのチームかを問わない)によって身体を支えられながら捕球した場合、正規の捕球となる。
【注】捕手が、身につけているマスク、プロテクターなどに触れてからはね返ったフライボールを地面に取り落とさずに捕らえれば、正規の〝捕球〟となる(ファウルチップについては定義34参照)。ただし、手またはミット以外のもの、たとえばプロテクターあるいはマスクを用いて捕らえたものは、正規の捕球とはならない。
16 CATCHER「キャッチャー」(捕手)
本塁の後方に位置する野手である。
16 CATCHER「キャッチャー」(捕手)
本塁の後方に位置する野手である。
17 CATCHER'S BOX「キャッチャースボックス」
投手が投球するまで、捕手が位置すべき場所である。
18 CLUB「クラブ」
プレイングフィールドとこれに付属する施設を用意してチームを形成し、かつリーグに所属するチームであると表明することに責任が持てる人、または人々の団体である。
19 COACH「コーチ」
コーチはチームのユニフォームを着用した一員であってベースコーチを務めるだけでなく、監督の指示する任務を果たすために、監督によって選ばれた人である。
20 DEAD BALL「デッドボール」
規則によって、プレイが一時停止されたために、 プレイからはずされたボールをいう。(5.06c)
21 DEFENSE or DEFENSIVE「ディフェンスまたはディフェンシィブ」(守備側)
競技場内における守備側チームまたはそのプレーヤーをいう。
22 DOUBLE-HEADER「ダブルヘッダー」
相次いで行なう2試合をいい、この2試合はあらかじめ日程に組まれた場合もあり、日程を修正して組み入れられる場合もある。(4.08)
23 DOUBLE PLAY「ダブルプレイ」(併殺)
守備側プレーヤーが連続した動作で、2人の攻撃側プレーヤーをプットアウトにするプレイであるが、この二つのプットアウトの間に失策が介在したものはダブプレイとみなされない。(9.11)
(a)フォースダブルプレイは、フォースアウトの連続によるダブルプレイである。
(b)リバースフォースダブルプレイは、その第1アウトがフォースプレイで行なわれ、第2アウトがフォースアウトされるはずの走者に対して行なわれたダブルプレイである。
例-1アウト走者一塁、打者が一塁手にゴロを打ち、打球をつかんだ一塁手が一塁に触れ(2アウト)、続いて二塁手または遊撃手に送球して走者をアウト(タッグプレイ)にした場合。
例-0アウト満塁、打者が三塁手にゴロを打ち、打球をつかんだ三塁手が三塁に触れ(1アウト)、続いて捕手に送球して三塁走者をアウト(タッグプレイ)にした場合。
24 DUGOUT「ダッグアウト」
「ベンチ」の定義参照。
25 FAIR BALL「フェアボール」
打者が正規に打ったボールで、次に該当するものをいう。(巻頭図参照)
(a)本塁一塁間、または本塁三塁間のフェア地域内に止まったもの。
(b)一塁または三塁を、バウンドしながら外野の方へ越えて行く場合に、フェア地域に触れながら通過するか、またはその上方空間を通過したもの。
(c)一塁、二塁または三塁に触れたもの。
(d)最初に落ちた地点が一塁二塁および二塁三塁を結ぶ線上であったか、あるいはその線を越えた外野の方のフェア地域内であったもの。
(e)フェア地域内またはその上方空間で、審判員またはプレーヤーの身体に触れたもの。
(f)インフライトの状態でプレイングフィールドを越えて行く場合に、フェア地域の上方空間を通過したもの。
フェア飛球は、ボールとファウルライン(ファウルボールを含む)との、相互の位置によって判定しなければならない。野手がボールに触れたときに、フェア地域にいたか、ファウル地域にいたかによって判定してはいけない。
【原注】飛球が、最初一塁本塁間または三塁本塁間の内野に落ちても、一塁または三塁を通過する前に、プレーヤーまたは審判員に触れないで、ファウル地域へ転じ去った場合は、ファウルボールである。飛球がファウル地域で止まるか、ファウル地域でプレーヤーに触れた場合も、ファウルボールである。
飛球が一塁または三塁ベースに当たるか、あるいは、一塁または三塁を超えた外野のフェア地域に落ちれば、その後ファウル地域にバウンドして出た場合でも、フェアボールである。
審判員が、フェア、ファウルを正確に判定できるように、ファウルポールのフェンスより上に出ている部分に、フェア地域に向かって金網を張り出して取りつけることが望ましい。
【注】打球が地面以外のもの、たとえば打者が捨てたバット、捕手がはずしたマスクなどに、フェア地域で触れたときは、ボールインプレイである。
【問】打球が三塁についている走者に触れてから、フェア地域に反転した場合は、いかに判定すべきか。また、これがファウル地域に反転した場合はどうか。
【答】ボールが走者と接触した位置によって、フェアかファウルかを判定すべきものであり、フェア地域で触れたときは、フェアボールとなる。したがって、走者はフェアの打球に触れたという理由でアウトになる。(5.09b7参照)
26 FAIR TERRITORY「フェアテリトリ」(フェア地域)
本塁から一塁、本塁から三塁を通って、それぞれ競技場のフェンスの下端まで引いた直線と、その各線に垂直な上方空間との内側の部分を指す。各ファウルラインは、フェア地域に含まれる。
27 FIELDER「フィールダー」(野手)
守備側のプレーヤーをいう。
28 FIELDER'S CHOICE「フィールダースチョイス」(野手選択)
フェアゴロを扱った野手が一塁で打者走者をアウトにする代わりに、先行走者をアウトにしようと他の塁へ送球する行為をいう。また、(a)安打した打者が、先行走者をアウトにしようとする野手の他の塁への送球を利して、1個またはそれ以上の塁を余分に奪った場合や、(b)ある走者が、盗塁や失策によらないで、他の走者をアウトにしようとする野手の他の塁への送球を利して進塁した場合や、(c)盗塁を企てた走者が守備側チームが無関心のためになんら守備行為を示さない間に進塁した場合などにも(9.07g)、これらの打者走者または走者の進塁を記録上の用語として野手選択による進塁という。
29 FLY BALL「フライボール」(飛球)
空中高く飛ぶ打球をいう。
30 FORCE PLAY「フォースプレイ」
打者が走者となったために、塁上の走者が、規則によって、その塁の占有権を失ったことが原因となって生じるプレイである。(5.09b6)
【注】次の原注に述べられているフォースプレイによるアウト、すなわちフォースアウト(封殺)と得点との関係は、5.08に明示されている。
【原注】フォースプレイを理解するために最も注意を要する点は、最初はフォースの状態 であっても、その後のプレイによっては、フォースの状態でなくなるということである。
例──1アウト満塁、打者一塁に強いゴロを放ったが、一塁手がこれを止めてただちに塁に触れ、打者をアウトにすれば、フォースの状態でなくなるから、二塁に向かって走っている走者は触球されなければアウトにはならない。したがって、一塁走者が二塁で触球アウトになる前に、二塁、三塁にいた走者が本塁を踏んだ場合には、この得点は認められる。しかし、これに反して、ゴロを止めた一塁手がただちに二塁に送球して一塁走者をフォースアウトにした後、さらに一塁への返球で打者もアウトにして3アウトとなった場合には、二塁、三塁の走者が本塁を踏んでいても得点とは認められない。
例──封殺でない場合。1アウト走者一・三塁のとき、打者は外野に飛球を打ってアウトになり、2アウトとなった。三塁に触れていた走者は、捕球を見て本塁を踏んだ。しかし一塁の走者は、捕球当時離塁していたので帰塁しようとしたが、外野手からの返球で一塁でアウトになり、3アウトとなった。この場合は、フォースアウトではないから、一塁走者のアウトより前に、三塁走者が本塁に触れたと審判員が認めれば、その得点は記録される。
31 FORFEITED GAME「フォーフィッテッドゲーム」(没収試合)
規則違反のために、球審が試合終了を宣告して、9対0で過失のないチームに勝ちを与える試合である。(7.03)
32 FOUL BALL「ファウルボール」
打者が正確に打ったボールで、次に該当するものをいう。(巻頭図参照)
(a)本塁一塁間または本塁三塁間のファウル地域に止まったもの。
(b)一塁または三塁を、バウンドしながら外野の方へ超えて行く場合に、ファウル地域に触れながら通過するか、あるいはファウル地域上の空間を通過したもの。
(c)一塁または三塁を超えたファウル地域内に、最初に落下したもの。
(d)ファウル地域内またはその上方空間で、審判員またはプレーヤーの身体、あるいは、地面以外のものに触れたもの。
ファウル飛球は、ボールとファウルライン(ファウルポールを含む)との、相互の位置によって判定しなければならない。 野手がボールに触れたときに、フェア地域にいたか、ファウル地域にいたかによって判定してはならない。
【原注】野手に触れない打球が、投手板に当たり、リバウンドして本塁一塁間または本塁三塁間のファウル地域に出て止まった場合には、ファウルボールである。
【注1】打者の所持するバットに、打球(バントを含む)がファウル地域で触れたときは(もちろん故意ではなく)、ファウルボールである。
また、打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッタースボックス内にいる打者の身体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは身体と接触した位置に関係なく、ファウルボールである。
【注2】打球が地面以外のもの、すなわちバックネットやフェンスはもちろん、打者が捨てたバット、捕手がはずしたマスク、地上に置いてある審判員のほうきなどに、ファウル地域でいったん触れれば、その後転じてフェア地域内に止まってもファウルボールである。
33 FOUL TERRITORY「ファウルテリトリ」(ファウル地域)
本塁から一塁、本塁から三塁を通って、競技場のフェンスの下端まで引いた直線と、その線に垂直な上方空間との外側の部分を指す。(各ファウルラインはファウル地域に含まれない)
34 FOUL TIP「ファウルチップ」
打者の打ったボールが、鋭くバットから直接捕手に飛んで、正規に捕球されたもので、捕球されなかったものはファウルチップとはならない。ファウルチップはストライクであり、ボールインプレイである。(5.09a2)
35 GROUND BALL「グラウンドボール」
地面に転がるか、または地面に低くバウンドしていく打球をいう。
36 HOME TEAM「ホームチーム」
あるチームが自分の球場で試合を行う場合、相手チームに対して、そのチームを指して呼ぶ術語である。試合が中立の球場で行なわれる場合には、ホームチームは相互の協定によって指定される。
【注】ホームチームの相手チームをビジティングチームまたはビジターと呼ぶ。
37 ILLEGAL or ILLEGALLY「イリーガルまたはイリガリー」
本規則に反することをいう。
38 ILLEGAL PITCH「イリーガルピッチ」(反則投球)
(1)投手が、投手板に触れないで投げた打者への投球、(2)クイックリターンピッチ、をいう。──走者が塁にいるときに反則投球をすれば、ボークとなる。
39 INFIELDER「インフィールダー」(内野手)
内野に守備位置をとる野手をいう。
40 INFIELD FLY「インフィールドフライ」
0アウトまたは1アウトで、走者が一・二塁、一・二・三塁にあるとき、打者が打った飛球(ライナーおよびバントを企てて飛球となったものを除く)で、内野手が普通の守備行為をすれば、捕球できるものをいう。この場合、投手、捕手および外野手が、内野で前記の飛球に対して守備したときは、内野手と同様に扱う。
審判員は、打球が明らかにインフィールドフライになると判断した場合には、走者が次の行動を容易にとれるように、ただちに〝インフィールドフライ〟を宣告しなければならない。また、打球がベースラインの近くに上がった場合には〝インフィールドフライ・イフ・フェア〟を宣告する。
インフィールドフライが宣告されてもボールインプレイであるから、走者は離塁しても進塁してもよいが、その飛球が捕らえられれば、リタッチの義務が生じ、これを果たさなかった場合には、普通のフライの場合と同様、アウトにされるおそれがある。
たとえ、審判員の宣告があっても、打球がファウルボールとなれば、インフィールドフライとはならない。
インフィールドフライと宣告された打球が、最初に(何物にも触れないで)内野に落ちても、ファウルボールとなれば、インフィールドフライとはならない。また、この打球が、最初に(何物にも触れないで)ベースラインの外側へ落ちても、結局フェアボールとなれば、インフィールドフライとなる。
【原注】審判員はインフィールドフライの規則を適用するにあたって、内野手が普通の守備行為をすれば捕球できるかどうかを基準とすべきであって、たとえば、芝生やベースラインなどを勝手に境界線として設定すべきではない。たとえ、飛球が外野手によって処理されても、それは内野手によって容易に捕球されるはずだったと審判員が判断すれば、インフィールドフライとすべきである。インフィールドフライはアピールプレイであると考えられるような要素はどこにもない。審判員の判断がすべて優先し、その決定はただちに下されなければならない。
インフィールドフライが宣告されたとき、走者は危険を承知で進塁してもよい。インフィールドフライと宣告された飛球を内野手が故意落球したときは、5.09(a)(12)の規定にもかかわらずボールインプレイである。インフィールドフライの規則が優先する。
インフィールドフライが宣告されたときに妨害が発生した場合、打球がフェアかファウルかが確定するまでボールインプレイの状態は続く。打球がフェアになれば、野手の守備を妨害した走者と、打者がアウトとなる。打球がファウルになれば、野手の守備を妨害した走者だけがアウトとなり、その打球が捕球されたとしても、打者は打ち直しとなる。
【注】インフィールドフライは、審判員が宣告して、初めて効力を発する。
41 IN FLIGHT「インフライト」
打球、送球、投球が、地面かあるいは野手以外のものにまだ触れていない状態を指す。
42 IN JEOPARDY「インジェパーディ」
ボールインプレイのとき、攻撃側プレーヤーがアウトにされるおそれのある状態を示す術語である。
43 INNING「イニング」(回)
各チームが攻撃と守備とを交互に行なう、試合の一区分である。この間、各チームは守備の際、それぞれ3個のプットアウトを果たす。各チームは1イニングの半分ずつをその攻撃にあてる。
【注】本規則では、ビジティングチーム(先攻チーム)の攻撃する間を表といい、ホームチーム(後攻チーム)の攻撃する間を裏という。
44 INTERFERENCE「インターフェアランス」(妨害)
(a)攻撃側の妨害──攻撃側プレーヤーがプレイしようとしている野手を妨げたり、さえぎったり、はばんだり、混乱させる行為である。(6.01aペナルティ参照)
(b)守備側の妨害──投球を打とうとする打球を妨げたり、じゃまをする野手の行為をいう。
(c)審判員の妨害──(1)盗塁を阻止しようとしたり、塁上の走者をアウトにしようとする捕手の送球動作を、球審がじゃましたり、はばんだり、妨げた場合、(2)打球が、野手(投手を除く)を通過する前に、フェア地域で審判員に触れた場合に起こる。
(d)観衆の妨害──観衆が競技場内に入ったり、スタンドから乗り出したり、または競技場内に物を投げ込んで、インプレイのボールを守備しようとしている野手の邪魔をした場合に起こる。
45 LEAGUE「リーグ」
あらかじめ組まれたスケジュールによって、所属リーグの選手権試合を本規則に従って行なうチームを保有するクラブの集まりである。
46 LEGAL or LEGALLY「リーガルまたはリーガリー」
本規則に準拠したことをいう。
47 LIVE BALL「ライブボール」
インプレイのボールをいう。
48 LINE DRIVE「ラインドライブ」(ライナー)
打者のバットから鋭く、直線的に、地面に触れないで飛んだ打球である。
49 MANAGER「マネージャー」(監督)
プレイングフィールドにおける自己のチームの行動に責任を持ち、チームを代表して審判員ならびに相手チームと協議するように、クラブから指定された人である。プレーヤーが監督に指定されることも許される。(4.02)
50 OBSTRUCTION「オブストラクション」(走塁妨害)
野手がボールを持たないときか、あるいは ボールを処理する行為をしていないときに、走者の走塁を妨げる行為である。(6.01h1・2)
【原注】ここにいう〝野手がボールを処理する行為をしている〟とは、野手がまさに送球を捕ろうとしているか、送球が直接野手に向かってきており、しかも十分近くにきていて、野手がこれを受け止めるにふさわしい位置をしめなければならなくなった状態をいう。これは一に審判員の判断に基づくものである。野手がボールを処理しようとして失敗した後は、もはやボールを処理している野手とはみなされない。たとえば、野手がゴロを捕ろうとしてとびついたが捕球できなかった。ボールは通り過ぎていったのにもかかわらずグラウンドに横たわったままでいたので、走者の走塁を遅らせたような場合、その野手は走塁妨害をしたことになる。
51 OFFENSE「オフェンス」(攻撃側)
攻撃中のチーム、またはそのプレーヤーをいう。
52 OFFICIAL SCORER「オフィシャルスコアラー」(公式記録員)
9.00参照
53 ORDINARY EFFORT「オーディナリーエフォート」(普通の守備行為)
天候やグラウンドの状態を考慮に入れ、あるプレイに対して、各リーグの各守備位置で平均的技量を持つ野手の行なう守備行為をいう。
【原注】この用語は、定義40のほか記録に関する規則でたびたび用いられる、個々の野手に対する客観的基準である。言い換えれば、ある野手が、その野手自身の最善のプレイを行なったとしても、そのリーグの同一守備位置の野手の平均的技量に照らして劣ったものであれば、記録員はその野手に失策を記録する。
54 OUT「アウト」
守備側チームが攻撃側となるために、相手チームを退けるのに必要な三つのプットアウトのうちの一つである。
55 OUTFIELDER「アウトフィールダー」(外野手)
競技場の内で、本塁から最も遠い、いわゆる外野に守備位置をとる野手である。
56 OVERSLIDE or OVERSLIDING「オーバースライドまたはオーバースライディング」
攻撃側プレーヤーが、滑り込みの余勢のために塁から離れて、アウトにされるおそれのある状態におかれる行為をいう。本塁から一塁に進む場合には、ただちに帰ることを条件として、滑り込みの余勢のために塁を離れることは許されている。
57 PENALTY「ペナルティ」
反則行為に対して適用される規則をいう。
58 PERSON of player or umpire「パースン・オブ・プレーヤー・オア・アンパイヤー」(プレーヤーまたは審判員の身体)
その身体、着衣および身につけているものをいう。
59 PITCH「ピッチ」(投球)
投手が打者に対して投げたボールをいう。
【原注】あるプレーヤーから他のプレーヤーに送られるボールは、すべて送球である。
60 PITCHER「ピッチャー」(投手)
打者に投球するように指定された野手をいう。
61 Pitcher's PIVOT FOOT「ピッチャース・ピボットフット」(投手の軸足)
投手が投球の際、投手板に触れている足をいう。
62 〝PLAY〟「プレイ」
球審が試合を開始するとき、およびボールデッドの状態から競技を再開するときに用いる命令をいう。
63 POSTPONED GAME 「ポストポンドゲーム」(2025年改正:追記)
どのような理由にせよ、予定された日に開始できず、延期された試合である。
64 QUICK RETURN Pitch「クイックリターンピッチ」
打者の虚をつくことを意図した投球をいう。これは反則投球である。
65 REGULATION GAME「レギュレーションゲーム」(正式試合)
7.01参照。
66 RETOUCH「リタッチ」
走者が、規則によって、帰塁しなければならない塁へ帰る行為をいう。
【注】〝リタッチ〟には、飛球が捕らえられたときに離塁していた走者が、進塁の起点となった塁に帰塁する行為と、飛球が打たれたとき塁にタッチしていて、野手が捕球したのを見て次塁へスタートする行為の二つがある。(5.09b5、5.09c1参照)
67 RUN or SCORE「ランまたはスコア」(得点)
攻撃側のプレーヤーが打者から走者となって、一塁、二塁、三塁、本塁の順序で各塁に触れた場合に、与えられる得点をいう。(5.08)
68 RUN-DOWN「ランダウン」(挟撃)
塁間で走者をアウトにしようとする守備側の行為をいう。
69 RUNNER「ランナー」(走者)
塁に向かって進んだり、触れたり、戻ったりする攻撃側プレーヤーをいう。
70 〝SAFE〟「セーフ」
走者にその得ようとしていた塁を占有する権利を与える、審判員の宣告をいう。
71 SET POSITION「セットポジション」
二つの正規な投球姿勢のうちの一つである。
72 SQUEEZE PLAY「スクイズプレイ」
三塁に走者がいる場合、バントによって走者を得点させようとするチームプレイを指す術語である。
73 STRIKE「ストライク」
次のような、投手の正規な投球で、審判員によって〝ストライク〟と宣告されたものをいう。
(a)打者が打った(バントの場合も含む)が、投球がバットに当たらなかったもの。
(b)打者が打たなかった投球のうち、ボールの一部がストライクゾーンのどの部分でもインフライトの状態で通過したもの。
(c)0ストライクまたは1ストライクのとき、打者がファウルしたもの。
(d)バントして、ファウルボールとなったもの。
【注】普通のファウルは、2ストライクの後はストライクとして数えられないが、バントのファウルに限って、ボールカウントには関係なく常にストライクとして数えられるから、2ストライク後にバントしたものがファウルボールとなれば、打者は三振となる。ただし、バントがフライとして捕えられた場合は、フライアウトとなる。
(g)ファウルチップになったもの。
(e)打者が打った(バントした場合も含む)が、投球がバットには触れないで打者の身体または着衣に触れたもの。
(f)バウンドしない投球がストライクゾーンで打者に触れたもの。
74 STRIKE ZONE「ストライクゾーン」
打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、ひざ頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間をいう。
このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである。
【注】投球を待つ打者が、いつもと異なった打撃姿勢をとってストライクゾーンを小さく見せるためにかがんだりしても、 球審は、これを無視してその打者が投球を打つための姿勢に従って、ストライクゾーンを決定する。
75 SUSPENDED GAME「サスペンデッドゲーム」(一時停止試合)
後日、その続きを行なうことにして、一時停止された試合をいう。(7.02)
76 TAG「タッグ」(触球)
野手が、手またはグラブに確実にボールを保持して、その身体を塁に触れる行為、あるいは確実に保持したボールを走者に触れるか、手またはグラブに確実にボールを保持して、その手またはグラブを走者に触れる行為をいう。
しかし、塁または走者に触れると同時、あるいはその直後に、ボールを落とした場合は〝触球〟ではない。
野手が塁または走者に触れた後、これに続く送球動作に移ってからボールを落とした場合は、〝触球〟と判定される。
要するに、野手が塁または走者に触れた後、ボールを確実につかんでいたことが明らかであれば、これを落とした場合でも〝触球〟と判定される。
本定義では、プレーヤーが身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具は、プレーヤーの身体の一部とはみなさない。
77 THROW「スロー」(送球)
ある目標に向かって、手および腕でボールを送る行為をいい、常に投手の打者への投球(ピッチ)と区別される。
78 TIE GAME「タイゲーム」
球審によって終了を命じられた正式試合で、両チームの得点が等しかったものをいう。
79 〝TIME〟「タイム」
正規にプレイを停止させるための審判員の宣告であり、その宣告によってボールデッドとなる。
80 TOUCH「タッチ」
プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、着用しているユニフォームあるいは用具(ただし、プレーヤーが身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具は除く)のどの部分に触れても〝プレーヤーまたは審判員に触れた〟ことになる。
81 TRIPLE PLAY「トリプルプレイ」(三重殺)
守備側プレーヤーが連続した動作で、3人の攻撃側プレーヤーをプットアウトにするプレイであるが、この三つのプットアウトの間に失策が介在したものは、トリプルプレイとはみなされない。
82 WILD PITCH「ワイルドピッチ」(暴投)
捕手が普通の守備行為で処理することができないほど高すぎるか、低すぎるか、横にそれるかした、投手の正規な投球をいう。
83 WIND-UP POSITION「ワインドアップポジション」
二つの正規な投球姿勢のうちの一つである。
競技者必携
投手の12秒及び20秒ルールの取り扱い基準
2020年から採用した投手に関する「12秒及び20秒ルール」の取り扱いに関する基準を以下に示す。
1.12秒及び20秒ルール
投手は、捕手、その他の内野手または審判員からボールを受けた後、走者がいない場合には12秒以内に、走者がいる場合には20秒以内に投球しなければならない。
違反した場合、球審は走者が塁にいない場合にはただちにボールを宣告し、走者がいる場合は警告を発することとし、同一の投手が2度繰り返したら、3度目からはその都度ボールを宣告する。
なお、塁に牽制球を送球したときは、20秒の計時をリセットする。
2.計時
計時は二塁塁審がストップウォッチを持って行う。(3人制は三塁塁審)
3.12秒ルールの適用
①走者がいない場合に適用する。
②12秒の計時は、投手がボールを所持し、打者がバッターボックスに入り、投手に面したときに始まり、投手が投球動作を開始したときに終わる。
※審判員は5.07(C)(1)(2)について、強く指導すること。
③12秒を経過したとき(13秒になったとき)、二塁塁審(三塁塁審)はタイムを宣告し、球審に12秒が経過したことを知らせる。
※二塁塁審(三塁塁審)のタイムの宣告と同時にボールデッドとなる。
※タイムの宣告にもかかわらず投手が投球した以降のプレイは無効とする。
④二塁塁審cの知らせを受けた球審は、ボールを宣告する。その際、球審は投手及び守備側の監督に12秒ルールを適用したことを告げる。
4.20秒ルールの適用
①走者がいる場合に適用する。
②20秒の計時は、次のときに始まり、いずれの場合も投手が投球動作を開始したときに終わる。
A)イニングが始まるときやボールデッドになったときは、球審がプレイを宣告したとき。
B)ボールインプレイの状態で、新しい打者が打撃を開始するときや、打者がバッターボックスの外に出ざるを得なくなったときなどは、投手がボールを所持し、打者がバッターボックスに入って投手に面したとき。
C)ボールインプレイの状態で、打者がバッターボックス内で打撃を継続しているときは、投手が捕手や他の野手からボールを受け取り、打者に面したとき。
※審判員は5.07(C)(1)(2)について、強く指導すること。
③20秒を経過したとき(21秒になったとき)、二塁塁審(三塁塁審)は「タイム」を宣告し、球審へ20秒を経過したことを伝達する。
※二塁塁審(三塁塁審)のタイムの宣告と同時にボールデッドとなる。
※タイムの宣告にもかかわらず投手が投球した以降のプレイは無効とする。
④二塁塁審(三塁塁審)の知らせを受けた球審は、同一投手の2度目までの違反に対して投手および守備側の監督に20秒が経過したことの警告を発し、その回数を知らせる。
⑤同一投手が3度目に20秒を経過し21秒になったとき、二塁塁審(三塁塁審)と球審は、走者がいないときと同様の処置をする。
⑥投手が塁に牽制球を送球したときは、20秒の計時をリセットする。
※投手板をはずしただけのときや偽投のときは、計時を継続する。
※送りバントのケースなど、捕手が内野手にサインを出している間も、計時は継続する。
アンチ・ドーピングを通して考えるースポーツのフェアとは何か-
私たちが守りたい大切なスポーツの価値の基盤~努力するからこそ得られる本当の勝利
スポーツを通して、何か得られたものはありますか?
答えは人それぞれ違うと思います。
スポーツを通して、ルールを守ることの大切さ、チームワークの大切さなど多くのことを学び、また一生思い出となるようなすばらしい経験を持ち、スポーツの価値を感じたことはないでしょうか。
・自分を信じて最善の努力をし、懸命に勝利を目指そうとすること-Excellence
・仲間を信じること-Friendship
・対戦相手や仲間を尊敬すること-Respect
-これらは、国や国籍、時間の経過を超えて尊重されている、スポーツの価値の基盤。みなさんが決められたルールに従い、全力でスポーツに打ち込んできたからこそ、得られたものです。
仮に、スポーツを通して得られたスポーツの価値が壊されることになったら、どのように感じますか? 結果や勝利だけにこだわり、ルール違反する人がいたら、どのように思うでしょう?
アンチ・ドーピング活動を学ぶことを通じて、みなさんがスポーツに対してどのように向き合い、スポーツを通してどのような存在となるべきか、目指すべきかについても、考えてみましょう。
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
試合のスピード化・マナーに関する確認事項
技術委員会
選手・審判員個々が強く意識し行動することが、野球競技をより楽しく面白く発展させると確信します。テンポの良いゲームを展開しましょう。
1)チーム
①攻守交代は、駆け足でスピーディに行うこと。(コーチも励行する。)
②日程・時間に余裕がある場合でもスピーディな試合進行を意識すること。
③ベンチ前の整列は、出過ぎないこと。プレイのコールを待たせないこと。
④投手が投球動作を開始したら投手の動揺を誘う声を発しない。
2)投手
①遅延行為とみなされる投手のけん制球はやめさせる。
②投手の基本的なルールを徹底させて下さい。
③投手は、ロジンバッグを指先だけで使用し、丁寧に取り扱うこと。
④捕手から返球を受けた投手は、速やかに投手板に着き投球動作に入ること。
3)捕手
①捕手は、返球したり声をかけるためにホームプレートの前や横に出過ぎないこと。
②サインについて、複雑なものは無くし、速やかに出すよう要請する。
③捕手の行動を機敏にさせる。
速やかなサイン・用具の脱着・バックアップや打ち合わせの後、速やかに守備位置に戻る。
4)打者
①攻撃側の第一打者・次打者を所定の位置に速やかに着くように喚起する。
②打者はみだりに打者席をはずさないこと。(サインは必ず打者席内で見ること。)
③次打者席では、投手が投球に関する動作(サインを見る姿勢)に入ったら速やかにスイングをやめ投球を注視すること。
5)野手
①内野手のボール回しは定位置で1回りとする。
②内野手が投手に返球するときは、定位置で返球すること。
マウンドまで持って行かせない。このような行動は即注意し徹底させること。
③内野手がアドバイスなどでマウンドへ近づかないよう注意すること。(タイムの回数制限に注意)
④タイムを掛け意図的にスパイクの紐の結び直しは認めない。
6)審判員
①グラウンド内の移動は、常に走ること。
②代打・代走の通告は、氏名とともに背番号を放送席に見せて告げること。
③交代選手は都度打順表で確認すること。
④45フィート前進後、捕手よりも戻りを早くし待機すること。
⑤節度・キレある判定・コールを実践すること。
⑥ボールデッドのときの時間を早くすることを意識すること。
以上
Ⅰ 図説一覧
Ⅱ 審判員・選手への注意事項
全国大会に参加するチーム・審判員の注意事項
開会式について
- 選手集合所では、代表旗を完全にセットし、代表旗(主将が持つ)を先頭に、背の低い順に2列で行進する。
- 開会式は、ユニフォーム並びにスパイクで入場行進をする。ただし、球場の芝保護の為アップシューズも認める。(ウインドブレーカー等の着用を禁止する。)
- 開会式は大会の意義あるセレモニーであり、手を大きく振って照れずに元気よく行進することが会場地への礼儀でもある。チームで行進の練習を希望する。
大会審判員について
- 公式試合の審判は、全日本軟式野球連盟に登録された審判員が行う。
- 全国大会の派遣は、60歳以下の指導員とし、その年の各ブロック指導員研修会を受講した者とする。なお、全国大会におけるブロック派遣は、その年のブロック講習会(ブロック講習会が秋季開催の場合は、前年の講習会)を受講した63歳以下の指導員および各支部から推薦した審判員とする。
◆少年部、学童部、女子大会
§1 競技運営に関する注意事項
- 球場の開門は、試合開始90分前とする。
- 監督会議で説明または決められた事項は、必ずチーム全員に徹底すること。
- 参加申込書(登録原簿)提出後は、選手の追加、変更及び背番号の変更は認めない。ただし、疾病・負傷等の特別な場合は、資格審査の上、認めることもある。
- ベンチは、組み合わせ番号の若い方を一塁側とする。ただし、1チームが2試合続けて行う場合はベンチの入れ替えをしないことがある。
- チームは、試合開始予定時刻の60分前までに球場に到着し、大会本部から打順表を受け取ること。
- ベンチに入れる人員は、
- 登録されユニフォームを着用した監督30番、コーチ29番・28番および選手25名以内と、チーム代表者、マネージャー、スコアラー、トレーナー(有資格者)各1名とする。ただし、監督、コーチは20歳以上でなければならない。
- 熱中症対策として、保護者2名までベンチに入ることができる。
- 打順表(登録された選手全員を記入したもの)の提出は、
- その日の第1試合は開始予定時刻の30分前までに
- 《少年部、女子中学》第2試合以降は前の試合の4回終了時に
- 《学童部、女子共》第2試合以降は前の試合の3回終了時
監督と主将が大会本部に提出し、登録原簿と照合ののち、球審立合いのもと攻守を決定する。
- シートノック
- 補助員としてコーチ(背番号28・29)を認める。ダートサークル内に入る補助員はヘルメットを着用すること。なお、コーチ1人のブルペン捕手を試合開始前までの間許可する。(マスクを着用すること)
- 後攻チームより行い、時間は5分間とする。
- ノッカーも必ず選手と同様のユニフォームを着用し、捕手はプロテクター、レガース、捕手用ヘルメット、ファウルカップを必ず着用すること。
- 大会運営上、シートノックを行なわずに試合を開始することもある。この場合は、攻守決定時に通知する。
- シートノックを行うことができない補助員もいることから、ベンチ前でのサイドノックを認める。
- 球場内ではトスバッティングのみ認める。
- その日の第1試合に出場のチームは、外野に限り練習に使用してもよい。その際、アップ用の服装(同一が望ましい)でもよいが、打順表の提出時には、全員ユニフォームに着替えていること。
第2試合以降のチームは、試合開始予定時刻に関係なく、前の試合が終了次第シートノックを行うので、終了挨拶の間にグラウンドに入り、ベンチの外野寄りに用具を置きキャッチボールを行う。 - 次の試合のバッテリーは、攻守決定後、競技場内のブルペンを使用することができる。
- 突発事故の際のタイムについて(規則5.12b(3)(8)関連)
試合中、プレーヤーの人命にかかわるような事態が発生した場合、人命尊重を第一に、プレイの進行中であっても、審判員の判断でタイムを宣告することができる。この際、その宣告によってボールデッドとならなかったらプレイはどのようになったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。 - 打者が頭部にヒット・バイ・ピッチを受けたときには、その程度を問わず臨時代走の処置を行う。塁上の走者が負傷した場合で、一時走者を代えないと試合の中断が長引くと審判員が判断したときは、臨時代走の処置を行うことができる。
臨時代走者は、試合に出ている9人の中から代走(打順の前位の者、ただし、投手を除く)を認めて試合を進行する。
臨時代走者の役割は、アウトとなるか、得点するか、またはイニングが終了するまで継続する。(規則5.10e【原注】関連) - ベンチ内での電子機器類(携帯電話、パソコン等)の使用を禁止するが、電子スコア記録用として1台の使用を認める。指示用のメガホンは、ベンチ内に限り1個の使用を認める。
- 第2試合以降は、試合開始予定時刻前でも、前の試合が終了した後20分を目安に次の試合を開始する。
- ダブルヘッダーは、1日2試合まで行うことができる。継続して行う場合は、試合終了後30分を目安に開始する。特別継続試合はこれに抵触しない。
- 試合開始予定時刻になっても会場に到着しないチームは、原則として棄権とみなす。
- 雨天の場合
- 雨天の場合でも日程の都合上、球場が使用可能な場合は試合を行う。
- 当日試合を全く行わない場合と、午前中見合わせて午後から行う場合があるので、大会本部からの連絡に注意すること。なお、当日試合が不可能な場合には大会本部から連絡する。
- 試合中雷が発生した場合は、状況を判断し、試合を中断して全員安全な場所に避難させ、気象台等の状況を掌握し、その後の処置を行う。
- 次のイニングに引き続き投げる投手は、ベンチ正面でのキャッチボールを禁止するが、ベンチ外野側角からポール方向のファウルテリトリーでの軽いキャッチボールは認める。また、ブルペンでのキャッチボールは2組4名以内を認める。
- 試合の挨拶は、試合前後の本塁整列の挨拶が全てである。チームの大会本部及び相手チームへの挨拶は不要である。(応援団への挨拶は奨励)試合に敬意を表し本部役員も起立し挨拶をする。
§2 競技に関する連盟特別規則
《学童部(女子共)》
1 正式試合
- 6回戦
- ゲームは6回戦であるが、暗黒、降雨などで6回完了まで進まなくとも、5回を終了すればゲームは成立する。
- 健康維持を考慮し、5回終了前であっても、試合開始後1時間30分経過した場合は、新しいイニングには入らない。均等回完了をもって試合を決する。
- ゲームは上記①・②どちらも試合成立となる。
「学童部4年生以下の大会は5回戦」 - 守備の時間が長い場合(概ね20分)には健康維持を考慮し、審判員の判断で給水タイムを設けることとする。(試合時間には入れない)
- コールドゲームの得点の扱い
連盟では、例えば両チームが、5回の攻撃を均等に完了し、6回の表に先攻チームが得点したが、後攻チームはその裏、同点もしくはリードしないままに、暗黒・降雨などにより試合中止を宣せられたような場合は、均等回の得点をもって勝敗を決する。
2 延長戦
6回を完了し同点の場合、または、試合開始後1時間30分を経過し同点の場合は、いずれも直ちにタイブレーク方式で試合を決する。
3 タイブレーク方式
- 継続打順で、前回の最終打者を一塁走者、その前の打者を二塁走者とする。すなわち、0アウト一塁・二塁の状態にして、投手の投球制限を遵守の上、勝敗が決するまで続行する。
- 得点の記録は、合計得点とする。
(例)1-1(タイ1回)4-3
4 特別継続試合
- 暗黒、降雨などで5回以前に中止となった場合、また5回を過ぎ正式試合になって同点で試合が中止の場合および1時間30分を経過し同点の場合は、翌日の第1試合に先立って特別継続試合を行う。
- 5回に満たない場合は、打ち切りになったところから試合を行う。試合開始1時間30分を経過した場合は、コールドゲームが適用される。同点の場合は、タイブレーク方式で試合を決する。
- 日没まで短時間しかない場合でも、試合を開始することがある。審判員は、あらかじめ両チームの監督にどの回で打ち切りになっても特別継続試合を行うことを条件に、試合をできるところまで行う旨を申し渡してから試合を開始する。
- 特別継続試合の再開
- もとの試合が中断された個所から再開する。
- 両チームの出場者と打撃順は、試合が中断されたときと全く同一でなければならない。ただし、規則によって認められる交代は許される。なお、もとの試合前に提出された打順表に記載されていない者は、出場できない。
- もとの中断された試合に出場して、他のプレーヤーと交代してその試合から退いたプレーヤーは、再開される試合に出場できない。
- 中断、再開の際は、試合の終了および開始と同じように挨拶をする。
- グラウンドを変えて再開するとき、および翌日特別継続試合として行う場合は、原則としてシートノックを行う。
- 特別継続試合は、全ての事項についてもとの試合を引き継ぐ。(試合時間、投球数、タイムの回数制限、警告回数等)
5 抗議権を有する者
監督か当該プレーヤーのいずれか1名とする。
6 監督に限り、グラウンドに出て指示することができる。
7 学童部の投球数制限について
選手の肘、肩の障害予防として、一人の投手が1日に投球できる数は下記の取り扱いとする。この投球数制限は、選手が安全に安心して健康で野球を楽しむことを目的としている。
【学童部(女子共)】
- 1試合かつ1日の投球数は70球以内。なお、4年生以下が投手として出場した場合の投球制限は学年で判断する。(4年生以下は60球以内)
- 特別継続試合で投球できる球数は、もとの試合で投じた球数を引き継ぎ、残りの球数だけとする。
- 特別継続試合に勝利したチームの投手は、同日に行われる試合において1日の投球制限を超えない範囲で登板できる。
【投球数管理運用】
- 試合中規定投球数に達した場合、その打者の打撃中に攻守交代となるか、打撃を完了するまで投球できる。
- ボークにもかかわらず投球したものは、投球数に数える。
- タイブレークになった場合、1日の規定投球数以内で投球できる。
- けん制球や送球とみなされるものは投球数としない。
- 投球数の管理は、大会本部が行う。
8 試合をナイターで実施する場合は、その終了時刻を原則として20時までとする。
9 試合時間の管理について
- 試合時間は大会本部が管理し、試合開始時間を通告すること。
- 制限時間に達した時は、審判はそのことを両チームに通告すること。
- 特別継続試合の試合時間については、もとの試合の残り時間のみ行うものとする。
- 試合時間が短い学童部(女子共)の試合においては、プレーヤー、監督、コーチ、審判員の負傷手当のための遅延は試合時間に算入しない。(野球規則9.02(l)【原注】は適用しない)。
【ケース1】
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| A | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
| B | 3 | 2 | 1 | 6 |
- 〔Aがリードの4回表に1時間30分が経過した場合〕
- ※4回裏の攻撃まで行う。
【ケース2】
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| B | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
〔Bがリードの5回裏のB攻撃中に1時間30分が経過した場合〕
※1時間30分を経過した時点で試合終了となるが、そのときの打者の打撃中にその旨を両チームに通告し、この打者の打撃を完了して試合終了とする。
10 変化球に関する事項
学童部の投手は、変化球を投げることを禁止する。関節の障害防止のため、まだ骨の未熟な学童部の投手に対して変化球を投げることを禁じ、変化球を投げた場合は次のペナルティを科すこととする。変化球を投げた場合とは、投球が審判員によって変化球と判断された場合をいう。
<ペナルティ>
- 変化球に対して〝ボール〟を宣告する。
- 投手が変化球を投げた場合は、投げないように監督および投手に厳重に注意する。注意したにもかかわらず、同一投手が同一試合で再び変化球を投げたときは、その投手を交代させる。なお、その投手は他の守備位置につくことは許されるが、大会期間中、投手として出場することはできない。
- 変化球が投げられたときにプレイが続けられた場合は、打者が一塁でアウトになるか、走者が次塁に達するまでにアウトになった場合は、プレイを無効とし、打者のカウントに〝ボール〟を加える。この場合状況によっては、攻撃側の監督の申し出があれば、プレイはそのまま有効とする。ただし、打者が安打、失策、四球、死球、その他で一塁に生き、走者が進塁するか、占有塁にとどまっている場合は、変化球とは関係なくプレイはそのまま続けられる。
◇各大会共通
§5 試合のスピード化に関する事項
- 守備側のタイムの回数制限
- 監督またはコーチ等(少年部・学童部・女子大会は監督のみ。以下同じ)が1試合に投手のもとへ行ける回数は3回以内とする。なお、延長戦(タイブレーク方式を含む)は、1イニングに1回行くことができる。ただし、投手交代の場合は回数に含まない。(5.01l(2)は適用しない)
- 捕手または内野手が、1試合に投手のもとへ行ける回数は、3回以内とする。なお、延長戦(タイブレーク方式を含む)となった場合は、1イニングに1回行くことができる。野手(捕手も含む)が投手のもとへ行った場合、そこへ監督またはコーチ等が行けば、双方1回として数える。逆の場合も同様とするが、投手交代の場合は、監督またはコーチ等の回数には含まない。
- 投手交代の場合、投手と捕手が打ち合わせ(サインの確認)のために、準備投球の前あるいは後に少しだけ会話することは、捕手または内野手の回数には含まない。
- 監督がプレーヤーとして出場している場合は、投手のもとへ行けば野手としての1度と数えるが、協議があまり長引けば、監督が投手のもとへ1度行ったこととし通告する。
- 攻撃側のタイム中に守備側は指示を与えることができるが、攻撃側のタイムより長引けば守備側の1回とカウントされる。
- 攻撃側のタイムの回数制限
- 攻撃側のタイムは、1試合に3回以内とする。なお、延長戦(タイブレーク方式を含む)は、1イニングに1回とする。
- 守備側のタイム中に攻撃側は指示を与えることができるが、守備側のタイムより長引けば攻撃側の1回とカウントされる。
- タイムは、1分以内を限度とする。
- 試合はスピーディに運ぶよう努め、1試合(9回戦)の競技時間は120分以内を目標とする。試合の進行状況によっては、タイムを制限することもある。
- 投手(救援投手を含む)の準備投球は初回に限り、8球以内が許される。次回からは、4球以内とする。なお、季節または状況により考慮する。
- 攻守交代はかけ足でスピーディに行うこと。監督、コーチが投手のもとへ往き来する場合も、小走りでスピーディに行うこと。
- 投手は、捕手、その他の内野手または審判員からボールを受け取り打者に面した後、走者がいない場合には12秒以内、走者がいる場合は20秒以内に投球しなければならない。違反した場合、走者が塁にいない場合はただちにボールを宣告し、走者がいる場合は警告を発することとし、同一投手が2度繰り返したら、3度目からはその都度ボールを宣告する。
- 投球を受けた捕手は、その場から速やかに投手に返球すること。また、捕手からの返球を受けた投手は、速やかに投手板に触れて投球姿勢をとること。
- 打者は速やかにバッタースボックスに入ること。また、バッタースボックス内でベンチ等からのサインを見ること。
- 試合中、スパイクの紐を意図的に結び直すためのタイムは認めない。
- 内野手間のボール回しは一回りとする。(状況によっては中止することもある)最後にボールを受けた野手は、定位置から速やかに投手に返球すること。
- 攻守交代時に最後のボール保持者は、投手板にボールを置いてベンチに戻ること。
- 代打者または代走者の通告は氏名とともに、「代打者」または「代走者」の背番号を球審に見せその旨を告げることとし、球審も放送席に向かって選手の背番号を見せて、「代打」または「代走」と告げること。
- 打者が二塁打を打ち、打撃用手袋から走塁用手袋に変える為にタイムをかける行為を禁止する。ただし、レッグガードとエルボーガードを外す時のタイムは認めるが速やかに行うこと。
- 投手と捕手について
無用なけん制が度を過ぎると審判員が判断したら、遅延行為として投手にボークを課すことがある。 - 打者について
- みだりにバッタースボックスをはずした時は、球審はタイムをかけずに、投球に対して、正規に〝ボール〟〝ストライク〟を宣告する。
- 打者がバッタースボックス内で打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審はストライクを宣告する。この場合はボールデッドとなり、いずれの走者も進塁できない。
- タイムについて
- 監督はタイムを要求するとき以外は、みだりにベンチを出てはならない。
- タイムは、プレーヤーの要求したときでなく、審判員が宣告したときである。打者は、投手がワインドアップを始めるか、セットポジションをとったならば、①打者は打撃姿勢をやめることは許されない。②審判員は、打者または攻撃側チームのメンバーから、いかなる要求があっても「タイム」を宣告してはならない。
- 本塁打の走者を迎える場合は、ベンチの前のみとする。
Ⅲ アマチュア野球内規
① 次回の第1打者
たとえば2アウト、打者のボールカウント1ボール2ストライク後の投球のときに、三塁走者が本盗を企てたが得点とならないで攻守交代になったような場合、次回の第1打者を明らかにするため、球審は、打者が三振でアウトになったのか、走者が触球されてアウトになったのかを明示しなければならない。(規則 5.04a(3)、5.09a(14))
② バッタースボックスルール
(1)打者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を除き、少なくとも一方の足をバッタースボックス内に置いていなければならない。この場合は、打者はバッタースボックスを離れてもよいが、〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出てはならない。
- 打者が投球に対してバットを振った場合。
- チェックスイングが塁審にリクエストされた場合。
- 打者が投球を避けてバランスを崩すか、バッタースボックスの外に出ざるを得なかった場合。
- いずれかのチームのメンバーが〝タイム〟を要求し認められた場合。
- 守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者に対するプレイを企てた場合。
- 打者がバントをするふりをした場合。
- 暴投または捕逸が発生した場合。
- 投手がボールを受け取った後マウンドの土の部分を離れた場合。
- 捕手が守備のためのシグナルを送るためキャッチャースボックスを離れた場合。
(2)打者は、次の目的で〝タイム〟が宣告されたときは、バッタースボックスおよび〝ホームプレートを囲む土の部分〟を離れることができる。
- 負傷または負傷の可能性がある場合。
- プレーヤーの交代
- いずれかのチームの協議
なお、審判員は、前の打者が塁に出るかまたはアウトになれば、速やかにバッタースボックスに入るよう次打者に促さねばならない。
ペナルティ(1)・(2)
打者が意図的にバッタースボックスを離れてプレイを遅らせ、かつ(1)の1)~9)の例外規定に該当しない場合、または、打者が意図的に〝ホームプレートを囲む土の部分〟を離れてプレイを遅らせ、かつ(2)の1)~3)の例外規定に該当しない場合、球審は、その試合で2度目までの違反に対しては警告を与え、3度目からは投手の投球を待たずにストライクを宣告する。この場合はボールデッドである。
もし打者がバッタースボックスまたは〝ホームプレートを囲む土の部分〟の外にとどまり、さらにプレイを遅延させた場合、球審は投手の投球を待たず、再びストライクを宣告する。
なお、球審は、再びストライクを宣告するまでに、打者が正しい姿勢をとるための適宜な時間を認める。(規則 5.04b(4)(A)、同(B))
③ ワインドアップポジションの投手
ワインドアップポジションをとった右投手が三塁(左投手が一塁)に踏み出して送球することは、投球動作を変更して送球したとみなされるから、ボークとなる。(規則 6.02a(1))
投手が投球動作を起こして両手を合わせた後、再び両手をふりかぶることは、投球を中断したものとみなされる。投球動作を起こしたときは、投球を完了しなければならない。(規則 5.07a(1))
④ 最終回裏の決勝点
正式試合の最終回の裏かまたは延長回の裏に、規則 6.01(g)規定のプレイで三塁走者に本塁が与えられて決勝点になる場合には、打者は一塁に進む義務はない。(規則 5.08b、6.01g)
⑤ 2アウト、四球暴投、決勝点で打者一塁へ進まず
最終回裏、走者三塁、打者の四球(フォアボール)目が暴投または捕逸となって決勝点が記録されるとき、四球の打者が一塁へ進まなかった場合は、規則5.08(b)のように球審が自ら打者のアウトを宣告して、得点を無効にすることはできない。
打者が一塁に進まないまま、守備側が何らの行為もしないで、両チームが本塁に整列すれば、四球の打者は一塁へ進んだものと記録される。
打者をアウトにするためには、両チームが本塁に整列する前に守備側がアピールすることが必要である(規則 5.09(c) [5.09c原注] [注 3])。しかし、守備側がアピールしても、打者は一塁への安全進塁権を与えられているので、打者が気づいて一塁に到達すれば、アピールは認められない。
守備側のアピールを認めて打者をアウトにする場合は、
- 打者が一塁に進もうとしないとき
- 打者が一塁に進もうとしたが途中から引き返したとき
である。(規則 5.08b、5.09c[5.09c原注] [注 3])
⑥ アウトの時機
アウトが成立する時機は、審判員が宣告したときではなくて、アウトの事実が生じたときである。第3アウトがフォースアウト以外のアウトで、そのアウトにいたるプレイ中に走者が本塁に達するときなどのように、状況によっては速やかにアウトを宣告しなければならない。(規則 5.08a[注 1])
⑦ アピールの場所と時期
守備側チームは、アピールの原因となった塁(空過またはリタッチの失敗)に触球するだけでなく、アピールの原因でない塁に進んでいる走者の身体に触球して、走者の違反を指摘して、審判員の承認を求める(アピール)ことができる。この場合、アピールを受けた審判員は、そのアピールの原因となった塁の審判員に裁定を一任しなければならない。
アピールは、ボールインプレイのときに行わなければならないので、ボールデッドのときにアピールがあった場合は、当該審判員は「タイム中だ」ということとする。(規則 5.09c)
ただし、最終回の裏ボールデッド中に決勝点が記録された場合、または降雨等で試合が中断され、そのまま試合が再開されない場合、ボールデッド中でもアピールはできるものとする。
⑧ 審判員がインプレイのとき使用球を受け取る
3アウトと勘ちがいした守備側が、使用球を審判員に手渡したのを審判員が受け取った場合は、規則 6.01(d)を準用する。審判員が使用球を受け取ると同時にボールデッドとし、受け取らなかったらどのような状態になったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。また、ベースコーチが同様のケースで試合球を受け取った場合も、受け取ると同時にボールデッドとするが、走者はボールデッドになったときに占有していた塁にとどめる。(規則 6.01d)
⑨ 打者の背後にウェストボールを投げる
投手がスクイズプレイを防ぐ目的で、意識的に打者の背後へ投球したり、捕手が意識的に打者の背後に飛び出したところへ投球したりするような非スポーツマン的な行為に対しても規則 6.01(g)を適用し、走者には本塁を与え、打者は打撃妨害で一塁へ進ませる。(規則 6.01g)
⑩ 危険防止(ラフプレイ禁止)ルール
本規則の趣旨は、フェアプレイの精神に則り、プレーヤーの安全を確保するため、攻撃側および守備側のプレーヤーが意図的に相手に対して体当たりあるいは乱暴に接触するなどの行為を禁止するものである。
1.タッグプレイのとき、野手がボールを明らかに保持している場合、走者は(たとえ走路上であっても)野手を避ける、あるいは減速するなどして野手との接触を回避しなければならない。
- 野手との接触が避けられた
- 走者は野手の落球を誘おうとしていた
- 野手の落球を誘うため乱暴に接触した
と審判員が判断すれば、その行為は故意とみなされ、たとえ野手がその接触によって落球しても、走者にはアウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。なお、走者の行為が極めて悪質な場合は、走者は試合から除かれる場合もある。(規則 6.01i(1))
2.次の場合には、たとえ身体の一部が塁に向かっていたとしても、走者には妨害が宣告される。
- 走者が、ベースパスから外れて野手に向かって滑ったり、または走ったりして野手の守備を妨げた場合(接触したかどうかを問わない)。
《走者は、まっすぐベースに向かって滑らなければならない、つまり走者の身体全体(足、脚、腰および腕)が塁間の走者の走路(ベースパス)内に留まることが必要である。ただし、走者が、野手から離れる方向へ滑ったり、走ったりすることが、野手との接触または野手のプレイの妨げになることを避けるためであれば、それは許される。》 - 走者が体を野手にぶつけたりして、野手の守備を妨害した場合。
- 走者のスライディングの足が、立っている野手の膝より上に接触した場合および走者がスパイクの刃を立てて野手に向かってスライディングした場合。
- 走者がいずれかの足で野手を払うか、蹴った場合。
- たとえ野手がプレイを完成させるための送球を企てていなくても、走者がイリーガリーに野手に向かってスライドしたり、接触したりした場合。
ペナルティ(1)~(5)
- フォースプレイのときの0 アウトまたは1アウトの場合、妨害した走者と、打者走者にアウトが宣告される。すでにアウトになった走者が妨害した場合は、守備側がプレイを試みようとしている走者にアウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。
- フォースプレイのときの2アウトの場合、妨害をした走者にアウトが宣告され、ただちにボールデッドとなり、他の走者は進塁できない。
- タッグプレイの場合、妨害をした走者にアウトが宣告され、ただちにボールデッドとなり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。
- 走者のスライディングが極めて悪質な場合は、走者は試合から除かれる場合もある。(規則 5.09b(3)、6.01i(1)、6.01j)
3.タッグプレイのとき、捕手または野手が、明らかにボールを持たずに塁線上および塁上に位置して、走者の走路をふさいだ場合は、オブストラクションが厳格に適用される。
なお、捕手または野手が、たとえボールを保持していても、故意に足を塁線上または塁上に置いたり、または脚を横倒しにするなどして塁線上または塁上に置いたりして、走者の走路をふさぐ行為は、大変危険な行為であるから禁止する。同様の行為で送球を待つことも禁止する。このような行為が繰り返されたら、その選手は試合から除かれる場合もある。
ペナルティ
捕手または野手がボールを保持していて、上記の行為で走者の走路をふさいだ場合、正規にタッグされればその走者はアウトになるが、審判員は捕手または野手に警告を発する。走者が故意または意図的に乱暴に捕手または野手に接触し、そのためたとえ捕手または野手が落球しても、その走者にはアウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。(規則 6.01h、6.01i(2))
⑪ 投手の遅延行為
走者が塁にいるとき、投手が投手板から軸足をはずして、走者のいない塁に送球した(送球するマネも含む)場合、または、投手板上からでも軸足を投手板からはずしても、塁に入ろうとしていない野手に送球した場合には、投手の遅延行為とみなす。(規則 6.02a(4)、6.02a(8)、6.02c(8))
⑫ 投球する手を口または唇につける
規則 6.02(c)(1)のペナルティに代えて、審判員はその都度警告してボールを交換させる。(規則 6.02c)
⑬ 正式試合となる回数
審判員が試合の途中で打ち切りを命じたときに正式試合となる回数については、規則 7.01(d)に規定されているが、各種大会などでは、この規定の適用に関して独自の特別規則を設けることができる。
大会によっては、一定以上の得点差、たとえば、5回10点差、7回以降7点差など、得点差によってコールドゲームとし、正式試合とする特別規則もある。(規則 7.01d)
Ⅳ 質疑応答
Ⅴ 索引
Ⅵ 審判員のために
1、一般心得
公認野球規則8.00『審判員に対する一般指示』は、審判員として心得ておかなければならないことを詳しく述べている。これを熟読したうえで、次のことがらも参考にされたい。
- 規則書と競技者必携に精通すること。
よき審判員は規則書に明るい。規則に通じることは、大きな自信にもつながり信頼も増す。また規則書と競技者必携は審判員の最大の味方でもある。いつでも規則書と競技者必携を携行すること。 - 審判員の連帯責任
一人の審判員の失敗は、当該審判員全員の共同責任である。常に連係動作に習熟し、万一他の審判員が持ち場にいなかったら、互いに助け合って必ずその穴を埋めなければならない。 - ゲームのスピードアップに努めること
判定に不信を抱かせたりトラブルが多いと、ゲームは長引いて審判員の存在も目立ってくる。スムーズに試合を運ぶ審判員は、上手な審判員だといえる。
審判員は規則に忠実でなければならない。規則に忠実なことは審判員として厳格であり、公平でもあるということばかりでなく、ゲームに活気を与えることになる。活気のあふれたゲームこそ魅力があるのだ。無用な〝タイム〟も大きな障害である。攻守交代はかけ足を実行させよ。ゲームの前半、特に3回ごろまでは遅れがちであるからスピーディに進めるように努めること。 - 勇敢でそして公平であること
審判員は大勢の人の前で、瞬間的な出来事に対して、即座に裁定を下さなければならない。常に見たままを的確に裁定するだけでよい。審判員は邪念を持たず、常に公平でなければならない。 - 立派な社会人でなければならない。
球場の内と外とを問わず、マナーに注意し、かりそめにも他から非難を受けるようなことがあってはならない。あらゆる点でいつも模範となるよう心がけることが必要である。 - 健康に留意すること
審判員は精神的にも肉体的にも健康でなければならない。特に、審判員は長時間肉体と精神を酷使し続けなければならないからである。寝不足などは禁物である。ゲーム前は余分な湯水を飲まないようにするとか、用便を済ませておくなど、ちょっとした注意が大切である。 - 服装は端正に
決して新しい物でなくても、良く磨かれた靴、クリーニングされたシャツ、プレスされたズボンの着用を心がけることが、おのずから信頼と尊敬につながるものである。 - 審判用具の点検
常に点検を怠ってはならない。用具を軽快に使用できるように習熟することが大切である。
2、判定に関する心得
- 常にボールから目を離してはならない。
- 選手の邪魔にならないよい位置を占め、プレイに対し最も適切な角度と距離をとるようにする。
- 判定を下す前は止まってプレイを注視せよ。走りながら判定をしてはならない。
- プレイの裁定を早まらず、プレイが完了するまで待つ。特にアウトの判定を下す場合は確保の確認が必要である。
- きわどいプレイの裁定は、ジェスチャー、コールとも大きく強調すること。
- 常にどんなプレイにも対応できる心構えと態勢を維持すること。
- もし、判定の一つに失敗しても、次の判定は正確に行え。埋め合わせは決してするな。埋め合わせは、失敗をもう一度やるより悪い。
- 他の審判員が「タイム」を宣告すれば必ず同調する。ただし、「ボーク」の場合は、プレイの成り行きを見極めた後に同調することもある。
- トラブルが起きた場合は、まず抗議者の資格を確認せよ。そして「必要なことだけを聞き、必要なことだけを答える」、これがトラブル解決の秘訣である。なお、抗議に対して審判員が協議によって得た最終結論は、再抗議があってもいたずらに変更すべきではない。
3、任務
試合は通常三人または四人の審判員によって行われるが、ときには二人または六人の審判員によって行われる場合もある。一人が球審でその他は塁審あるいは外審と呼ばれ、異なった位置を占めそれぞれの任務を持っている。
1 球審
投球の判定にあたっては、インサイドプロテクターを使用する場合は、打者と捕手の間から見極める。アウトサイドプロテクターを使用する場合は、ホームプレートの後方中央で捕手の真上から見極める。いずれの場合も、判定が終るまで身体を動かしてはならない。
フォースプレイの場合は、捕球と走者の関係がよく見える位置(角度)で裁定を行い、タッグプレイの場合は、プレイの妨げにならない範囲で近づき、プレイが最も見易い位置で裁定を行う。
いずれの場合も、余裕をもって動き、停止をして裁定を行う。
一・三塁線近くの打球に対しては、すばやく前に出てラインをキープして判定する。この場合判定が早すぎないように注意しなければならない。
また、プロテクターの操作やマスクの脱着に習熟することが、素早い行動につながり任務を遂行するために必要なことである。
任務は次の通りである
- 試合を適正に運行するためのすべての権限と責任を持つ。
- 「ボール」「ストライク」をコールし、それをカウントする。
- 塁審が宣告する以外のフェアボールのポイントとファウルの宣告をする。
- 打者についてのすべての裁定をする。
- 通常塁審が行うことになっているもの以外のすべての裁定をする。
- フォーフィッテッドゲーム(没収試合)の裁定をする。
- 試合前に本部で確認された打順表を受け取る。なお試合中、出場プレーヤーに変更があれば発表する。
- 特別グラウンドルールの必要なときはそれを発表する。
- 特別継続試合に入る場合はそれを発表する。
2 塁審
一・三塁の塁審は一・三塁ファウルラインの外側、二塁塁審は一・二塁または二・三塁の延長線方向に位置し、打球、送球に対して速やかに適切な位置をとる。塁審の位置や動きは人数によって異なってくるので、審判メカニクスを参照し、習熟することが大切である。
フォースプレイ、タッグプレイの裁定は、球審と同じ要領で行う。
「タイム」「ボーク」を宣告するときは、特別な場合を除き、全員が一致した宣告をしなければならない。
任務は次の通りである
- それぞれの分担する塁におけるプレイを裁定する。
- 「タイム」「ボーク」等の裁定については、球審同じ権限を持つ。
- 規則を適用して、規律を維持することについては球審と同じであり、試合の運行についてはあらゆる方法で球審を援助しなければならない。
審判員に関する取り決め事項
一、審判員の服装
審判員にふさわしい服装とし、各都道府県支部において統一する。
マスク等の装具は、連盟公認のものを使用する。
オフィシャルマークの帽子、公認審判員ワッペンを着用のこと。
二、球場への到着から試合終了まで
- 審判員は、試合開始予定時刻より、少なくとも1時間前までに球場に到着する。
- 天候、球場の状態が試合を開始するのに適しているのかどうかを、球場責任者と打ち合わせて大会本部に報告して指示を受ける。
- 場内の点検、設置器具、各ラインなどの点検をする。
- 試合開始前に担当審判員(控え審判員を含む)は相互のコミュニケーションを深めるために、打ち合わせや決まりごと等の確認を行う。試合終了後には、必ずその試合の反省を行う。
- 球審立会いのもとに、両チームの監督または主将により攻守の決定を行い、打順表の交換が終わったのち、監督または主将がベンチに戻り次第、後攻チームよりシートノックを行うよう指示する。
- 担当審判員は、シートノック中に両チームの用具・装具を点検する。
- 連盟公認でない違反の用具・装具があれば取り除き、大会本部に預ける。
- 違反の装具があれば、改めるよう指導する。
- 球審は5回終了時に使用球を新しいボールと交換する。なお、審判員は季節によっては、随時水分を補給する。
- 暗黒、降雨その他の事情で試合を中止するなど大会の運営に関係ある事柄については、当該審判員が大会本部と協議をして決定する。
三、控え審判員
連盟主催大会では、控え審判員を採用する。
- アマチュア野球では、提訴試合が認められない。したがって審判員の規則適用の誤りや、その他監督などの抗議を直ちに解決するため、控え審判員を置く。(7.04)
- 控え審判員は2名とし、内1名はアウトカウント、ボールカウントを常に確認し、このことについて責任を持つ。なお、その他の事項についても、他の1名と同様の責任を持つ。
- カウントの明らかな間違いについては、控え審判員が訂正させる。
- 当該審判員が裁定に苦しむときには、控え審判員と協議することができる。
- 規則適用の明らかな間違いについては、控え審判員がその誤りを訂正させることができる。
- 大会に派遣されている技術委員、および審判技術指導員は、控え審判員としての資格を有するものとする。
審判上の取り決め事項ならびに注意すべき規則
1、宣告の取り決め
- ファウルライン付近を転がる打球は、一・三塁ベースまでは球審、一・三塁ベースを含む以遠のものは塁審が宣告する。
- ファウルの宣告は、身体の向きは特に規制しないが、フェア地域の方を向いてはいけない。
- 投球が打者に触れたが死球としない場合、両手を上げてボールデッドであることを示し、「ボール」または「ストライク」と宣告する。
- スクイズプレイまたは本盗の場合、投手の投球を捕手が本塁上に出るか、あるいはバットまたは打者に触れてボークと打撃妨害の規則が適用される場合は、「タイム」を宣告後、「打撃妨害」を宣告して三塁走者の進塁(得点)を認め、続いて打者を一塁に進める。他の走者も「ボーク」によって1個の進塁を認める。
- 打球、送球等に野手がグラブを投げて故意に触れさせるか、帽子・マスクその他着衣の一部を、本来着けている個所から離して故意に触れさせた場合
- フェアの打球に対しては「テイク・スリー」と宣告して3本の指で示す。
- 送球(投手板上からの送球も含む)に対しては「テイク・ツー」と宣告して2本の指で示す。
- 投球に対しては「テイク・ワン」と宣告して1本の指で示す。
【注】いずれの場合もボールインプレイであり、走者の進塁の起点は、野手の投げたグラブ等が打球または送球に触れた瞬間である。
2、本・一塁間に設けられてあるスリーフットレーン内を、打者走者が走っているかどうかは球審が見る。(ライン上はスリーフットレーン内に含まれる)
したがって、一塁への守備が行われているとき、スリーフットレーン外を走り、守備を妨害した場合に、「ヒー・イズ・アウト」を宣告するのは球審である。
3、アピールプレイ
- 塁を空過するか飛球が捕えられたとき、リタッチを果たさず進塁した走者に対して、元の塁だけでなく進塁した塁上で触球してアピールすることも認められる。
- ボールインプレイ中にアピールがあり、このアピールに対して、審判員が「タイム」を宣告して協議しなければならない場合は、ボールデッド中に協議結果を宣告する。
- アピールプレイは、ボールインプレイのときに行わなければならないから、タイムを要求してアピールをしようとしたときは、審判員は「タイム」を宣告してはならない。しかし、審判員が「タイム」を宣告した場合には、ボールインプレイにしてから改めてアピールをさせることとする。
4、キャッチ(捕球)
併殺プレイのとき、ピボットマンはすばやい送球動作を行うので、落球か否かの判定については、野手が捕球後、ボールがそのプレーヤーの「投げ手」に移り、送球動作に移ったことが明らかなときは「キャッチ」と判定される。
しかし、投げ手に移されようとする状態とか、あるいは、投げ手に移ったばかりで、まだ送球動作に入っていないときは、「キャッチ」とはみなされない。
【注】「ピボットマン」とは、併殺の際、ボールを継送するプレーヤーである。たとえば遊撃手-二塁手-一塁手とわたる併殺ならば二塁手を指す。
5、ヒット・バイ・ピッチ(死球)の判定
打者が投球を避けようとすることが条件である。しかし、投球がストライクゾーンで打者に触れた場合には、避けようとしたかどうかを問わずすべて「ストライク」である。
6、打球が再びバットに当たった場合
- バッタースボックス内で当たったときはファウルボールである。
- バッタースボックス外(フェア地域)で当たったときは、打者をアウトにする。ただし、バッタースボックス外で当たったときでも、打者の両足がまだバッタースボックス内に残っているときはファウルボールである。
- フェア地域で、落としていったバットに打球が転がってきて当たったときは、ボールインプレイである。
- 投げたバットが打球に当たったときは、バッターはアウトになり、ボールデッドとなる。
- 折れたバットの先の部分が、打球に当たったときは、ボールインプレイである。
7、故意落球
容易に捕球できるはずのフライまたはライナーを、内野手および外野手が内野近くまで来て、片手または両手で現実に打球に触れてから、併殺を企てるため故意に落としたものが故意落球であり、ボールデッドとなる。しかし、手またはグラブに触れないで落としたものは故意落球とはならず、ボールインプレイである。
8、ハーフスイングの判定
球審が下したハーフスイングの判定には抗議はできないが、「ボール」と宣告したときだけ、監督または捕手は、振ったか否かについて塁審にアドバイスを受けるよう、球審に要請することができる。
なお、バントはスイングではないから、ハーフスイングについての要請は受けられない。ただし、捕手の陰で打者の行為が判然としないようなときは、球審は独自の判断で塁審にアドバイスを求めることができる。
9、走者が盗塁を企てたとき、捕手の送球動作を妨害した場合
- 打者の妨害
打者はいかなる形であろうとも走者を助けようとする行為をしてはならない。- 現実に捕手の送球動作が妨害されたときに限る。
- をアウトとし、走者を元の塁に戻す。
- 妨害にもかかわらず捕手が送球できて、走者をアウトにしたときは打者はアウトにならず、妨害はなかったこととする。
- 妨害にもかかわらず送球することができて、走者をアウトにできるタイミングであっても、野手が落球して走者をアウトにすることができなかったときは、妨害として処置する。
- 捕手からの送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員は直ちに「タイム」を宣告して、打者を妨害によるアウトにし、走者を元の塁に戻す。(6.03a(3)、【注2】)
- 球審の妨害(打球処理を除く、捕手のすべての送球動作)
- 捕手の送球で走者をアウトにしたときは妨害とはならない。なお、捕手からの送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、球審は直ちに「タイム」を宣告して走者を元の塁に戻す。(5.06c(2)【付記】、【注】)
- 第3ストライクを捕手が捕球できなかったときの捕手の守備行為を妨害したときも、球審は直ちに「タイム」を宣告して打者をアウトにし、走者を元の塁に戻す(5.06c(2))。なお、投手への返球行為を妨害したときも含まれる。
10、打者が反則打球をした場合
打者が反則打球をした場合は、打者はアウトとなる。なお、走者がいる場合はボールデッドとなって投球当時に占有していた塁に戻す。(6.03a、5.06c(4))
11、ダブルプレイが故意の妨害により阻止された場合
- 走者による場合
妨害した走者とともに打者もアウトにする。- ピボットマンの守備を故意に妨害したとき(5.09a(13)、5.09b(3))
- 打球の進路を故意に変えたり、捕ったりして打球を妨げるか、打球を処理しようとしている野手の守備を故意に妨害したとき(6.01a(6))
- 打者走者による場合
どこで併殺が行われようとしていたかに関係なく、その打者走者と本塁に最も近い走者をアウトにする。(6.01a(7)) - アウトになった打者または走者、あるいは得点したばかりの走者による場合
併殺の対象となった走者をアウトにする。どの走者に対して守備が行われようとしていたか判断しにくいときは、本塁に最も近い走者をアウトにする。(5.09a(13)、6.01a(5)【注】)
12、同一塁上で二人の走者にタッグした場合
- ボールインプレイのとき、二人の走者が同一塁に触れているときは、その塁の占有権は前位の走者にある(5.06a(2))。したがって、二人の走者にタッグしたときは後位の走者を指さして「ヒー・イズ・アウト」を宣告し取り除く。ただし、(6.01h(2))適用の場合を除く。
- フォースの状態で進塁を余儀なくされた走者が元の塁に触れたままの場合は、その塁の占有権は後位の走者にあるから、二人の走者がその塁上にいてタッグされたときは前位の走者がアウトになる。(5.06b(2))
13、走者が一塁におり、打者走者を先にアウトにした場合
打者走者が先にアウトになれば、一塁走者は塁を明け渡す(進塁)義務は無くなるから、帰塁も進塁も自由である。このようなときには、審判員は特に一塁手が先に走者にタッグしたか、ベースに触れたかを確認することを怠ってはならない。先に一塁走者にタッグしてから、次に一塁ベースに触れれば二つのアウトが成立する。(5.09b(6))
14、悪送球が場外に出た場合の進塁の基準
悪送球が場外に出た瞬間にボールデッドとなるが、そのときの走者の位置が進塁の基準ではない。(5.06b(4)(G))
- 打球処理直後の内野手の最初のプレイに基づく送球(ファーストスロー)が悪送球のときは、投手の投球当時の各走者の位置を基準として2個の塁が与えられる。(打者を含む各走者が1個の塁を進んだ後に送球したものを除く)(5.06b(4)(G)規則説明)
- その他の送球のときは、常にその悪送球が野手の手を離れたときの走者の位置を基準として、2個の塁が与えられる。ただし、フライが捕球された後に続く悪送球の場合に限って、投手の投球当時、その走者が占有していた塁を基準として2個の塁が与えられる。このとき、捕球より離塁の早かった走者は次の塁に達しなければ、ボールデッドの状態であってもリタッチを果たすことは許される。もし、リタッチを果たさないときは、プレイ再開後にアピールがあればアウトになる。(5.06b(4)(I)【原注2】、5.09c(2)規則説明(B)、【注4】)
15、正しい投球姿勢の徹底(5.07a(1)、(2))
- 投手がセットポジションに入るとき、一塁へ左肩(右投げ)を大きく振って「偽投と見間違えられる極端なものに限定」それから向き直ってストレッチに入る入らないに関係なく、偽投と類似の動作をした場合。(ボークとなる)
- 二塁に走者がいるとき、投手が二塁に顔を強く振りながら「自由な脚および両手が伴いあまりにも不自然な投球動作」をした場合。(ボークとなる)
- 打者への投球動作を起こしたならば、中断したり、変更したりしないで、その投球を完了しなければならない。“中断”とは、投手が投球動作を起こしてから途中でやめてしまったり、投球動作を一時停止したりすることであり、“変更”とは、ワインドアップポジションからセットポジション(または、その逆)に移行したり、投球動作から塁への送球(けん制)動作に変更することである。
- セットポジションから投球する投手は、投球するまでに必ずボールを両手で保持したことを明らかにしなければならない。その保持に際しては身体の前面ならどこで保持してもよいが、打者あるいは走者の位置によってその保持する箇所を変えることは欺瞞行為にあたる。したがって、同一投手は、1試合を通して同じ位置でボールを保持しなければならない。(注意指導)
16、ホームスチールとピッチドボール(投球)の判定
16、ホームスチールとピッチドボール(投球)の判定
決してあわててはいけない。まず投球の判定を宣告し、次に本塁でのプレイを、「アウト」か「セーフ」のジェスチャー、コールで示す。それから、改めて記録員に、今の投球は「ボール」か「ストライク」であったかを通告する。
17、ランダウンプレイ中に野手の際どいタッグプレイがあり、実際にはタッグが無かったときは、審判員は「ノータッグ」と宣告し、セーフと同じジェスチャーで示す。(5.09b関連)
18、タイムを宣告する時期
プレーヤーは、投手がワインドアップを始めるかセットポジションをとったとき、プレイが始まろうとしているとき、またはプレイが行なわれているときには「タイム」を要求できない。したがって、審判員はこのような要求があっても「タイム」を宣告してはならない。(5.12b(8)、5.04b(2)【原注】)
しかし、プレーヤーは往々にして時期をわきまえず「タイム」を要求することがある。このようなとき、審判員はとっさに「タイム」をかけるべきか否かを判断して処置しなければならない。この判断と処置は審判員にとって極めて大切な審判技術の一つである。
なお「タイム」が発効するのは、「タイム」が要求されたときでなく、審判員が「タイム」を宣告した瞬間からである。(5.12a、5.12b)
19、雨の中で試合を開始する場合、または、暗黒、降雨等で試合を中止する場合
試合の開始、中止、再開については、当該審判員が大会本部と協議のうえ決定するよう取り決められている。なお、日没時は少し早めに打ち切るのがよい。もう1回できそうだと思えるときが打ち切り時である。
審判員の構え、判定と宣告、ジェスチャー
審判員は、すべてのプレイを見たままに正確に判定して、宣告する義務があります。そのためにも、以下に記載されている諸事項と併せて、プロアマを問わず、我が国統一の審判マニュアルとして、全日本野球会議審判技術委員会から、基本のジェスチャー及び基本のメカニクスを、冊子にまとめた「審判メカニクス・ハンドブック」が発行されておりますので、審判技術の確立に活用されるよう、お願いいたします。
集合と挨拶
- ユニフォームを着た両チームの全員が、それぞれ自軍のベンチ前に整列して、集合の合図を待つ。
- 審判員は試合開始予定時刻の5分前に、両チームに集合を呼び掛け、本塁方向に向かう。
- 審判員は捕手席の後方に、本塁を中心とした横1列(右から一塁塁審、球審、二塁塁審、三塁塁審の順)に並ぶ。なお、外審がつく場合は、その左右に並ぶ。
- 両チームの選手は、打者席の外側に監督(少年、学童は主将)を先頭にして、向かい合って1列に整列する。
- 両チームの監督(少年、学童は主将)に握手させる。
- 球審の合図により全員脱帽して、相互に礼を交わす。
- 守備側チームは、その場から守備位置に向かう。
試合の開始
球審は投手の準備投球が終了したら、マスクを着け、捕手の後方に位置する。
○宣告用語「プレイ」
○宣告
球審は、塁審(外審を含む)及びプレーヤーが所定の位置についているかを確認し、オンザラバーのスタンスを取り、投手が正規に投手板に位置したら右手を伸ばして「プレイ」と宣言する。
球審の構え(スロット・ポジション(スロット・スタンス))
リラックスしているときは、身体の中心を打者のインサイド側ホームプレートのエッジに置くようにする。
構えるときは、まず打者側の足(スロットフット)を移動して爪先を投手の方向に向ける。
この際、爪先を打者側の捕手の踵の線と平行にする。次に反対側の足(トレルフット)を肩幅よりやや広め(両足のスタンスは自分の1番楽な位置)に開き、打者側の足の踵の線に爪先がくるようにする。(爪先は45度まで開いてもよい)
投手に正対して、ホームプレートのインサイドの線に身体の中心がくるようにし、やや前傾姿勢で、捕手の頭の上部から、やや高めに顎が位置するように構える。
構えたときの腕と手は、打者側の腕は90度に曲げてベルトのあたりに止め、片方の腕は、膝の上部あたりに軽く添えるか、両腕を足の内側に入れて太ももあたりに置き、手は自然に下げるか軽く握る。
「構え」たときから「宣告」まで、投手に正対していなければならない。
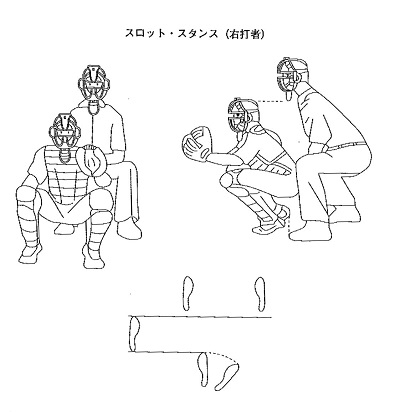
マスクの外し方
マスクを外すときはインジケータを左手薬指と小指の二本で持って他の指三本(親指、人差し指、中指)でマスクの左側の下部を握り、前に引いてから押し上げるようにする。
打球から目を離さないようにするため、マスクを外すときに下を向かないよう注意する。
投球の判定
投手が投げてから捕手が捕るまでボールを目で追い、投球を判定することを「トラッキング」という。投球を正確に判定するための大事な作業である。投球がミットに入ってからコールする。
1、ストライク
○宣告用語「ストライク・ワン」「ストライク・ツー」「ストライク・スリー」
○宣告
ゲット・セットの姿勢でトラッキングを終えたら、一連の動作で立ち上がりながら、コールする。
2、ボール
○宣告用語「ボール・ワン」「ボール・ツー」「ボール・スリー」「ボール・フォー」
○宣告
ゲット・セットの姿勢のまま、ボール(捕手のミット)から目を離さず、顔を動かさないでコールする。
打者が四球に気がつかなかったときは、声で一塁に進むことを促す。(左手で一塁を指さすジェスチャーはしない)
3、ボールカウントの表示
両手を頭のあたりまで上げ、左手の指で「ボール」の数を、右手の指で「ストライク」の数を示す。
はじめに「ボール」の数を、次に「ストライク」の数をコールする。
4、申告敬遠
守備側の監督がタイムを要求し、打者を申告敬遠する意思を球審に示した場合はボールデッドとし、タイムのジェスチャーを行い、打者に対して一塁への進塁の指示を行う。二人の打者を連続して行う場合は、一人目の打者が一塁に達した後、二人目の申告を受ける。
5、振り逃げの際のジェスチャー
下記①②いずれの手法も用いることができる。
- 振り逃げの状態になった時は右手を横(上ではない)にポイントを出し、一塁塁審に分かるようにしばらくそのままの状態にする。捕手がタッグできなかった場合は、両手を広げながら「ノータッグ」と発声する。
- 打者の空振りした投球を捕手がショートバウンドで捕った場合、またはストライクの投球(打者は振らずに見逃した)を捕手が確捕できなかった場合など、上記のジェスチャーに続いて、セーフのジェスチャーをしながら「ノーキャッチ」“No catch!”と発声する。
那覇ブロックルール
大会要項(その他)
- 背番号は、監督30番、コーチ29番・28番、主将は10番とし、選手は0番から99番とする。
- ベンチ入り出来る成人は、①引率責任者(チーム代表)、②監督30,③コーチ29、④コーチ28、⑤スコアラー、⑥マネージャーの最大6名で、大会申込書に登録された者とする(代理者のベンチ入りは認めない) ※半ズボン・無帽は認めない。
夏場に限り選手の体調管理を目的に、保護者(母親)2名のベンチ入りを認める。 - ベンチ入りの大人(監督、コーチ含む)のサングラス着用を認める。但し、ミラーレンズ等の派手なものは除く。試合開始、終了の礼の時、試合中グラウンドに入る際は外す。
- 試合中打者、走者、次打者、ベースコーチは連盟公認の両耳付ヘルメット、捕手は連盟公認マスク(SGマーク付)、スロートガード、プロテクター、レガース、捕手用ヘルメット、ファウルカップを着用しなければならない。金属、ハイコンバットは連盟公認(JSBB)マーク入りを使用すること。
- 全日本軟式野球連盟公認マーク(JSBB)が完全に消えた用具は使用できない。
- バットリング、トレーニングバット、スプレー(滑り止め)の使用を禁止する。(但し、マスコットバットを使用しての素振りは可)
- 参加申込後は、選手の追加、変更および背番号の訂正も認めない。
- 判定に対するアピールは、基本的に監督だけが行えるが、走者の走塁に関するアピールは、野手でも行うことができる。
- 判定に対する異議や抗議は受け付けない。但し審判員の裁定がルールの適用を誤っていると疑われるとき、監督は裁定への質問や訂正を申し出るアピールをすることが許される。
- 予め最新版競技者必携、特に学童部に関する事項を熟読しておくこと。
- 6回を終了した時点、または制限時間を過ぎた時点で同点の場合はタイブレーク方式(2回)を行う。決着がつかない場合は抽選で勝敗を決定する。
決勝戦でも同様。 - 投手の投球制限については、肘・肩の障害防止を考慮し、1人の投手は1日70球以内を投球できる。試合中に70球に達した場合、その打者が打撃を完了するまで投球できる。ダブルヘッダーの場合、最初の試合で投手として投球した投手は、残り投球数以内で投球することができる。(投球時のボークはBSOカウントされないが、投球を行った場合、投球はカウントされる。(投球を行わなかった場合、投球はカウントされない)
- 4年生以下の投手に関しては、1人の投手は1日60球以内とする。
- ファウルカップは、試合に出場する捕手、控え捕手いずれも必ず着用すること。
- ベンチ前で投球練習を行う際、捕手は必ず防具(ヘルメット、マスク、プロテクター、レガース)を着用すること。着用していない場合は、捕手は座らず立ったまま投球を受けること。試合中、試合前も同様。
また、試合開始前に限り捕手を監督、コーチが行うことを認めるが、その際も必ずヘルメットとマスクを着用すること。 - コールドゲームになる回数は、3回以降10点差、5回以降7点差とする。
※決勝戦も適用。 - 日没降雨コールドの場合、原則として5回終了時点で試合成立とする。5回以前の中断の場合は後日継続試合とする。降雨時の待機時間は45分とするが、審判員が再開不可能と判断した場合は、時間を問わず中断することが出来る。
- フォーフィッテッドゲーム(没収試合)の扱いについては申し合わせ事項7の通り。また、抽選会及び開会式に遅刻や無断欠席の場合は出場を取り消す。
- 主催者は負傷、その他事故について、応急処置を除き一切の責任を負わない。
- 選手の試合前練習補助は背番号 30、29、28 着用者に限る。但し安全確保対策としての父母はその限りではない。
- 安全対策のため、ボールボーイ・バット引きの選手も、試合に出る選手同様ヘルメットを着用すること。
確認事項
- 序
- 本確認事項は、沖縄県野球連盟那覇支部学童部那覇ブロック(以下、「那覇ブロック」という)が主催する大会において、公認野球規則や競技者必携に明記されていないプレイに対するジャッジ・解釈、運営上の支障を取り除くための処置、その他をまとめたものです。
- 那覇ブロック審判部長および副部長、那覇ブロックに所属する4地区(小禄・首里・那覇・真和志)の審判部長によって構成される那覇審判部長会によって策定され、那覇ブロック役員会の承認を経て成立されています。
- なお、本確認事項 の適用にあたっては他のブロック・支部で取り扱いが異なる場合がありますので、その点お含みおき願います。
- 図説一覧
- 野球競技区画線(学童部)
- 投手のマウンドの区画線は引かないものとする(必携 Ⅰ図説一覧 野球競技場区画線 改)
- 区画線は 7.6cm幅 ではなく 5cm幅 とする(必携 Ⅰ図説一覧 野球競技場区画線 改)
- 野球競技区画線(学童部)
- 審判員・選手への注意事項
- 大会に参加するチーム・審判員の注意事項
- 開会式について
- 開会式には、登録原簿に記載された全員が参加することとする。ただし、疾病、負傷、その他の理由で当日の試合に出場できない選手については、その限りではない(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 全国大会に参加するチーム・審判員の注意事項 開会式について 改)
- 大会審判員について
- 公式試合の審判員は、全日本軟式野球連盟に登録された審判員および各地区審判部長が推薦する審判員、各チーム監督から推薦された義務審判員が行う(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 全国大会に参加するチーム・審判員の注意事項 大会審判員について 1 改)
- 開会式について
- 競技運営に関する注意事項(学童部)
- 監督会議で説明または決められた事項は、必ずチーム全員に徹底すること(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 学童部、少年部、女子大会 §1競技運営に関する注意事項 2 再周知)
- 打順表(登録された選手全員を記入したもの)の提出は、1)その日の第1試合は開始予定時刻の40 分前までに、2)第2試合以降は前の試合の2回終了時に、大会本部に提出し、登録原簿と照合ののち、1)その日の第1試合は開始予定時刻の30分前に、2)第2試合以降は前の試合の3回終了時に、監督と主将が球審立会いのもと攻守を決定する
ダブルヘッダーの場合は、開始予定時刻の15 分前に大会本部に打順表を提出し、登録原簿と照合し、投手の球数制限を確認したのち、監督と主将が球審立会いのもと攻守を決定する(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 学童部、少年部、女子大会 §1競技運営に関する注意事項 7 改) - ベンチ内での電子機器類(スマートフォンやタブレット、ノートPC等)の使用・持ち込みを禁止する。指示用のメガホンは、ベンチ内に限り1個の使用を認める(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 学童部、少年部、女子大会 §1競技運営に関する注意事項 15 改)
- 試合の挨拶は、試合前後の本塁整列の挨拶が全てである。チームの大会本部及び相手チームへの挨拶は不要である(応援団への挨拶は奨励)。試合に敬意を表し本部役員・記録 員・控え審判員も起立し挨拶をする(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 学童部、少年部、女子大会 §1競技運営に関する注意事項 20 改)
- 試合前のウォーミングアップでグラウンドへ入ることができる大人は、選手と同様のユニフォームを着用した者(30番、29番、28番。代理は認めない)に限られる(2023年沖縄県野球連盟)
- 次の試合の記録員および義務審判員は、試合終了の5分後に大会本部へ集合する
- 競技者のマナーに関する事項
- 投手が投手板に触れて投球位置についたら、投手の動揺を誘うような大きな声を発しないこと(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 競技者のマナーに関する事項 8 再周知)
- 用具・装具に関する事項
- ベンチ入りする大人および審判員は、試合中にサングラスを使用できるものとするが 、 使用するサングラスは、選手への威圧感を感じさせにくいものとし、高校野球の使用規定を参考とする(必携 Ⅱ審判員・選手への注意事項 用具・装具に関する事項 3 改 2025 年沖縄県野球連盟)
- [高校野球の使用規定]メガネ枠はブラック、ネイビーまたはグレー(ホワイトは不可 とし、メーカー名はメガネ枠の本来の幅以内とする。グラスの眉間部分へのメーカー名もメガネ枠の本来の幅以内とする。なお、メーカー名はメガネ枠と同色とする。また、著しく反射するレンズのサングラスの使用は認めない
- 大会に参加するチーム・審判員の注意事項
- アマチュア野球内規
- バッタースボックスルール(必携 Ⅲアマチュア野球内規 ②バッタースボックスルール 補足 2025 年沖縄県野球連盟)
- 「打者が投球に対して バット を振った場合」とは、スイングの余勢で打席から出ざるを得ないと判断されるような場合のことである。出た場合は、速やかに戻る
- 「打者がバントをするふりをした場合」とは、セーフティバント等でバントの余勢で打席から出ざるを得ないと判断されるような場合のことである。出た場合は、速やかに戻る
- 【原注】本規定は積極的に反則行為を取りにいくものではなく、試合のスピードアップを目的としたものである。したがって、審判員による事前の “選手への促し“ を前提とする
- 【注】本規定のペナルティは、選手個人に対して与えられるものである
- バッタースボックスルール(必携 Ⅲアマチュア野球内規 ②バッタースボックスルール 補足 2025 年沖縄県野球連盟)
- 質疑応答
- ファウ ル地域のボールデッドライン(Ⅴ ① b)を越えた送球に対する処置はエンタイトル・ワンベース(Ⅴ ① a)を適用する(必携 Ⅳ質疑応答 5.00 試合の進行 44 改)
- 内野ゴロを打った打者走者をアウトにしようとした内野手 が 一塁に悪送球し、ボールデッドライン(ベンチを含む)を越えた場合は、打者走者が一塁に到達したとみなし、そこから1つの塁を与える。その他の走者 も次の塁に到達したものとみなし、そこから1つの塁(投球当時の占有塁から2つの塁)を与える
- 一塁 (または三塁)走者に対する牽制球が ボールデッドライン(ベンチを含む)を越えた場合は、投手板上からの送球も、投手板を外した場合も同じく、走者に1つの塁を与える
- 前述の a b を除く野手の送球が ボールデッドライン(ベンチを含む)を越えた場合は、走者に ボールデッドラインを越えた時の占有塁から1つの塁を与える
- ファウ ル地域のボールデッドライン(Ⅴ ① b)を越えた送球に対する処置はエンタイトル・ワンベース(Ⅴ ① a)を適用する(必携 Ⅳ質疑応答 5.00 試合の進行 44 改)
- 索引
- 用語の定義
- エンタイトル・ワンベース:走者に2個の塁を与えることが、守備側に極めて不利になるという判断から適用されるルール
- ボールデッドライン:競技場を囲うスタンドまたは柵に替わる区画線
- 用語の定義
- 審判員のために
- 審判に関する取り決め事項
- 球審は、1回表 およ び1回裏開始前、投手へ新しいボール(=未使用球)を手渡す。ただし、大会本部の意向により、未使用球ではなく、洗浄済みの使用球を採用しても構わない(必携 Ⅳ審判員のために 審判員に関する取り決め事項 二球場への到着から試合終了まで 7 改)
- 控え審判員として、現行試合の担当審判員を除く審判員にその任を与えることとする。
控え審判員は、休憩中であっても現行試合を注視し、担当審判員と協議したり、誤りを訂正したりする(必携 Ⅳ審判員のために 審判員に関する取り決め事項 三控え審判員 改)
- 審判に関する取り決め事項
- 附則
- 2025年5月 本確認事項を施行する

